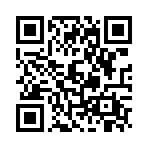2009年02月26日
『静かに見守る』



もしも、子どもが、不登校やひきこもりになったときには、どう対処したらよいのでしょう?
親は、戸惑い、不安になり、何とか登校させたいと思い関わってしまうかもしれません。
しかし、援助機関で勧められてきた方法は、無理に、行かせようと「登校刺激」をするのでなく
『静かに見守る』のが正しい対処法であるとしてきました。
しかし、この『静かに見守る』ということが、なかなか難しいことなのです。
『静かに見守る』とはどういうことでしょう?・・・・・
『静かに見守る』という名目で「何も言わない、何もしないで、ほおっておく。」ということではなく、
また、「腫れ物に触るようにすること」でもなく・・・・・
子どもとのその距離感が大切なのではないでしょうか?
「あなたの気持ちが落ち着いて、話せるようになったなら、お母さん、聴く準備はいつでも出来ているよ。」
ということを伝えたり、
「話したくなったら話せばいいし、今はゆっくりと休む時なのかな。でも、食事はいつものように一緒にとろうね。」
「あなたの生活が、昼夜逆転しないように、私たちは今までどおりのリズムで生活したいと思うのよ。」
と、「人としての親切」な態度で接するのが『静かに見守る』距離感なのだと思います。
『静かに見守る』とは「人としての親切・思いやり」を添えたものであるのですね。
それは、本当に難しいこと。しかし、それが出来ているお母さんがおられます。
敬服します。その方にあるのは、見守ることのできる勇気と無理な期待をしない自覚だと感じました。
相手や自分を責めることなく、哀れむことなく、
「誰にとっての問題」で「誰が解決していく問題」なのかを考えてみれば、
親はその時が来るのを『静かに見守る』しかないのです。
不登校やひきこもりばかりではありません。
子育てにおいて「子どもが何か、自分で解決しなければならない問題を抱えているな・・・」
と感じたときこそ、子どもを尊重し、「この子にはそれを乗り越える力がある」と信頼し、
『静かに見守る』ことができるかどうか、親は試されているときなのですね。
子どものこころの世界に寄り添いながら『静かに見守る』
――― 親であるかぎり永遠の課題です。―――