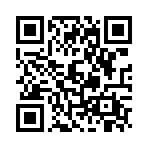2009年02月28日
苦手なこと

【子育てを通して発達障害の理解に近づくことは、実は、
自分の子どもを理解することになるのだと感じています。】
どういうことかというと、
例えば、わが子に苦手な事があるとします。
親は、どうしてもその苦手な事をなおしたり、克服して欲しいと願いそれを一生懸命にして
させようとします。
しかし、考えて見ますと、苦手な事は、苦手だから上手くできないわけです。
それを、直したり、克服したりする事は容易ではないのです。
ですが、親はどうしても、それを、「努力が足りない、忍耐が足りない、
人と同じようにできない、繰り返しやりなさい、できるようになるまでやりなさい・・・」
と、関わりがちです。
確かに、努力して出来るようになる事もあります。
しかし、それは『容易ではないのだ』ということです。
親はそれを忘れがちです。
「何であなたはできないの?」
「みんなと同じようにできないの?」
そう繰り返し言ってみたところで、できるようにはならないでしょう。
子どもは更に勇気がくじかれ、自尊感情が低下し、今まで出来ていたことさえ
できなくなってしまう可能性もあります。
人は、それぞれ苦手な事を持っているのです。
この、苦手な事を、人よりも多く持つのが発達障害の子どもたちです。
彼らは、「人と比べて同じようにできないこと・苦手なことも多い」けれども、実は、
「人より更に良くできる」ということがあるのです。
ですから、発達障害とは、発達の遅れではなく、発達の凹凸だといわれます。
発達障害を持つ子どもたちへの関わり方は、
『彼らの長所や得意なところに注目し認めて伸ばし、肯定感を高めながら、
苦手な事もスモール・ステップで、少しずつできるように支援していきます。』
それはそれは、容易ではないのです。
行きつ戻りつしながら出来るように支援して行くのです。
この子育ての視点と方法は、どんな子どもにも有効だと感じています。
「どうしてできないの?」「がんばりなさい」
では、決して出来るようにはならないのです。
2009年02月27日
H21.3.5 『くさなぎ井戸端会』開催します。

年度末、最後の『くさなぎ井戸端会』です。
転勤が決まった方、進学、進級、新生活・・・
4月からまた新たな気持ちでスタートするにあたり、
私たち親も一年間を振り返って、大いにお互いを労い合いましょう!!

さて、今回のテーマは・・・・
『”子どもの世界”発見トーク』
一年間を振り返って、子どもとの日々の関わりのなかから、
嬉しかったこと、困っていること、子どもの変化、喜びなど・・・
みんなでお話しをしながら、”子どもの世界”を覗いてみませんか?
新しい発見があるかもしれません!
日 時 : 平成21年3月5日(木)10:00~13:30
場 所 : 長崎新田スポーツ広場(交流センター) 2階
駐車場あり
参加費 : 500円
昼食をご一緒できる方は、ランチをお持ち下さい。
お子様ご同伴でどうぞ!

尚、『くさなぎ井戸端会』は、当事者の子どもを持つ親、そうでない親、
お父さん、お母さん、学校の先生、学生さん、支援者の方・・・
いろいろな立場の方が集まり、ここでは平らに話しをします。
お互いの対場を尊重し建設的な意見交換をします。
初めての方でも大丈夫。お気軽にご参加くださいね。
お誘いあわせていらしてください。
たくさんのご参加をお待ちしております。
お申し込み、お問い合わせは。。。。
http://www.locoms.com/
2009年02月27日
ストレスマネジメント





現代に生きる子どもたちの抱えるストレスは、相当なものです。
そして、少し前から、『疲れやすい小学生』が問題になり、今では、
小学生の4人に3人が「朝なかなか起きられない」というデータさえ出ています。
このような小学生は、精神的にはストレスを抱え、肉体的には体のだるさ・疲労感を抱えています。
皆さんはいかがでしょうか?
自分のストレス解消法をお持ちですか?
ストレスを自覚していない人も多いと思います。しかし、体がそれを表してはいませんか?
肩こり・腰痛・頭痛・イライラ・寝起きが悪い・・・
子どももそうです。
いつもと様子が違う、イライラ、爆発、当り散らす、落ち込む・・・
そんなときは、それがストレスから来るものかもしれないということを自覚させていくと良いようです。
「イライラするんだね。体のどこかが緊張しているかな?
おなかの中に何かを抱えてしまっている感じかな・・・・?」など、
自分の体の状態を子どもに自覚させるように関わりながら
「ストレスというものがあってね。ストレスの壺がたまり過ぎると、心や体が不調を訴えるんだよ。」
と話してみてはいかがでしょうか?
そして、「お母さんと一緒にそのストレスの壺の中身を減らしてみよう。」と取りくみます。
「イメージ法」(・・・過去にあったよい時のことを思い出す。また、そのときの音、香り、風景などを思い浮かべる。)
「呼吸法」
「体ほぐし」など、子どもに合った方法を探します。
ポイントは、いつでもどこでも気軽にできて、習慣化しやすい簡単な方法で、リラックスが得られるもの。
子どもにどれが良かったか聞いてみて子どもの使いやすいものを取り入れてみましょう。
そして、
・大勢の人の前での発表で不安なとき。
・大事なテストの前での集中力アップに。
・嫌な事があった後の気分の切り替えに。
・気合を入れたいとき。。。
などに、使ってみるように言うのです。
生きていく上でストレスを感じないわけにはいかないでしょうが、ストレスと上手く付き合いながら、
自分なりに、ストレスを自覚しコントロールする方法を持つと、心も身体も今よりは少し軽くなるはずです。
親子でストレスマネジメントすることで、親子関係も改善され、子どもが抱える不安やイライラを
軽減する一助けとなるものが見つかると良いですね。

2009年02月26日
『静かに見守る』



もしも、子どもが、不登校やひきこもりになったときには、どう対処したらよいのでしょう?
親は、戸惑い、不安になり、何とか登校させたいと思い関わってしまうかもしれません。
しかし、援助機関で勧められてきた方法は、無理に、行かせようと「登校刺激」をするのでなく
『静かに見守る』のが正しい対処法であるとしてきました。
しかし、この『静かに見守る』ということが、なかなか難しいことなのです。
『静かに見守る』とはどういうことでしょう?・・・・・
『静かに見守る』という名目で「何も言わない、何もしないで、ほおっておく。」ということではなく、
また、「腫れ物に触るようにすること」でもなく・・・・・
子どもとのその距離感が大切なのではないでしょうか?
「あなたの気持ちが落ち着いて、話せるようになったなら、お母さん、聴く準備はいつでも出来ているよ。」
ということを伝えたり、
「話したくなったら話せばいいし、今はゆっくりと休む時なのかな。でも、食事はいつものように一緒にとろうね。」
「あなたの生活が、昼夜逆転しないように、私たちは今までどおりのリズムで生活したいと思うのよ。」
と、「人としての親切」な態度で接するのが『静かに見守る』距離感なのだと思います。
『静かに見守る』とは「人としての親切・思いやり」を添えたものであるのですね。
それは、本当に難しいこと。しかし、それが出来ているお母さんがおられます。
敬服します。その方にあるのは、見守ることのできる勇気と無理な期待をしない自覚だと感じました。
相手や自分を責めることなく、哀れむことなく、
「誰にとっての問題」で「誰が解決していく問題」なのかを考えてみれば、
親はその時が来るのを『静かに見守る』しかないのです。
不登校やひきこもりばかりではありません。
子育てにおいて「子どもが何か、自分で解決しなければならない問題を抱えているな・・・」
と感じたときこそ、子どもを尊重し、「この子にはそれを乗り越える力がある」と信頼し、
『静かに見守る』ことができるかどうか、親は試されているときなのですね。
子どものこころの世界に寄り添いながら『静かに見守る』
――― 親であるかぎり永遠の課題です。―――
2009年02月25日
何度、同じこと言わせるかな~!!

「ったく、もう!!何度、同じこと言わせるかな~!!あ〜、今日も朝から嫌になっちゃう。。。 」
」
と言いながら・・・・子どもへ、
『早くしなさい!』
『がんばりなさい!』
『ちゃんとしなさい!』
『みんなと同じに!』

って何気なく、習慣となり口ぐせとなって声掛けしていませんか?
実は、これらは、組織が上手く機能して動くための特性を表しているものなのです。
S スピード『早くしなさい』
S 生産性 『がんばりなさい』
K 管理強化『ちゃんとしなさい』
K 画一化 『みんなと同じに』
この『SSKK』を人間に当てはめてしまうのが現代だといわれています。
確かに、日々の子育てにおいての声掛けは、まさにこれです。
仕事で求められる完璧さ(スピード、生産性、管理強化、画一化)を子育て求めてしまいがちです。
しかし、仕事では通用する「完璧さ」は子育てには通用しないのです。
通用しないことを、やり続けているから、子育てが苦しくなるし、大変になるのですね。

『SSKK』を使わない習慣を身につけられるとよいですね。
そこで、子どもに対して使いたい『SSKK』を考えて見ました。
S 信頼 『あなたにはできる能力があると信じているよ。』
S 尊重 『ありのままのあなたでいいと思うよ。』
K 感謝 『あなたにはいつも感謝しているよ。ありがとう。』
K 貢献 『お母さんがあなたの力になれることがあったら言ってね。』
みなさんのお家のSSKKを考えてみてくださいね
2009年02月24日
すぐに親の意見を求めて来る子



子どもが、
「お母さん、次何したらいい?」
「何で遊んだら良い?」
「今日は、誰と遊んだら良いの?」
『子どもがこう聞いてきて困ります。親が何でも決めてくれると思っているのですから。』
というお話しをよく聴きます。
子どもが自分で考えて意見を持つ前に親に聞いてきてくることが、繰り返されている場合
どんなことが考えられるでしょうか?
子どもが自分で考えない。。。という事はないでしょうか?
自分の頭で考えて、自分の意見を言えるようになるには、
親はどう関わったらよいのでしょうか?
① まずは、子どもに考えさせる事です。
『あなたはどう思う?』『間違いなどないよ。考えてごらん?』
『あなたはどうしたいの?』『するとあなたはどうなるかしら?』
と、子どもに考えさせる言葉を投げかけます。
② 親がすぐに指示や提案をしないこと。
指示、提案、命令、強制・・・で子どもと関わると、子どもは
『どうせ自分で考えても、母ちゃんが何でも決めてしまうんだ・・・』
と思うでしょう。
例えば、子どもが『お母さん、今日は、手袋していった方がいいの?』と聞いてきたら
すぐに『そうね、していきなさい。』と答えずに、
『さあ、どうかしら?あなたはどう思う?必要かしら?お外にでて寒いかどうか試してくる?』
などと子どもに考えるという経験をさせることです。
『子どもがこう聞いてきて困ります。親が何でも決めてくれると思っているのですから。』
というのは、実は、
些細な事だからと、すぐにこちらから指示を出してしまうことを繰り返し習慣にしてしまったことで、
『親の意見を求める子』にてしまっていると感じいています。
親の関わり方一つで、子どもは自分で考えようとするものですね。
2009年02月23日
子育ち・親育ち『特別支援教育』②

H18年9月・・・当時、発達障害に関する親の会など、当事者の子どもを持つ保護者の会は
あっても、そうでない者が発達障害に関して学びたいと思っていても参加させていただける会は
無いのだということに気づき、立ち上げたのが『くさなぎ井戸端会』でした。
ここでは、障害を持つ子どもの親もそうでない親も、双方が互いの理解に近づきながら
子育てを通して発達障害について学ぶ・・・ということをしてきました。
各所でのこのような学習会や地域活動を通して感じていることは、
残念ながら、相変わらず誤解を持たれている保護者の方もおられる一方で、実は、
発達障害の理解に近づきながらわが子の人間関係を育てて行ききたい
と考える保護者も確実に増えてきていると実感しています。
こうした保護者や地域の人々の理解が広がる中での更なる課題は、
福祉&教育&地域が三位一体となって行くことだと考えています。

平成19年4月から学校現場で「特別支援教育」スタートされてきてから、
問題はたくさんあるでしょうが、熱心に取り組んでくださる学校や先生方も少しづつ
増えてきているように思います。
しかし、まだまだ発達障害の子どもたちの二次障害や薬の常用の問題は減少している
というところにまでは行き着いてはいません。
そこで、福祉&教育&地域が、相互に更なる理解を深めながら連携し、
意識の合意形成をしていく必要性を強く感じています。
ここで、私たちにできることは何でしょう?
障害を持つ子どもの親もそうでない親も一緒に考えて行けたらと思うのです。
すべての子どもたちの未来の為にも【福祉&教育&地域の三位一体】について、
諦めずに模索し続けていきます。

2009年02月22日
子育ち・親育ち『特別支援教育』①

2008年5月より【子育ち・親育ち『特別支援教育』】と題した学習会を
交流館やPTA講座で開催して来ました。
ご存知ですか?
「特別支援教育」はH19年4月から学校現場でスタートされました。
これまでも、通常の学級の中で、生活や学習の場面で困難を抱えている子どもたちがいましたが、
何の手立ても受けずにいました。この子どもたちの学ぶ権利を支えようとスタートしたのが、
この「特別支援教育」です。
しかし、「特別支援教育」は、発達障害の子どもたちだけでなく、新しい「荒れ」の対象となる子ども、
いじめ、不登校、非行、悩みを抱えた子ども・・・・など
すべての子どもに必要な教育だと考えます。
学習会は「特別支援教育」を上手く推進していく為にも「家庭と学校は子どもを真ん中に挟んで、
もっとお互いに信頼し合いましょう!
家庭では、子どもにまなざしを置いて、しつけや教育をして行きましょう!」
と保護者の皆さんと共に考えるものとなっています。
その中で以下のような参加者のお声をたくさん頂いて来ています。
*****
「特別支援教育」という言葉だけを聞くと、何か特別な私たちとは少し離れたところで行われる教育なのかなという印象でした。
でも今日のお話で特別な子ども達への特別なことではなく、誰にでも対応されるべきことなのだと気付かされました。
改めて考えてみれば、子どもは学校だけで学び育つわけではなく、一番重要なのは家庭なのだということが分かりました。
自分の子や周囲の子ども達によく目を向けることを皆がすれば、何かが変わって行くのかな・・・変わっていくと思いました。
*****
「特別支援教育」を理解していただくとともに子どもへのまなざしが変わることで、
誰もが、『支援し・支援される』関係になれることを願っています。

2009年02月22日
今日もやっちまった〜!!

「こんなに激情するつもりはなかったのに・・・」
「子どもに八つ当たりしてしまった・・・」
「叱り始めたら止まらなくなっちゃった・・・」など
『あ〜やっちまったな〜・・・
 』という経験は、どなたにもあるのではないでしょうか?
』という経験は、どなたにもあるのではないでしょうか?
感情のコントロールが出来ないのは子どもばかりではありませんね。
多くの親が「子どもに対して、自分の感情をコントロールするのは難しい」と感じているようです。
どんな時に感情のコントロールが難しくなるのでしょうか?
『HALT』だそうです。
Hungry 空腹
Anger 怒り
Lonely 孤独
Tierd 疲れ
こんな状態のときには要注意!!
まずは、
『今、私はHALTである』ということを自覚し、
『今は、子どもと上手く関われない』ということを明らかにし認めましょう。
そして、子どもに伝えてみてはいかがでしょうか?
『お母さん今、お腹が空いてイライラして来ちゃった。。。 』と。
』と。
思いやりのある子どもは、お菓子を分けてくれるかもしれません
よ。
あるいは、『お母さん,今日とっても疲れているのよ。。。 』と
』と
背中でも丸まっていたなら『肩たたきしてあげる!! 』なんて嬉しいことにもなるかも。
』なんて嬉しいことにもなるかも。
親は、今の自分の感情を隠すのでなく、相手に素直に伝えることで、
感情を爆発させるという方法で伝えるという必要がなくなるものです。
試してみてくださいね
2009年02月21日
あ~、かっぽれ、よ~い~っとな、よいよい!!
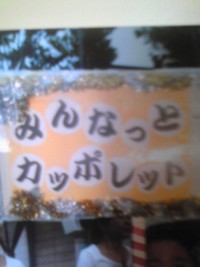
う~。。。。。“花粉deダウン”のこの時期に
なんと、今年も『清水みなと祭り』参加連としての活動が始まりましたよ~。

「え~ッ!!もうですか~!?」って、
はい。。。まだまだ、気分はコタツの中ですが・・・・
チーム
 『みんなっとカッポレット』
『みんなっとカッポレット』

さて今年はどうなりますか?
年々、平均年齢があっぷあっぷ
 してきています。
してきています。
みなさま~、今年も楽しく踊っちゃいますか~?
その前に今夜楽しいミーチング。
久々に、メンバーとの再会。
うふふふふ・・・・・・・・・・・・・
♪酔~い~っとな、好い、良い!!♪
『みんなっとカンパイット』!!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『みんなっとカッポレット』・・・・HPでみてね
http://www.locoms.com
2009年02月21日
『んねっ?怒らないでしょ。』

娘がHちゃんと2人で公園に遊びに行きました。
『ただいま~っ!!ね~母ちゃん、来て、来て!』
呼ばれて玄関まで出て行くと、靴と靴下をぶら下げた2人がニヤニヤして立っています。
私 『あんりゃ、ま~。寒くないかい?』
娘 『うふ。Hちゃんが川に、はまった。
んで、あたしもお付き合いして、裸足になって歩いて帰ってきたよ気持ちよかった~!!』

私 『うんうん。そりゃ~楽しそうだ!!んで、今からどうしたい?』
娘 『がはは・・・・んねっ?怒らないでしょ。うちの母ちゃんは、
こういうことは怒らないんだよ。』
私 『普通は、こういうことで怒られるの?・・・はい、スリッパはいて、お風呂にGo!!』
Hちゃん『(下向いてニヤニヤ・・・・)』
私 『さて、H子ちゃんや。そのぬれた靴下をどうするかだ。服はどうする?
いくつか方法があるね。考えてごらん?Hちゃん、あなたはどうしたいの?』
Hちゃん『。。。靴下は洗いたい。。。。乾かしてもって帰りたい。服はこのまま。。。』
私 『よっしゃ、自分で考えてよく言えたね。H子ちゃんの考えを尊重して、じゃ~そうしよう!』
後は2人楽しくお風呂でゴシゴシ。


どうも子どもたちの間で最近話題になっているらしいのですよ。
テーマ:『母ちゃんが怒るとき』・・・「どんな場面でどんな風に噴火するか?」
をみんなで具体的に話しあっているようですよ。
『きゃ~!!怖い!!』って?
子どもから見た“大人”は、私が“子どもだった頃見ていた大人”と何ら変わらないのです。
やっぱり、子どもの世界って、素敵ですよ。

さて、私が怒らなかったのは、何も怒る必要がない場面でしたから。
危険を伴わない範囲で、子どもが楽しみながらも、失敗したことは、
次に“どうしたら良いかを考えさせられる”良いチャンスです。
答えは子どもが出すのです。出した答えを実行するのも子どもです。
せっかくのチャンスを、頭から叱ってしまったら、子どもには、
“叱られ”たという事実だけが無残に残り、そこからは何も学べません。
この場合、私の権利を奪われたり、何も責任を負わされたりしてはいないのですから、
怒る必要も無かったのです。
子どもが自分で考え、行動し問題解決に取り組む姿を見ているとき。。。
“子育てって楽しい”と思える瞬間です!!
2009年02月20日
ナチュラルサポーター

支援を必要としている子どもとは、障害を持つ子どもに限りません。心に悩みや不安を抱えている子。虐待を受けている子、非行、不登校・・・・。みんな、支援を必要としている子どもたちです。
◆クラスの中に『どうしてよいのか、困っていたり』『支援を必要としている子ども』がいたとしたら・・・
決められた人が、その人の“お世話係”のようになって支援するのでなく、そこにいる誰もが必要に応じて自然に「支援し、支援される」そんな関係になれたらいいな~と感じます。






先生自身がナチュラルサポーターとしての姿勢を示せば、子どもたちもその姿勢から学ぶことでしょう。
そして、何よりも、親がわが子のよきナチュラルサポーターであらねば、子どもはナチュラルサポーターとしての役割を学びません。
親の子どもに対する関わり方が、子どもの社会的態度や対人関係を形成する一要因となります。
各家庭での子どもとのかかわり方が大切なのだと感じます。
2009年02月20日
お母さんの心配“ひまわりちゃん”




子どもの“こだわり”への“とり越し苦労”というお話しです。
以前、お友達のママさんからこんな相談を受けました。
「みのちゃん、このA子は、“黄色”のものしか選ばないのです。どうしたらよいのでしょう?この先心配なのです。。。。」(そういえば、こんな芸能人がいましたっけ・・・?!)
靴も服もタオルも布団も、おもちゃ、歯ブラシ、リボン、コップにお皿、かばん、ティッシュ・・・
身につけるものや自分のものなど、すべて黄色。黄色以外の色は、何としてでも拒否したそうです。“黄色”へのこだわりがあったのですね。
そこで、私は、
みの 「へ~!偉いわね~ 2歳で自分の好きな色を持ち、自分の考えをお母さんにちゃんと言うのだものね。黄色。素敵よね~。
2歳で自分の好きな色を持ち、自分の考えをお母さんにちゃんと言うのだものね。黄色。素敵よね~。 」
」
ママ 「ええっ?そういうことで良いんですか~? 」
」
みの 「ええっ?じゃ~、どういうことなら良いんでしょうか~?
うふふ、あのね、例えば、A子ちゃんがお母さんの物も全て黄色にしなければいられないってわけでは、ないでしょ?」
ママ 「そこまでは、言いません。。。 」
」
みの 「たとえば、黄色以外の物でも食べるんでしょ?
それに、黄色と見れば見境なく盗んでくるってわけじゃ~、ないんでしょ?
んじゃ、何の問題があるの?“黄色は素敵” って、このA子ちゃんにはわかっているだけのことじゃない?」
って、このA子ちゃんにはわかっているだけのことじゃない?」
ママ 「でも、一生、黄色ってことはないですよね? 」
」
みの 「さ~、そんな子は見たこたないけど、その場合でも、“マスタードちゃん”より“ひまわりちゃん”の方がいいわね。」
ママ 「は??????? 」
」
みの (A子ちゃんに)「A子ちゃん、“ひまわり”っていう、背が高くて黄色い大きなお花は好き?」
A子ちゃん「すっきっ~!! 」
」
みの 「んじゃ~、今日からA子ちゃんを“ひまわりちゃん”てよんでもいいかしら?」
A子ちゃん「いっいっ~!! 」
」
その“ひまわりちゃん”と数年ぶりにお会いしました!
まさに“ひまわり”のようにスラリとした背が高く、笑顔輝くなんとも美しいお嬢さんに成長しておられるではありませんか?
感動してしまいましたよ!!

黄色???
黄色など一つも見当たりませんでしたよ。
人間てのは変わるものなのです!!
2009年02月19日
あるわよね~。。。「くせ」や「こだわり」

2・18【“こだわり”をやってみて】の続きです
「くせ」や「こだわり」・・・・たとえば、
・身体を洗うときは、首から洗う。
・ラーメンの上のナルトは一番最後に食べる。
・いつも同じ道を通ってしか目的地に行かない。
・どんなときも、必ず右足からくつをはく。
・家中の全ての鍵を点検してからでないと眠らない。
などなど。
強い、弱い、多い、少ないの差はあっても、誰にでも「くせ」や「こだわり」はあるものです。
発達障害の一つの表れとして、この“こだわり”があります。
『障害児が育つ放課後』で白石正久氏は、こうおっしゃっています。
【「くせ」や「こだわり」は『がんばりたいけどがんばれない』という前向きな葛藤をする心の支え「心のツエ」としての役割があるのです。】
時に、その「くせ」や「こだわり」を持つことで、いろいろな弊害を生むとしても、 「心のツエ」としての役割があるのだから、いきなり取り上げるのではなく、それを持ちつつも挑戦したくなる雰囲気を作ることが大切だといいます。
考えて見ますと、見通しが立たなくて不安な時や心配事のあるとき、急激な変化に柔軟に対応できない時・・・などに、「くせ」や「こだわり」行動は強く出るように思います。
「それを持ちつつも挑戦しながら、それがなくても挑戦できるように」なっていくことが大切なようです。

2009年02月18日
2009.2.10 ママpika学習会 参加者アンケート



第15回 【子育てトーク&リラクセーション】
お母さんがpikapika輝くと子どもの笑顔も輝きます!! 

今回は、現役大学生3名が参加くださり、子育てトークも盛り上がりました。
参加者の皆さんの許可を得て、ここに一部をご紹介させていただきます。
●T・K(将来教員を目指す大学生)
教育現場に立った時に、保護者の方とどう関わって行くかが、具体的に知れて、自分が教師になった時に実行して行こうと思いました。
●Y・A(将来教員を目指す大学生)
保護者の方の悩みや先生に対する思いを聴けたことが、とても勉強になりました。保護者の方と “会話”をして行きたいと思いました。又、子どものことをたくさんほめられる先生になろうと思いました。こちらの思いを押し付けるのではなく「どうしてそうなったの?」「あなたは、どうしたい?」という問いかけを大切にして行きたいと思いました。ありがとうございました。
●T・S(将来教員を目指す大学生)
保護者の方々が持っている不安や現場の先生に求めるものが少し見えてきました。子どもの発達段階に応じた成長課題や基準を示されることで、安心を得られるというのは、今までなかった考えでした。子どもを認めるために自分自身を肯定する必要があるということ、大変勉強になりました。本日はありがとうございました。
●N・T
今日も日頃のグチが言えて、スッキリしました。子どもが計算カードをやるときに[深呼吸3回]などとやらせていましたが[リラックスする]という方向ではなく[集中させる]という親の都合の良い方向に仕向けていたな〜と気づきました。ここに来ると、色々なことに気づかされます。気づいたことを活かして行けきたいな〜。
●S・T
リラクセーションを日々やることによって、自分のものにして行き、何か不安な時に活用できるようにしたい。日々、取り入れて、親子で習慣にしていきたい。
●O・T
子どもの良いところ、認めてあげたいところも見えてきました。自分とは違う人格、人生なのだから、自分の考えを押し付けずに認めて見守ってあげたいなと思いました。そして、まず自分を見つめ直し、認めてあげて、人の意見に左右されない自分を持って行けたら良いなと思いました。兄弟だから比べたりせず個性を認めて私が受け止められる大きな人間になりたいです。

●I・I
久しぶりのママpikaで、また気持ちがすっきりしました。子どものことで上手く行かない時でも、上手く行っていても、ここでは、子どもへのまなざしをおいたな関わり方に接することが出来るので、家に帰ってから、心穏やかな母になれる気がします。呼吸法、イメージトレーニング、早速子どもとやってみます。
大勢の皆様、お忙しい中をお出かけくださいましてありがとうございました。






2009年02月18日
STEP勇気づけセミナー・体験会のお知らせです。
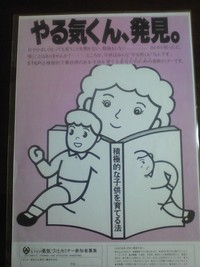
日本の子どもたちは 「大人に言われると素直にやるのに、自主的に取りくめない子どもが増えている」といわれています。。。。。。。。。。。。。。
STEPは児童心理学の理論やカウンセリング、コミュニケーションの手法から開発された親支援プログラムです。
STEPを知ると、親子関係、人間関係が楽になり、子育てにゆとりが生まれ、
子どものよいところがどんどん見えてきます。
各地のカルチャーセンター(朝日・読売)や行政の子育て支援、教職員、保育士の研修にも取り入れられ、子どものやる気と責任感を育てる方法として高い評価を得ています。
STEPは「なぜ、親の言うことを聞かないのだろう?」
「なぜ、親を困らせることばかりするのだろう」
というような子育ての問題を自分で解決できるようになる考え方です。
子育てのヒントが見つかるかもしれません。
体験会
日 時/ 2/24(火)
9:45 ~12:00(9:35受付)
会 場/ 長崎新田スポーツ交流センター
会 費/ 500円
詳しくはHPをごらん下さい。お申し込みお問い合わせは
http://www.locoms.com
よりお願いいたします。
2009年02月18日
“こだわり”をやってみて
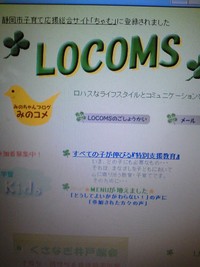
「こだわっている」ことをお持ちですか?
たとえば、「○○社の調味料しか使わない」とか、「方位にこだわる」とか・・・・
“こだわり”とは?・・・・○些細な事を必要以上に気にすること
○細かな点に気を使って価値を追及すること
「“こだわり”???へ~、これって、どんな感じなのかしら?」
と改めて、私のなかで、この“こだわり”を体験的に拘ってみようと始めたのが
『毎日欠かさず更新“みのコメ”』でした。

誰かが毎日更新せよ、といったわけでもなく、更新する必要性もなかったのですが、あえてこだわってみたのです。
そして、このこだわりを遂行しようして来たこの73日間は、辛くもあり、恐怖でもあり、楽しい日々でもありました。


そんな日々も・・・んま~、それこそつまらない事で、ひょんなことから、この「こだわり体験」は
潰えてしまったわけですが・・・(昨日のブログをごらん下さい。)
しかし、ブログのカレンダーの16日のとこにだけ、アンダーラインがない事に気づくと、何とも悲しくも悔しく・・・
しまいに、
痛恨!
 悲嘆!!
悲嘆!!
 悔恨!!!
悔恨!!! 絶望!!!!
絶望!!!! パニック~!!!!!
パニック~!!!!!
 ・・・・
・・・・という気持ちになってきましたよ。
“こだわり”とは、周囲にとっては、「そんなつまらないことで・・・」と言われそうなことでも、
当人にとって見たら、「つまらないことなんかじゃないんだ!!なんて失礼な!!」ってな、
かなり真面目なことなのですね。
そして、“こだわり”とは自分が自分である為の一種の装置であり、儀式であり、作法であったりするのです。
あたかも自分の一部分にでもなってしまったようなものなのです。
自分にとっては、たとえ意味がなくても、大事な大事なものなのですね。
それが“杖”のように支えとなっている事もあるし、自分の首を絞める“リード”となることもありました。
さて、皆さんには、そんな“こだわり”がありますか?
2009年02月17日
マスク星人

昨年の11月から、毎日欠かさず更新してきた“みのコメ”を グア~ン、グア~ン



どこまで続くか、勝手に自分で挑戦していたのですが。。。
たとえ、40度近い熱を出しても、睡眠時間が3時間の日も、それでも更新にこだわってきたのに~
な、なんと、こ、こんなことで・・・・・お休みをしてしまうなんて。。。
こりゃ、想定外でしたよ・・・
昨日は、STEPのフォロー会を気合で乗り切り、次第に記憶の遠のくなか、何とか無事に帰宅すると、そのまま白雪姫のように眠りに付いたのですよ。(白雪姫?)
気づくと朝でしたよ
となりに眠っているはずの七人の小人ならず、息子や娘を見ると
。。。。な。な。な。んとっ。。。。。。そこにいるのは、
マスク星人でしたよ。
そうなんです。。。。只今、われら、酷い花粉症に苦しんでおります。
週末、東京から帰った私は、駅に降り立ったとたん、いや~な予感がしましたよ。
空気が、心なしか、どんより重かったですからね。
今日一日は、顔中をマスクで覆う、マスク星人で過ごします。
顔のパーツは一切出しません。たとえ、おまわりさんに、職務質問されても、金輪際出しませんよっ!!
それでも、大概わかると思いますよ。。。
われら家族以外のマスク星人は、まだそうは歩いちゃいませんから。
街で見かけたら「もしや、みの星人?」と声をおかけくださいましよ。
2009年02月15日
お泊りでしたの。

先週末は、2日間、静岡⇔東京⇔静岡
 静岡⇔東京⇔静岡
静岡⇔東京⇔静岡 と、行ったり来たりの繰り返し。。。
と、行ったり来たりの繰り返し。。。でしたが、さすがの身体が持ちません

ということで、今週は、お泊りでしたの

こちら、ビジネスホテル『一茶』
清潔で、意外とお部屋が広くて落ち着きましたわ。

日頃、TVのない生活をしていますものですから、“TV見放題”がこんなにも“贅沢”な代物だとは思いませんでしたよ


あ~、久しぶりの一人っきり!!



開~放~感~っ!!
かつて、山口百恵ちゃんも歌っていたではありませんか。。。
♪♪ ♪♪ これっきり、これっきり、も~、これっきり~ですか~?
 ♪♪ ♪♪
♪♪ ♪♪ってね。
『いいかげんにしろっ!!
 』
』という家族の声が聞こえてきました。。。。。


『 叱られてそら(=そこ)から直にかへる雁 』 (一茶)
ヘイヘイ、帰って来ましたよ・・・・


『ただいま~!!』



2009年02月14日
『たっ、たのむから動くなよっ!!』


♪〜♪〜♪〜♪〜山本リンダ『狙いうち』の曲に乗せてどうぞ!!
♪ぎっくり〜、びっくり〜、ぎっくりびっくり de〜
ぎっくり〜、びっくり〜、 ぎっくり腰 yo〜
ぎっくり〜、びっくり〜、ぎっくりびっくり no〜
この腰わたしの腰じゃない!!(痛っ!!)♪
先日、我が家の おふざけ企画『自作ネタ発表会』のあった日に、なんと、おパ◯ツを取ろうと棚に手を伸ばしたとたん、
素っ裸のそのままの姿で、しばし固まって しまいましたの。
・・・声も出ない とは、このことです。
その姿を見つけた兄は、
「グハハ〜。母ちゃん、新ネタ?新しいギャグにしちゃ〜卑猥だよ 」
」
妹 「しゃべらないギャグも有りか〜 」って・・・・
」って・・・・
私 「ち。。ち。。(ちがう〜!)イ。。。イタ。。(痛い〜!)」

兄 「父、イタ?」
私 「。。。ち。。が。。う。。。ギックリ、腰。。だ。。。」



兄 「え〜?大変じゃん 」(って、全然大変そうじゃない言い方・・・)
」(って、全然大変そうじゃない言い方・・・)
妹 「母ちゃん、とりあえずパ◯ツをはこう!後で、湿布を貼ってあげるよ!」
と、片足ずつ、パ◯ツを履かせてくれたやさしい妹。
私 「う〜・・・、母ちゃんほんとに幸せだよ・・・ 」
」
このとき、本当に心の底から『幸せ』を感じたのですよ。
『幸せってのは、こういうもんだな〜 』
』
と感じさせてくれたぎっくり腰は良かったんだか、悪かったんだか・・・・
しかし、何でもかんでもネタと思われちゃ〜適わないな〜とほほ・・・
さて・・・・・慣れない正座などして、「圧倒的にしびれを切らした足の時」と、
「“思わぬところで、ギックリ〜!!”の ぎっくり腰の時」には、
思わず、こう声を上げたくなりませんか?
 『たっ、たのむから動くなよっ!!』
『たっ、たのむから動くなよっ!!』 



お陰さまで1週間したら良くなってきましたわ。