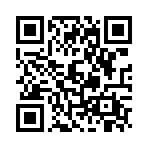2011年10月19日
「第39回くさなぎ井戸端会」参加者の声

参加者アンケートより、皆様の了解を得て、一部掲載させていただきます。
********************
●今日は自分の頭の仲でモヤモヤしたものがあったので、「しゃべることで発散するぞー! 」
」
と意気込んでいたので最初に一気にしゃべってしまって。
それだけでかなり発散しました。
ずーと悩むことはしないんですけど、所々、ぐーんと落ち込むこともあるのでとてもスッキリします。
ありがとうございまーす。
もともと人の話を聞いてる時間が自分の気持ちをおさめることが出来る時間のようです。
かなりスッキリです。<M.N>
●今日もよい時間をすごせました。ありがとうございます。<M>
●今回、初めて一人で(そして久しぶりに)参加させていただきました。
普段は聞くことの出来ないお母さんたちの気持ちや思いを聞くことが出来、頭がほぐれるような思いでした。
どうやって、楽に、楽しく考えられるようになるか。
まだまだ考えていきたテーマだなぁ。
もっと、できるようになりたい!と焦りというよりむしろわくわくする気持ちがもらえました。
ありがとうございました。<教師志望・R.H>
●見方を変えてみると、いろいろな選択がみえてくる・・・というのは頭では判っていたつもりですが、
なかなか身につかない自分がいました。
少し離れて自分を見てみる余裕と自分が楽(楽しい)になる考え方が出来るように、頑張ろうと思いました。
みんなの話を聞いていると、元気が出てきます。
ありがとうございました。<O>
●久しぶりに参加しましたが、やっぱり一番思うことは、皆いろいろ悩みがあるけど、
こういう機会に意見を聞いているうちに、元気にプラスに考えられることです。
今日は、ものの見方・とらえ方、自分ももっと視野を広げて楽しく子育てしていきたいです。<K.I>
みなさま、ありがとうございました。
2011年10月18日
第39回「くさなぎ井戸端会」ご報告②

(前回より続く)・・・・
○私…「私ってきちんとしている」
夫…「そんなことないしー」
人はいつでも完璧であらねば、とおもっていたけど、完璧でなくていいんだな。
選択肢が増える分迷うこともあるだろうが、こうあらねば!と思っていた時よりは楽。
見方が変えられることも知らなかったから、こだわっていることにも気付かなかった。
もしかしたら、これからの私の人生おもしろい?
豊かになったねー!
○教師を目指す大学生
久々の参加。1人だけの学生!1人だけの男!などの理由で、緊張して参加していた!
「いいこと言わなくちゃ!」など考えて参加したが、これから楽しく何回も来ればいいや!
教師の言葉って親に大きな影響をもつのだと再認識した。
○担任の先生に
学年の初め、先生に「どうしたらいいですか?」と聞かれた時、混乱した。
「先生が親に聞くなんて。」
↓捉え方を変えて…
「先生は考えてくれているからその言葉がでたんだ。」という気付き
その後、先生ととてもよい関係を築くことができた。
○楽に生きられる見方を探そう。
楽になる=怠けている。よくない。と感じていた。が自分が楽しいと感じるほうが楽。
○自分の思考癖
自分の癖は「心配性」なんだけど、なかなか治らない。
子どもを信頼できず、ただ心配している自分。
見方を変えることで癖を直したい。
もっとワクワクする考え方ってないかな?と考えてみよう。
○水泳の平井コーチ…
「なぜ、できないのか?」ではなく「なぜ、これができた?」「前回は何でできた?」
と尋ねることで出来たことを認識させる。←リカバリー能力がつく
○生まれて初めて、思い通りにならない存在がわが子。
今までは自分がちゃんとやっていれば、自分の思い通りになっていたが、子どもは、
親の思い通りに動いてくれない。この子と自分は違うんだ、と気づいた。
といって、相手に合わせているばかりではなく、おたがい譲り合って折り合いをつけて。
違う考え方を持ち始めているんだな。とガスを抜く。俯瞰する。
*************
井戸端会を終えて
事実は一つ。でも、それに対する見方・捉え方はいろいろで、それによって生まれる感情も変わってきます。
ならば、自分が(子どもも)ハッピーで楽になる捉え方ができればいいなぁ…と思いました。
「あの人にこう言われた!」ではなく「あの人はこう捉えているんだな」と思うだけで解決の糸口が見つかったり、
気持ちが楽になったりするかもしれません。「他にはどんな見方があるのかしら?」と
思うだけでも気持ちが落ち着いてきたり…。
これって、対子どもだけでなく、対夫、対先生、対上司、対ご近所さん…いろいろなところで役立ちそう♪
とにかく、今回も楽しく話して、少し気持ちも軽くなって帰ることができました。
皆さん、ありがとうございました
^^(O・H)
*************
古代ギリシャの哲学者エピクテトスは、、、、
「私たちの心を乱すのは、現実に起きていることでは無く、起きている事に対する考え方である。」
と言いました。
「起きている事に対する考え方・・・・」この事実に気づくことが大切です。
もしも、心が乱れたとき、
「私は今、○○と言う出来事を前にして、怒りや不安を感じている。
そう感じているのは私自身。
でも、それって本当かしら?本当はどうなのかしら?
このことに関して、他の見方・捉え方はできないかしら? 」
」
と・・・・
「起きている事に対する見方・捉え方・考え方を変えてみる」ということを習慣にすることが出来ると
生活の中で、心乱れることが大きく減ります。
ネガティブな感情に長く浸ることが減るからです。
勇気を持ってやってみてくださいね。
細野 
2011年10月17日
第39回「くさなぎ井戸端会」ご報告
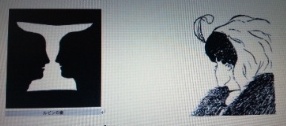
テーマ『物の見方・考え方・捉え方は変えられる?』
日時 6/23(木) 10時~13時半
場所 長崎スポーツセンター
参加者 14名
<まずは『錯視』から…>
↑(写真の絵)
左の絵は、何の絵に見える?
「向かい合った2人の顔」
「果物を載せる脚付きのお皿」が大半を占めていたのですが
ナント、「帽子を被った男の人」が見えていた人も。
同じ絵を見ていても見え方は人によって全く違うのですね。
…ということは、同じ子ども、同じあらわれでも、人によって捉え方は
全く違うのかも…!
別の視点を持つことで、子どもへのかかわり方も変えられたり、
気持ちが楽になったりするかもしれません。
※ちなみに、中学1年生の国語で「視野を広げる―ちょっと立ち止まって」という教材で、
この錯視が扱われています。
<グループディスカッションのシェアリング>
○一年生の女子。隣の子が騒いでも、その子に注意をできない子ども。
先生…「隣の子がうるさい時は、注意ができるようになってほしい。」
本人…「隣の子がうるさいとは思っていない。」
親 …「周りの子に引っ張られずに集中できることがすばらしい。」
先生、子ども、親の見方・捉え方はそれぞれ違う。
先生の捉え方が良い悪いではない。
どちらかしか見えないと、追いつめることになる可能性がある。
価値観で、見え方が違ってくるのかも。
○骨折しているのに、スポーツの練習に行きたがる男子。
本人…どうしてもやりたい。
親…迷った末行かせた。体験させた上で、リスクを背負っていることを話した。
その結果「やめておく」と本人が決めた。
安全をとるのか、勢いをとるのか。
最後に決断するのは自分。
○指示待ちっ子。
指示待ちになってしまったのは、今まで指示をたくさん与えられてきて、考える場が
なかったから。
「あなたはどうしたい?」という問いかけをしていく必要がある。
自分も指示待ちっ子かも!?他の人の考えを聞いて「へえ~」と思うことが多いのは
考える習慣がないから?←「へー!ホー!星人 」
」
○小4女子
本人…遊び感覚でスポーツクラブに入ったので、つらい。
クラブをかわって楽しくなった。
親 …入ったからには一生懸命やるべきという思い込み。
そういう思い込みも、見直したり修正していけばいいのかな。
○子育てとは
子育てとは、自分の良いと思う通りに育てる事だ、それを成し遂げるのがよい親だと思っていた。
第3の大人の見方・考え方が必要。例)学校の先生。
○兄弟関係
普段から乱暴な妹。自己主張できない兄。最近兄が乱暴になってきた。
周りの親…妹に乱暴するのを見ているなんて。(と、思うだろう)
親…「よし!もっとやり返せ!」と思っている。
まわりはいろんな見方をするだろうが、自分の折り合いが付けばよいのだろう。
○中1男子。
幼稚園の担任…「マイペースだけど、周りの様子も見えているから大丈夫ですよ」
小1の担任…「ずいぶん甘やかして育てたんですね、おばあちゃんが育てられました?」
(初対面の第一声で)
親…この先生はそう捉えたんだろう。先生の目の前の席なのも、よく見てくれてありがたい。
子ども…「また一番前の席なんだ!」とうれしそう。
親の捉え方一つで破たんしていた可能性もあっただろう。
先生も人間。先生にも捉え方の癖はあるはず。
先生が絶対だと思い込んでいたら、そうは思えなかったかも。
幼稚園の時の先生からは「大丈夫ですよ」と言ってもらえていて、自分もそう思えていたし。
自分の中で折り合いがついていればそれでよい。
(つづく)
2011年10月15日
くさいど 終了&新生

平成18年に開始した『くさなぎ井戸端会』は発足から5年の節目を迎えました。
発達障害の理解に近づきながら、子育てを一緒に考えていく井戸端会の活動も、
時を経て様変わりしてまいりました。

世の中の発達障害への理解と対策の推進や参加者の子供達の成長と共に、
井戸端会も又、新たなものへと変化すべく、ここで一端、会を綴じさせて頂くことにしました。
これまで御参加下さった皆様方へ、心から感謝申し上げます。
今後は新たに『勇気づけサロン』昼の部、夜の部を開催してまいります。
子育ち、親育ち、自分育ちのためのコミュニケーション学習交流会
心理士・交流分析しの細野が皆様とともに“勇気づけのコミュニケーション”で
ハッピネスを創造していきたいと考えております。
今後ともロコムスの活動が終結するわけではなく、形を変えて、皆様と共にありたいと思います。
*************************
11月は、、、、、長崎スポーツセンターにて
●4日(金) 『勇気づけサロン』昼の部
10時から13時半
参加費1000円
*よろしければランチご持参ください
●24日(木) 『勇気づけサロン』夜の部
19時から21時
参加費1500円
で開催いたします。
参加希望者4名以上にての開催といたします。
お誘い合わせてご参加ください。
よろしくお願いいたします。
2011年10月03日
「第38回くさなぎ井戸端会」参加者の声

参加者アンケートより、皆様の了解を得て、一部掲載させていただきます。
********************
●しつけをしなくちゃ!といつも肩の力が入ってしまい、
その結果口うるさいお母さんになっていることに気付いていましたが、
どうしたらいいのか日々ゆっくり考える時間をとらず来てしまった気がしました。
今日の話を聞いて、案外自分の子は生活力がある気がしたので、放って置いてもいいかなーと思いました。
皆さんが同じような悩みがあるのを知り、ホッとしたり、
やっぱりこの場所は私にとって必要なものだなーと思います。
ケンカもケンカだからこそ言葉づかいがわるくなっていたり、
相手を叩いていたり、しているんだと考え方・見方を変えて、今日帰ろうと思います。<M,I>
●「しつけ」について日々「ちゃんとしなきゃ!」とばかり思っていますが、
今日は何をどうしたいのか・・・が分からなくなっていたことに気づきました。
自立を考えることで少しリラックスして考えられるな(^。^)と思いました。<M.W>
●今日二回目でした。
子育ての先輩・先生・保育士さん、いろいろな立場の方の話が聞けて、少し力が抜けたような感じです。
近すぎるお母さん友達とは重い話題はし辛い・・・ということもありますので、
貴重な場所だと思います。<A.M>
●この会に参加するといつも、子育てについて忘れかけていた大事なことを再確認
することが出来ます。<N.A>
●今日も皆さんのお話を聞けて心がスッキリしました。
わが子の悩みは尽きないけれど、成長や生きる力を感じられ「うん・うん、いいぞ」
と思う事も増えてきました。
こういう集まりに参加できて、幸せだなーとつくづく感じています。
ありがとうございます。<N>
** mino**
座談会にご参加いただきました皆様、
今回も活発なディスカッションをありがとうございました。
お疲れ様でした。
2011年10月02日
「第38回くさなぎ井戸端会」ご報告

日時: 5/26(木)
テーマ: 「しつけの目的」ってなんだろう???
参加人数: 17名
「しつけの目的」ってなんだろう??? が今回のテーマでした。 
まずは、なかなかうまくいかない・・・と日ごろ感じておられる「しつけ」とは
何なのでしょうか?
みなさんと話し合ってみましたよ。
・ 人をたたく
・ 片付けられない
・ 宿題をやらない
・ 言葉づかいの悪さ
・ お金の大切さを教えたい
・ 他の家とのしつけのルールの違いに戸惑いを感じる
などなどお悩みが出てくる、出てくる。
日々悪戦苦闘している姿が目に浮かびます。
それぞれの問題についてはみなさんで、ディスカッションしました。
改善していく良いヒントが見つかったでしょうかね?
そもそも、どうしてしつけをするのでしょうか?
本題の「しつけの目的」です。
それは、間違っても子どもに親の権力や威厳を知らしめる為ではありませんよ!
子どもの自立(自律)=生きる力 を育てる
しつけをするのは、子どもの自立を助ける為の親の協力
なのだそうです。
ハイ!親はいつまでも子どもの側にいられません。
将来就職して働いて、結婚して家庭を作って・・・
子どもに幸せになってもらいたい願いがあります。
かなしいことに幸せに生きてもらうための協力しか出来ません・・・
ちなみに子どもにとっての自立するために必要な心構えってなに?
①「自分の人生は自分で決める」
②「自分で解決する力がある」
③「自分は世の中に必要とされている」という自覚
だそうです。
子どもがこの自立への心構えになるように、親や、まわりの大人がうまいことうながせたら・・・
考えただけで、明るく有意義な未来が待っていそうですね。
そして、親は、親の構えとして
「共育ち・友育ち・朋育ち」の3つの とも育ち が求められるようです。
一つ一つしつけがうまくいかなくったって今あせることはないのです。
今直ぐに結果を求めることなく、長い目で育つのを待つ。
そりゃ忍耐勝負ですよ!!大変なことです!!

一本の木を見て、森を見ないで。大きな森が見られる子育て。
実は私達親は、”子育て”を通して、心を大きく広く持つことを
子どもに鍛えられているのかもしれないですね
そうと分かれば、
「しつけ」・・・子どもの全体を見て、ひとつゆったりとのんきにリラーーーーックスして
根気よくやりましょうかね。 
以上です(M・N)
2011年09月08日
「第40回 くさなぎ井戸端会開催」のご案内

夏休み、いかがお過ごしでしたでしょうか?
子どもの成長や変化に気づいたことはありましたか?
みなさんで
思う存分、自由にトーク!

是非ご参加ください。
日時: 9/29(木)10:00~13:30
場所: 長崎新田スポーツセンター・和室2
参加費: 500円
ランチご一緒できる方は、ご持参ください。
くさなぎ井戸端会は、どなたでもご自由に参加していただくことのできる
『子育ち・親育ち学習会』です。
お気軽にお越しください。
皆さんとお会いできるのを楽しみにいたしております。
2011年08月02日
9月のLOCOMS 日程変更

夏休みいかがお過ごしですか?
さて、9月開催の
『STEPフォロー会』と
『くさなぎ井戸端会』
の日程変更についてお知らせいたします。
***************************************
『STEPフォロー会』・・・9/6(火)9:30~13:30
『くさなぎ井戸端会』 ・・・9/29(木)10:00~13:30
会場: 長崎新田スポーツ交流センター・和室2
***************************************
お間違いないようによろしくお願いいたします。
皆さんとお会いできるのを楽しみにいたしております。
2011年07月12日
夏休み、くさいどはお休み

毎月、第4木曜日、定例となっています
『くさなぎ井戸端会』(子育ち・親育ち&発達障害啓蒙)は
7・8月は、子供たちが夏休みになるためお休みです。
次回は、9月15日(第3木曜日)です。
1週間ずれますので、お間違いなく。
9月は、記念すべき第40回となります。
これまで、5年間、会を重ねて来られましたのも皆様のお陰です。
夏休み明け、また皆様のお元気な姿をお見せくださいね。
猛暑のこの夏、
夏バテしないよう、
節電しながら上手く乗り切りましょうね!
2011年07月02日
「第37回くさなぎ井戸端会」参加者の声


参加者アンケートより、皆様の了解を得て、一部掲載させていただきます。
********************
●この会に来るといつも、自分と同じように皆さんも悩んだ末に今がある(うまくいってる)んだと思います。
子どもにいつも過度な期待している自分を客観的に見つめ直す機会になり、大変でも参加したいなーと思える場所です。
「日々の積み重ね」という言葉に日々ガミガミ言ってしまう自分や、言われている子どもはどう思っているのか。
このまま行ったら子どもはどうなってしまうのか!?と不安に思いつつ、自分が変わらなくちゃ!と改めて思いました。
経験された方の言葉はずしっと胸に来ます。
不登校に敏感な私でしたが、関わり方しだいで大丈夫と思えるし、自分のマイナスイメージはやっぱり子どもに伝わり、
その通りにしてしまっている様に思います。
自分の子育てに対するゆらいだ考え方をいつも少し修正できる場になりました。<M.I>
●今日もありがとうございました。
今日は皆さんのお話を聞きながら、色々な事を思い出し、気持ちを立て直すことが出来ました。<M.W>
●初めて参加させて頂きました。わかっているようでわかっていなかったことが、再認識できたような気がします。
子どもに自分の意見を押し付けてはいけないと思っても、やはり押し付けている自分がいる。
こんなに頑張っているのに、と感じてしまいます。
子どもにとって何が大切なのか、ゆっくり考えていきたいと思います。<J.Y>
●久しぶりの参加でした。今まで(4年間)学校とも保護者とも違う立場で仕事をしてきましたが、
今日久しぶりの保護者の方と(自分も保護者として)お話して、新たな視点をいただけたなと思います。
自分の子育てをもう一度見直すよい機会でした。
子どもたちにやさしく接することが出来そうです。<教師・保護者>
●あたりまえについて、中学生で求められる事・・・等。
とても参考になりました。
当たり前の事をちゃんとできるように・・・ってとても大変なことを注文しているんだって事を
前にも学んだはずなのに、つい忘れて日常をすごしている気がします。
気をつ行けようと改めて思いました。



2011年07月01日
「第37回くさなぎ井戸端会」ご報告

日時: 4/28(木)
テーマ: 「進級進学」フリートーク
参加人数:10名
4月は進級進学で子ども達の閑居に変化がある時期である。
そんな中で子どもや親がどのように過ごし、何を感じているのかを自由に話し合ってみた。
●子どもが入学して2日目に鼻血を出して帰ってくる。理由を聞くと「前の席の子が(わざと)転ばしてきた。
でもすぐに謝ってきたから許してあげた」と。
学校からはその事について特に連絡もなく、親の私のほうがびっくりしてしまったが、
本人が「別にいいから・・」と納得しているようにみえた。保育園の時は毎日の送迎で先生と話す機会があったが、
小学校に入り全くといっていい程、情報が入らない。
親としては今回の思わぬできごとに、先制パンチくらったように思ったが、子どもの成長を感じ取ることも出来た。
●小6の子が不登校になっている。一年生の終わり頃から学校に行きたがらなくなり最後は、
無理にでも引っ張って登校させることもあったが、理由を聞いても「いじめられるから・・・」と言うが、はっきりせず。
小4の2学期から行かないことも多くなり、5年の後半から不登校になり、現在に至る。親としても心配ではあるし、
年齢に不相応に暴れることがあった。
その後、病院で軽度発達障害があると診断されるが、支援を受けられるほどでもない状態でいる。
学校側にも何度か相談するが、取り合ってもらえず、市の子ども相談センターに相談する。
不登校の今は、週に一度、支援を受けている子どもと一緒の教室に通い、勉強している。
担任や学校に相談してもダメだと感じ、外部に相談することで救われた感じがあるが、
6年生なので、中学への進学も様々な角度から考えて、子どもにとってよい方法を見つけたい。
●小2の子。とてもゆっくりマイペースが心配で、つい言葉がけが多くなってしまう。
先生は「何度も繰り返し経験する事で、自分のものにしている」と言われるので、見守っていこうと思う。
けれど朝「学校に行きたくない」と言われると親も少しドキッとする。
親の敏感さが子どもに伝わり、子どもも反応していると思う。
●小4の子。小2の頃、数日間学校に行かないときがあった。
原因はいじめでもなく、親の私がしっかりして欲しいと思うが余りに細かく色々言い過ぎて、子どもが疲れて
(勇気がくじかれていた)いたように思う。
親の当たり前は子どもに当てはまるものではなく、その子のペースで成長しているのだと分かった。
●小5の子。友達との関係が上手に築けず「ふつうの女の子になりたい」と言う。
友達への声かけや接し方などを具体的にアドバイスをしてみると、「やってみる」と。
子どもも高学年になり、自分と他人の違いを感じてきている。
********************
子どもの年齢により、悩みや問題も変化してくる。
学年が上がるにつれて「不登校」なども増えてくるが、原因は本人に聞いても分からない。
けれど何か心がくじけてしまう事があり、学校に行けなくなってしまう。
ともすれば親は「学校に行けない」ことに過敏に反応し、行けなくなった原因を探り、何とか登校させようとすることが多い。
けれど親は学校に行けない子どもの心を認め、学校以外に行ける場所や、何なら出来るのか、好きなことは何か、
などその子どもがどう在りたいかを一緒に考えていくことも必要である。
そして、親の思う当たり前はそのまま子どもに通用するものではなく、親の思い込みや願いばかりを子どもに強要している事も
多いので、当たり前を具体的に表していくと分かりやすいと思う。
また、小学校から中学校への移行期は子ども本人の思春期とも重なり大変でもある。
小学校では段階を経て少しずつ手を離していくのに対し、中学校では、出来るのが前提でスタートするので、
「何で出来ない?」「やっておけよ!!」となり、子どもも混乱する。
移行期に向けて、子どもが主体性を持って何事にも取り組むことが出来る力をつけていくためにも、
日々「あなたはどう在りたいのか?」という視点を持って子どもと接していきたいと思う。
(S)
2011年06月11日
「第39回くさなぎ井戸端会開催」のご案内

梅雨の季節、気持ちよく過ごせていますか?

井戸端会・・・今回のテーマは、
『物の見方・考え方・捉え方は変えられる?』
日時 6/23(木) 10時~13時半
場所 長崎スポーツセンター
参加費 500円
同じ事象でも見方・考え方・捉え方は人によって違うことがありますね。
ネガティブに捉え、心配になってしまう人。
ポジティブに捉え、チャンスだと思える人。
自分の気持ちを楽にするには、物ごとの捉え方に工夫が必要なようです。
皆さんの問題や悩みを通して、ご自分の『物の見方・捉え方』のクセを
発見してみましょう。
2011年06月05日
「第36回くさなぎ井戸端会」参加者の声

参加者アンケートより、皆様の了解を得て、一部掲載させていただきます。
********************
お母様方の意見がきけて大変参考になりました。
一番印象に残ったのは、公平さの話題です。
連帯責任において本人が納得する不公平さの理由付けをする。
それは大変なことだと感じました。自分だったら、連帯責任というのはしたくないです。
しかし、お母様方の話をきき、ときにはしなければならないものではないかと思うようになりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
教師志望の学生<A.Y>
今日はさまざまなテーマでの皆さんの意見を聞けて、とても参考になりました。
「子どものことで悩んでいるのは私一人ではない!」とも感じ、なんだか安心したようなホットしたような
・・・。また参加させてください!
<H>
本日は参加させていただきまして、ありがとうございます。
実際に皆さんのお話を聞くことが出来、とてもうれしいです。
来年度、教育実習にもいくので、今回お聞きしたことを実践していきたいです。
本当にありがとうございました。又参加させてください。
教師志望の学生<H>
自分の親としてのスキルがまだまだだなぁと実感させられます。
理屈としてわかっていてもそれを実践できないところが子どもというより、
自分の成長が必要かと思いました。<M.I>
皆さん、カード等を通じて、先生とコミュニケーションをとっているんだなぁ・・・と思いました。
私はつい面倒くささが先に立ってしまって・・・。
これからは、あまり肩肘張らずに、気楽な気持ちで思いついたことを先生に伝えていけたら、と思います。
<N.A>
今日もありがとうございました。毎回勉強になります。
これから先生になる学生さんの意見を聞く機会はないので参考になりました。
4月からの小学校生活に向けて、また皆さんのお話を聞いていけたらいいなと思います。
<M.W>
保護者の方から見た子どもと、教師から見た子どもは違うんだなと感じました。
しかし、子どもたちをよくしようという気持ちは一緒で、みなさん熱心な方が多くとても感動しました。
清水区内の小学校でボランティアをやっていますし、来年度静岡市の教員になろうと思うので、
またお会いする機会があると思います。よろしくお願いします。
教師志望の学生<T.K>
本日はありがとうございました。
保護者の方々とお話しする機会は滅多にないので、参加できて大変うれしかったです。
来月も参加したいです。
先生になってからはなかなか参加できませんが、自分に子どもが生まれたり、育児休暇中には参加したい!
!と思いました。ママ教師を目指して頑張ります!!
教師志望の学生<Y.M>
今日は貴重なお話がたくさんお聞きできて良かったです。
温かい目で先生を見ていることを知りとてもうれしい気持ちになりました。
ありがとうございました。
<K.S>
発達障害について子どもがどう考えているのかをお話し頂いてとても参考になりました。
診断名がつく事、その選択については、未だに良かったかどうかは分からない・・・と聞き、
親の気持ちを思い知りました。
本当にみんな悩みながら前向きに過ごしているんだなと改めて思いました。
先生たちも保護者がどう感じるかはとても気になることなんだなと判りました。
<O>
2011年06月04日
「第36回くさなぎ井戸端会」ご報告②

<前回につづきます>
今回の井戸端会には、とても熱心な教師志望の学生さんがたくさんご参加下さり、
保護者(親)への質問や、保護者から教師への願いや普段はなかなか言えない本音なども出てきました。
学生さんからは、
・教師が信頼を得ていないような気がして・・・
教師としてもっとたくさんの知識を得たいと思いました!!
という、とてもうれしくてありがたい志や、
・来年度、新採で教壇に立ちますが、新採の教師に保護者としてどんなことを望みますか?
・教師にされて嫌なことは何ですか?
との問いに対して、
・新人の教師は若さゆえに、親からは頼りなく感じられることもあるが、
「若さと自分の強み」を生かして指導して欲しい。
・子どもを不公平に扱う、笑顔やユーモアがない、年齢にそぐわない責任を子どもに強いるのは
やめて欲しい...。
また、中学校の子どもの担任は、比較的若くて、気さくで話しやすい反面、
子どもからなめられているようにも感じる。それでいいのかと疑問に思うこともあるし、
教師として、大人としてもっと毅然とした態度や威厳を持つのことも必要なのでは?
という意見が出ました。
立場が違えば、考え方や見方の違いは当然ありますが、両者共に「子どもを教育する」
という目的は同じなので、お互いに信頼関係を築くことが何より必要なのでしょう。
けれど実際にはなかなか教師と保護者が話をする機会(時間)がありません。
そこで、コミュニケーションのとり方のひとつに、子供の宿題で使われる音読カードの保護者サイン欄に
コメントを書くというのがありました。
相談するという程ではないけれど、気になることや、子どもの様子などを書き、
それに対して返事があることで、お互いの信頼が増していくのだと思います。
また教師からもクラス便りなどで情報を発信することで、保護者の信頼を得ることがあります。
(クラス便りがなくても直接子どもとの会話で教師や学校の様子を知るのが理想ですが...。)
本音も飛び出す意見交換で、学生さん達からは、思っている以上に保護者の方が教師に対して
暖かい気持ちでいてくれるのがわかったという感想があり、
コミュニケーションの大切さを再確認しました。
(一歩間違えれば、モンスターズペアレントになりかねないので、それには注意が必要ですが... 。)
。)
2011年06月03日
「第36回くさなぎ井戸端会」ご報告

日時:2/24(木)
テーマ:無し フリートーク
参加人数:18名(学生6名)
今回のくさなぎ井戸端会も、前回同様、椅子にテーブルの会議室で行われました。
あえてテーマを決めず、過去のアンケートの中で皆様から挙げられていた、
『取り上げて欲しいテーマ』をホワイトボードに書き上げ、
参考までに参加者の皆さんにそれを御覧いただき、書かれた内容に関連することでも
そうでないことでも、自由にお話いただくような形で、会をスタートしました。
まず最初に投げかけられたことは、
「特性と障害はどう違うの? どこで線を引くのだろう・・・
どこで線を引くのだろう・・・ 」でした。
」でした。
・社会で生きていく中で、その特性があることにより生きづらくなった時、
特性が障害となるという見方をするのかな・・・
・生きやすくなる為に、手立てを必要とするとき、障害となるのかな・・・
・発達障害ではなく、発達デコボコというネーミングの方がふさわしいという話も聞いたことがあるけど
・・・
・障害があるかないかの線引きそのものは主に医師がすることになるよね・・・。
その目的は、差別区別ではなく、療育や支援を具体的にどのようにしていくかを見極める為なんだよね・・・
・「僕は障害者なの? 」と子供に聞かれたことがあって・・・。
」と子供に聞かれたことがあって・・・。
障害者なのか、そうでないのかという白黒つけるような答え方はしなかったな・・・。
子供自身が「障害者」をどう捉えているのかを聴いて、そう考えている子供の気持ちを受け止めるよう
にしたよ・・・
そして、このようなディスカッションからさらに、
・やっぱり親が早期に気づいて受け入れることが大切なのかな・・・
・早いうちに発見できると、具体的な手立てを早期に得られるし、
集団生活でのスキルを身につけるには、小さいうちからの方が良いのは明らかだけど、
早期に受け入れるのが親の責任!みたいになってしまうと、それは厳しいかな・・・
障害じゃないと思いたい親の心情もあるしね・・・
・うちの子は小学校入学と同時に障害があるものとして受け入れて、支援級を選択してきたけど、
それが本当に子供にとって良いことなのかどうかはわからないし、親としては全く後悔はしていないし、
むしろたくさん得るものがあると信じているし確信しているけど、
子供がそれをどう受け止めるかは子ども自身になるからね・・・
・先生や学校の理解が得られないと感じたら、専門の相談機関に行くのもいいかも...。

といった、すぐには答えが出ないけど、
皆さんと一緒に考えていくことそのものがとても大切と思われる貴重な意見がたくさん交換されました。


<つづく>
2011年05月15日
「第35回くさなぎ井戸端会」 参加者の声

H23.1.27に開催しました「第35くさなぎ井戸端会」
ご参加いただきました皆様のアンケート(感想、ご意見、ご要望など)の一部を
ご了解を得てここに掲載します。
**********************************
保護者の方々の直接の声をお聞きすることが出来、よい機会でした。
まだまだたくさん勉強することがあると思いました。
担任の先生になったら悲しいことがおこらないように努力したいと強く思いました。
又来たいです。ありがとうございました。
教員志望の大学生<T.E>
自分の思いが上手に伝えられなかった。
ただ相手を変えようと思っている自分がいたと気づいた。
自分から変わってみることが大切だと思った。
当事者としては大きな問題として抱えていることが多い。
客観的な意見が聞けてよかった。
<S>
皆さんの話をきいて、どんな事でも上手な解決策はあるのだ・・と思いました。
落ち込む必要はなく、その時の相手や当事者の気持ちを受け止め、思いやりつつ、感情に流されずに考えていけば、
きっと当たり前のような解決法に気づくのかなと思いました。
とっても難しいけど、頑張ってみようと思います。
<O>
今日もありがとうございました。
皆さんのお話に自分や自分の子を重ねながら聞かせて頂き、勉強になりました。
年齢が上がっていくのに連れて、子供の社会も変わっていき、自分が対応していけるか心配もありますが、
楽しんで子育てできるようになりたいと思います。
<M.W>
今日は本当に参加出来てよかったです。
少しずつ親育ちが出来たり、問題の解決を話し合ったりすることが出来てすばらしいと思います。
<K.K>
今日は久しぶりに参加できてうれしかったです。悩みって本当に体力使うんですよね。
心が疲れていて、体力もダウンしてしまうと思考も低下するし・・・。
でも解決したい気持ちだけは増殖する。
そんな時に人の意見を聞いたり考え方を置き換えたりすると、ヒントをもらったり・・・。
解決の道が近づいたりすると思います。みんなが笑顔になって欲しいです。親も子も。♡
<N>
本日はお話を伺って、また自分の世界が広がりました。
お母様方の悩みをお聞きして、私たちはこのような時、問題に直面した時のためにも勉強してるんだ、
と気持ちを新たにしました。また学ばせてください。ありがとうございました。
教員志望の大学生<I>
2011年05月14日
「第35回くさなぎ井戸端会」ご報告

『第35回くさなぎ井戸端会』 H23.1.27に開催いたしました。
参加人数 16名
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
座談会の模様をご報告します。
****************************
インフルエンザ流行中にもかかわらず、
未就学児を連れたお母さん・初参加者・先生を目指す学生さん等、
いろんな立場の人16名で和やかに開催しました。
いつもは畳のお部屋に座布団でジャパニーズ!なのですが、
今回は広々とした洋室にスポンジマットコーナーを設け、
小さな子もお母さんとリラックス。
私たち大人もテーブルと椅子で足がしびれず楽チン。
今回、テーマは「? ? ?」特に決めず
参加者が気になっている事を皆で話し合いました。
専門家は一人もいません。まさに座談会です。
さて、どんなお話が聞こえてくるでしょう?
「片づけが苦手な小学生。
落し物が多く学校でとても困っている様子。
家では声をかけると出来るのに・・・。」
「学校休んでいい?」朝、元気のない小学生。どうしたらいい?
「お宅のお子さんが、学校でうちの子に怪我をさせた」と連絡があった。
1週間前に起きたことで、子供の記憶はあやふや。どうしよう?
お互い交換して遊んだおもちゃ。
おともだちの部品が我が家で失くなってしまった・・・。
パソコンに興味を持ち始めた4年生。
チャットを始めている。心配だ。どうしよう。
等等
ここでは、専門家は一人もいません、
ふつうのお母さんたちで
「さて、どうなのかしら?」と話し合っています。
その中から一人一人が子育てのヒントをつかみ、
「参加して、トクしたー」と
さっぱり顔で会を終えたのでした。 
(I.Y)
****************************
2011年05月13日
「第38回くさなぎ井戸端会開催」のご案内

今回のテーマは『しつけの目的』
改めて、子どもを”しつけ”るために皆さんが日頃行っている子育てについて
ご一緒に考えてみましょう。
お誘いあわせてご参加ください。
日時: 5/26(木) 10時~13時30分
場所: 長崎新田スポーツセンター・会議室
参加費: 500円
 ランチご一緒できる方は、ご持参ください。
ランチご一緒できる方は、ご持参ください。
くさなぎ井戸端会は、どなたでもご自由に参加していただくことのできる
『子育ち・親育ち学習会』です。
お気軽にお越しください。
お待ちしています。

2011年04月12日
「第37回くさなぎ井戸端会開催」のご案内

進級進学おめでとうございます。
今年の春休みは、遅咲きの桜の開花が待ちどうしく過ごされたのではないでしょうか?
さて、新年度となって、今回第1回目のくさなぎ井戸端会では、
皆様と楽しく、フリートークで座談会を進めて参りたいと思います。
お誘いあわせてご参加ください。
日時: 4/28(木) 10時~13時30分
場所: 長崎新田スポーツセンター・会議室
参加費: 500円
ランチご一緒できる方は、ご持参ください。
くさなぎ井戸端会は、どなたでもご自由に参加していただくことのできる『子育ち・親育ち学習会』です。
お気軽にお越しください。
お待ちしています。
2011年03月28日
「第34回くさなぎ井戸端会」 参加者の声

H22.11.25(木)に開催しました「第34くさなぎ井戸端会」
テーマ:「あなたが口を出したくなる時」
にご参加いただきました皆様のアンケート(感想、ご意見、ご要望など)の一部を
ご了解を得てここに掲載します。
**********************************
● 感情のコントロール、感情を切り換えるという事が娘も私も下手だなと思いました
「怒りたくなったら笑ってみる」なんて「いいなーおもしろいなー。 」
」
生活の中でユーモアを活かして工夫して娘と私にあった方法を探してみたいです。<N>
●学校低学年を持つお母様たちが悩みながらも前向きにがんばろうとしている姿に「みなさんがんばってるなァ」と
思いました。そして、3人の子ども達が幼かったころの自分を思い返して、親として未熟で不安だったことや、
考えた事、やってみた事、失敗した事をいろいろ思い出しました。
アスペルガーの方の講演のお話しも次男がアスペルガー傾向が強いと感じているのでとても参考になりました。
ありがとうございました。<M.N>
●今日もありがとうございました。
子どもにも自分にも夫にもハードルを上げてしまっていることがたくさんある気がします。
家族一人一人の意志や気持ちを尊重しながら生活できるようになりたいなと思いました。<M.W>
●2回目の参加ですが、来る度に自分を客観的に見ることができて、今までの自分が恥ずかしくなります・・・。
でも子どもに命令してばかりでは子どもにうまく伝わっていないのは実感していたので、今日からは質問形にかえてみて、
子どもにどうしたいのか聞くこと、一緒に順番を決めてみようかと思います。
他の皆さんがうまくやっているのかと思いきや、皆さんも昔は失敗していたり、うまくいかないところを乗り越えてきている
と知り、ホッとしました。
子どもを客観的に見られたらもっと楽しくなるかと思います。
自分で工夫したやり方を見つけていきたいなーと思いました。
自分がよい親になろうとしすぎて、それを子どもに求めていた気がします。もっと気を楽に持てたらと思います。<M.I>
●初めて参加させていただいましたが、このような会がある事で、親の気持ちの中にも余裕が出来、家に帰ってからの
子育てにも良い関係が築けるのかなと思いました。
ついつい先を見越して色々と口を出してしまうことが多いのですが(下の子に)、その子その子の発達段階や性質を見極めて
、言葉を声かけする事が大事だと思いました。
子どもが「次は頑張ろう」と思える意欲的な行動が出来る様になるべく肯定的な捉え方をして声をかけてあげようと
思います。今日から少しずつ実践しようと思います。<無記名>
●くさなぎ井戸端会は、いつも自分を見つめなおす大事な時間です。
「口出し」はしないようにしてるつもりなのに、やっぱりしてる自分に気づき、ブレーキをかけるきっかけになりました。
「怒りたい時は笑う事にした」という話を聞いて、是非やってみようと思いました。<O>
●口を出すことは悪いことではなく、タイミングや言い方が大事だと思います。
子どもの目線に立つことをいつも心がけています。今日は楽しかったです。ありがとうございました。<J.M>
●3年ぶりに参加し年を感じましたが、母親を楽しめるようになったな~と思いました。
年の最後に来てよかったです。皆さんステキ!ありがとうございました。<I>



くさなぎ井戸端会は、どなたでもご参加頂ける座談会です。
皆様のお越しをお待ちいたしておりま~す。