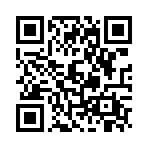2015年03月31日
頑張っている姿、認めているよ

春休みが始まり二週間。
みんなの憩うリビングは荒れ放題。
出がけに私は言いました。
「お母さん、こんなところでは生活するのは、本当にイヤなのよ〜…」と本気で哀しくて。
仕事から帰ると半分は綺麗に片付いていました。そして、娘の書き置きがありました。
「母へ
きたなすぎて
かたづけられません。
教科書とか。
帰ってきたら
やります。(一緒に…)
じゅくいってきます。」
へ? 一緒に…って(^^;;
いつも美しい字を書く子が字まで汚くなっていました。
ふふふふ。
本当に一生懸命に彼女なりに片付けたのだと思います。
塾から帰宅し22時、疲れて帰った娘と片付けをするのだなぁ〜と今夜は早めに家事を終えておくことにしました。
頑張れ〜!新中学三年生*\(^o^)/*


2015年03月19日
今ここからのスタートです。

三月、別れの季節です。
これから社会に出ようとする光り輝く原石の君に頂いた有難い言葉はそのままに、私から感謝を込めて100倍返しに贈ります。心からありがとう♡♡
四月、出会いの季節です。
新しい友、新しい仕事、新しい学び、新しい自分との出会い。
そう、仕切り直しの季節です。
キャラ立て失敗した人、ここから仕切り直してみては?今、ここから始めればいい。新しいスタートです。
私は、、、キャラの変えようはないだろうから(≧∇≦)、
柔らか〜い、若いお母さんたちの脳ミソと器用に動く指先をお借りして新たな試みを始めます!!
夢を語り合い、アイデアを出し合い、心を開いて、一年後、形になっている様に頑張ります。♪( ´▽`)
2015年03月14日
小指の思い出。

親にせがんで幼児で始めたピアノ教室。
ドからドに届かない私の5本の指を先生は一本づつボールペンで強く弾く。
どうして出来ないの?
やる気がないの?
と怒りながら。
届くわけがない。
親も先生も私でさえ大人になるまで気がつかなかったけど、私の小指は極端に短く力が入らないように出来ている。まるで添え物だ。存在理由がわからないほど、その使い道は全くない。
先生は言われた。
「それなら、指の股を切りましょう。」と。
その時、幼心に
「みんなはちゃんと出来ているのに、出来ないで指の股を切られる私は何て駄目な子だろう」と苦しんだ。
しかし、やる気のない子は辞めてもらうという理由で、切られる前にピアノ教室を退塾させられてホッとした。
親は、小指の事情を知らなかったから
”続かない子” ”不器用な子” というレッテルを私にくれた。
大人になって、やっと分かった。
私の根性が曲がっていたのではない。
私が悪い訳でもない。
。。。と。
私の小指の特徴が、ピアノや懸垂や器具を扱うスポーツや楽器に向かなかっただけなのだ。
自転車を始めたが、ドロップハンドルは私には難しいようだ。小指の事情により、ブレーキ操作をうまくできないことに気づいたからフラットハンドルに替えてみた。おかげで抜群に調子が良い。
選択肢がある事はとても嬉しい。フラットハンドルなら小指の問題は問題では無くなる。
さて、何を言いたいかといえば…
親は子どもの特性や特徴を捕まえながら、その子のできないことをとやかく言うのでなく、できる事、得意なことに視点を置いて、認め、褒めて、子どもが自信(自分への信頼)を持てるように関わる事が大事だ。
苦手なこと、できないことをとやかく言うより、できることを伸ばしながら自信と責任を育てることで、自分から苦手なことへの挑戦や克服に向うたくましい心が育つのだと思う。
さて、53歳の私もかなり図々しく、違う意味でたくましくなった。
いよいよ、生まれながらの高所恐怖症と水難妄想症を克服する時が来た!
今年は高さ(登山)と水(水泳)、そして、孤独(砂漠)に挑みます。
*\(^o^)/*

2015年02月06日
ムスコよ!ん、JUST DO IT!

高校2年のムスコが、珍しく進路について真情を吐露してきた。
驚きを持って母は、ハハハと素直に答えた。
「あなたの人生をあなたが主役で生きて行けるよう、お母さんはいつも応援しているつもりだよ。だから、進路は、あなたが決断すればいい事だけど、ハハハ、驚いたね〜。(≧∇≦)
始める前から何故、自分に限界を設けるの?何で自分の能力をディスカウントするの?それは結果を恐れているからだよね。問題は結果でなくそこに向かう過程に価値があるんでないのん?一生懸命努力してやれるだけのことやったら、受験失敗したとしても、そこから学ぶ事が出来るんじゃないのん?失敗したら、そこからまた始めればいいじゃん。若いんだし、遠回りしてもいいんじゃん。人生無駄なことなんて何一つないんだと思う。何をそんなに遠慮してんの?
ビビってんなよ!やれよ!やって見ろよ!突っ込んで見れや!今の自分を見てちゃダメだよ。これから見たい自分の姿を浮かべなきゃね♡
イヤー、ハハハ驚いたね〜。母さんなんか失敗ばかりの人生だから怖いもん無いしぃ〜〜。(⌒▽⌒)v」
ムスコは、大きく頷き「へ〜〜、お母さんは、ただのモノ好き変態野郎かと思っていたけど、あゝ、何か、響いた。ヨシ!やれそうな気がして来たよ。明日は早起きして勉強するっ!(^o^)/」
そう言って就寝したムスコは、翌朝ずいぶんと寝過ごし遅刻して行った。(^◇^;)
クフクフ、若者よ、人生はこれからよのう(*^_^*)苦しめ、楽しめ、喜べ、悩めー!
彼の人生を温かく見守って行きたいと思います。
♪☆☆☆♪☆☆☆♪☆☆☆♪☆☆☆
『すべての人生は実験だ。たくさん実験を重ねるほどよくなる』
ラルフ・ワルド・エマーソン
2014年03月07日
反映的な聞き方

子どもが学校での出来事や自分の思いを話してくれない・・・ と不安になられる親がいます。
と不安になられる親がいます。
子どもの話を上手に聴く技術ってあるのですか?
こんばんは~。minoです。
『子どもの話を上手に聴く技術』・・・あるんですよっ!!
STEP勇気づけセミナーでは、これを『反映的な聴き方』と呼びます。
「この子は何を感じているのか? 」と子どもの言葉の背後にある感情を理解し
」と子どもの言葉の背後にある感情を理解し
言葉にして投げ返すというものです。
例えば、子どもの気持ちが、嬉しそうならば、「嬉しかったの?」とか、
悔しそうならば「悔しかったの?」 というようにその感情を言葉にして子どもに返してあげるのです。
すると子どもは、自分の感情に気づき感情を処理することが出来るようになってきます。
『反映的な聴き方』は、子どもの「話す内容に反応して善悪の判断をする」ということは無いのです。
あくまでも、子どもの感情に焦点を合わせて聴きます。
子どもは、親に理解され、共感されたと感じ、自分の話をもっと聞いてもらいたいと思うようになり
進んで話をするようになるでしょう。
ですから『反映的な聴き方』をすることは、子どもへの勇気づけともなるのです。
ご家庭で親子の会話が飛び交う「開放的なコミュニケーション」をするために
『親は、自分の価値観や善悪の判断に振り回されることなく、子どもの感情に焦点を合わせて話を聴こう!』
『反映的な聴き方を心がけよう!』
☆☆☆ STEP勇気づけ shimizu room ☆☆☆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【STEP勇気づけセミナー】
アドラー心理学に基づく実践プログラム
http://www.locoms.com/step-s.htm
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2014年03月06日
勇気づけの壺

誰でも持っている“勇気づけの壺”のお話です。
その壺が涸れかけて、ヒビが入って来ているなんてこと、ありませんか?

こんばんは。minoです。
勇気づけの壺とは、その壺が“勇気”でいっぱいになると
建設的で肯定的なものの見方、考え方、捉え方ができるようになり
人の価値観を裁いたり、自分自身を責めたりすることが無くなる
というものです。
では、その壺をいっぱいに満たし、溢れんばかりにするにはどうしたらよいのでしょうか・・・・?
・美味しいものを食べる。
・大好きなお友だちと旅行をする。
・欲しいものを手に入れる。
このように、自分自身の満足を得ることをすることでしょうか?
いいえ、違います。
それは、、、
『社会や共同体に貢献すること。』
(共同体に貢献し、役に立っていると実感することで自分に価値があると思えるのです。)
アドラーは言いました。
「私は自分に価値があると思う時にだけ、勇気をもてる。
そして、私に価値があると思えるのは、
私の行動が共同体にとって有益である時だけである。」と。。。。
自分の事ばかりに一生懸命になるのでなく
他人に貢献することをしてみてはいかがでしょうか。
きっと、あなたの勇気づけの壺も満たされるはずです。
そして、壺から勇気づけが溢れ出たなら
あなたの周りは自ずと勇気づけられて行くことでしょう。
2014年03月05日
勇気づけの心理学

本日、静岡県内24000人が高校受験!
こんばんは。minoです。
今日までの一日一日。
健康管理や学習成果をベストの状態で試験に挑めるようにと
親子ともども、これまで緊張の日々ではなかったでしょうか?
一生懸命に受験に向かって頑張る子どもを勇気づけ支援してきた皆様、
お疲れ様でした。
*******************
さて、勇気づけの心理学『STEP勇気づけセミナー』は、
子どものやる気を育て、生き生きとした親子関係を築くための
アドラー心理学に基づく親教育(支援)プログラムです。
効果的な親子関係を築き、子育ての指針となるしつけ法やコミュニケーション法を学びます。
アドラー心理学では
「人間は、この社会で生きていく上でその言動には、何らかの目的があるのだ」
と考えます。
そこでSTEPではまず初めに、目的を知るために「子どもの言動を理解する」ところから始まります。
たとえば、
「受験が近づくのに一向にやる気がなく机に向かわない子ども 」
」
そんな姿を見ると、親は心配になったり、がみがみ言ってみたくなったり、
イライラしたり、怒ったり ・・・どうしてよいものかと思われるかもしれません。
・・・どうしてよいものかと思われるかもしれません。
しかし、慌てることはないのです。
子どものその言動の目的を知ることで、その対応が分かるようになるのです。
多くの人たちは、そうなっている言動の原因を追究しようとします。
ところが、原因が分かったたところで過去に立ち返って、
子育てや人生をやり直すことはできません。
STEPでは、違います。
なぜそのような言動をするのか?
とその目的を知り、今ここから対応していけるのです。
これまでの親子関係を振り返り「間違った子育てをした。」と
後悔したり、自分を責めたりする必要はありません。
ただ、効果的な子育て法を知らなかったというだけなのです。
『STEP勇気づけセミナー』では
今ここから、影響しあえる協調的な親子関係を築いていく方法を知ることができます。
自分自身を勇気づけ、子どもを勇気づけ
大きな試練にも勇気をもって立ち向かうことのできる
そんな親子関係を築いてきましょう。
2014年02月26日
人生先輩の話はオモシロい
歳を重ねても、えがおいっぱい、明るく元気が自分流
・・・って人に会ってきました。
おはようございます。元気のたかまり・・・いや、かたまりminoです。
昨日は、お友だちのお母さまに、いろいろなお話を伺いにいってきました。
人生の実年齢でなく、自分の感じた年齢で溌剌と生きておられるお母さまは、
70歳には到底見えません。
その肌は、年齢よりも若々しく、みずみずしく透明感があり
疲れた様子などありません。
お話しながら、その瞳は子どものようにきらきらと輝き、
口角がクッと上がっていて幸福感に満ちています。
日々を充実して生活しているご様子が素敵に感じました。
毎日を大切に「今ここに生きている」方なのだな~~と、とっても刺激を受けました。
「20歳で何ができるか? 」と考えたとき
」と考えたとき
「夢と希望に溢れ、健康と体力があるのだから未来は永遠!何でもできるさ!
 」
」
と感じて生きていた私。
今「50歳から何ができるか? 」と考えてみると
」と考えてみると
未来に賞味期限があることを感じて、そこに開放的な感覚はありませんでした。
しかし、70歳の先輩に
「私は50歳から始めて今があるのよ。あなたは、それを、これから出来るの 。」
。」
と言われ、
「もう50歳、後30年しかない 」と思っていた人生の物差し が
」と思っていた人生の物差し が
「いま50歳、まだ30年もある 」に変わったとき
」に変わったとき
私の口角もくくくくく~~~~っ

 と上がった気がしました。
と上がった気がしました。
70歳になっても
「新しいものに挑戦する好奇心」と「バイタリティー」と「フットワーク」と「勇気」
をもっている人に出会い、まだまだこれから・・・と人生の勇気をいただきました。
愚痴や不満や噂話の不要な人生先輩のお話は、建設的な内容のもので、
聴いていてとってもオモシロいし、気持ちがいい。
幸せな人生とは?・・・・
「今ここを十分に生ききる」ことのできる人生なのかもしれません。
2014年02月24日
アドラー心理学の本
本のご紹介をします。
【『嫌われる勇気』・・・自己啓発の源流「アドラー」の教え】
岸見一郎、古賀史健 (ダイヤモンド社)
・「すべての悩みは、対人関係の悩みである」
・「人は、今この瞬間から変れるし、幸福になることができる」
・「問題は能力ではなく、勇気なのだ」
と喝破するアドラー心理学。
初めて、アドラーに触れる方にも、対話方式でわかりやすく書かれています。
***************************
日本では、アドラーの名前は、フロイトやユングに比べて、あまり知られていませんが
欧米では「心理学の三大巨頭」と称され、D.カーネギーなど自己啓発のメンターたちに
多大な影響を与えてきました。
アドラー派の見方や考え方は、現代多くの心理療法の中にその影響を見出すことができます。
たとえば、
グラッサーの現実療法、バーンの交流分析、フランクルのロゴセラピー、ロジャースのクライアント中心療法など。
私は、これまで、これらの心理療法について学習をしてきましたが、
行きついたのが「アドラー心理学」と「ギリシャ哲学」でした。
アドラー心理学は、現在、プラス思考心理学の一つとして、教育現場や自己啓発などに効果を上げています。
そして、アドラー心理学に基づいた『STEP勇気づけセミナー』は、
子育てをする親のためのプログラムとして開発されたものですが、
子育てのみならず、職場や近所付き合いなどのどんな人間関係にも有効な方法です。
『STEP勇気づけセミナー』を受講された皆様も、どうぞお読みください。
これまでの学習を更に深め、実践に広がりを持たせることとなりましょう。
☆ ☆ ☆  STEP勇気づけ shimizu room
STEP勇気づけ shimizu room ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【STEP勇気づけセミナー】
アドラー心理学に基づく実践プログラム
http://www.locoms.com/step-s.htm
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2014年01月30日
一生涯の勇気づけ
和装普及に努めるminoです。

(民族衣装普及協会会員なの・・・うふ)

着つけてみたのは、母の着物。
先日、映画「小さなおうち」を観ました。
女優の松たか子さんのお召しになっていた着物がとっても素敵で
昭和初期の和装文化の美しさも同時に楽しめる映画でした。
あの時代を、彼女も生きてきたのだ・・・ と
と
映画に母の人生をかぶせながら観ていました。
去年の暮れから、
「母が元気なうちに少しずつでも・・・」と、始めた母の和箪笥の整理。
そして、母から譲り受けた着物たち。
30着あまりの着物と
15本あまりの帯と
羽織と草履と小物たち。
着道楽でお洒落の母は
高度成長期の核家族化された時代に
仕事を持ちながらも父と二人で3人の子を育てました。
子育て支援などなく、今のように便利ではない時代。
それでも母はいろいろな習い事に勤しみ、自分を磨き
着付けにおいては師範の資格を持ちました。
そんな中、コツコツとためたお金で着物を仕立ててきたのです。
多くの着物の中には、作ったままに仕付け糸も解かれていない状態のものが
何着かありました。
いずれ、子育てから少し手が離れたら着ようとでも思っていたのでしょうか。
その時間もないままに、ずっとタンスの中に眠っていた着物たち。
今、私が着ることで、着物が呼吸をしはじめました。
母の着物に触れながら、母の生きてきた時代や生活に思いを巡らしています。
「母が元気なうちに少しずつでも・・・」と始めたことが
親の人生に寄り添いながら一時代の家族であった私たちの関係性を見つめ直し、
更には、自分の人生のあり方を考えさせられる良い機会となっています。
それが、私の心の中で大きな財産となりつつあることに感謝しつつ
母の着物をまとっています。
あたたかい。
しっとりとした重さ。
肌にじんわり。
安心感に包まれて。

母がいなくなった後を想像するのも哀しいのですが(涙)
きっと着物たちが、私を勇気づけてくれるものとなるでしょう。
一生涯の勇気づけ!!!
そうして、今日も走りつづけるminoがいますッ!!!
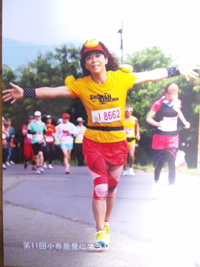
2014年01月29日
ウソはタダソレダケナノサ

おはようございます。
『理由なんてない。
理由なんていらない。
タダソレダケナノサ。』
の“走り続けるmino”です。
さて、今回は子育て相談にお答えいたします。
(こっちが本業。走ってばかりでもないのです 。)
。)
皆さんは、日頃、
子どもの気になる言動に振り回されていませんか?
今回は、あるお母さんからの
『子どもが嘘をつくのです。 』
』
というご相談です。
お友だちに行ったこともない外国の話をし
外国旅行はしょっちゅうしていると話す小学校6年生の娘。
お母さんは、ウソをつく娘の不誠実さに腹を立て
「そんな嘘ばかりつくとお友達がいなくなるよ」
「将来、ウソが嘘を呼び大悪党になるよ」
「ウソがばれていじめられるよ」
と、何とかそのウソはよくないのである、と子どもに伝えたいあまりに
脅しの言葉をかけました。
娘は、さんざん脅され、道徳的なことを言い聞かされました。
果たして、子どもは、説得されたのでしょうか?
『ああ、いけないことをした、二度と嘘はつくまい』と改心し、
ウソはいけないと納得したのでしょうか?
残念ながら、お母さんの努力(?)のかいもなく、
子どもの嘘は続いているそうです。
そのウソは、人を傷つけるような種類のものでなく
ただ何となく、自分を大きく見せたいがためのいウソのようです。
さて、今回の子どもの気になるい言動(ウソをつく)
に対処するための考え方に移りましょう。
STEP【アドラー心理学に基づく教育心理学】では、
ウソをつく子どもは、実は、“勇気のくじかれた子どもである”と考えます。
ですから、親が、脅したり、道徳的に説教することで、
さらなる勇気くじき となることには、お気づきでしょう。
ここで大事なことは
『人間の言動には目的がある』ということなのです。
Q. ウソをつくことで、子どもは何が満たされるのでしょう?
・ 友だちの注目を集めることができた。
・ カッコイイと思われた。
・ いいな~と羨ましがられた。
Q. 子どもの目的は、何だったのでしょうか?
この場合、子どもは友だちの『関心を引く』のが目的です。
関心を引き、自分に注目を集めたかった。
自分の存在を認められたかったのです。
(子どもは言うでしょう『タダソレダケナノサ 』と)
』と)
良いことで他人に認められたり、注目を集め続けるのは至難のわざです。
ならば、「ネガティブなことをしてでも関心が引きたい」ということになるのです。
この場合のウソをついてでも関心を引きたいという“勇気のくじかれた子ども”に必要なのは、
道徳的な説教よりも“勇気づけ”であったのです。
勇気づけとは、反映的に話を聞く、励ます、結果よりその過程を認める、
子どもの長所や能力を認める。。。などの行為です。
この場合、親は、裁判官や警察官になり、子どもの間違いをただそうと努めるのでなく
ただ、反映的に話を聞けばよかったのです。
しかし、最初の段階で(子供が嘘をついたと知った時)
お母さんの感情は、すでにイライラしたり怒ったりしたものでした。
これでは反映的には聴けません。
「ウソをついたのね。今、話を聞いてお母さんちょっと驚いちゃったわ 。(Iメッセージ)
。(Iメッセージ)
でも、ウソをついたらどんな気持ちだった? 」
」
と、言葉をかけてあげれば子どもは素直に話し出すはずです。
子どもの話を良いとか悪いとかの判断をすることなく
『この時、子どもはどう感じていたのか?』
に視点を置いて話を聞きます。
すると、子どもは自分の感情に気づき、整理していきます。
6年生ともなれば、子どもは、友だちの関心を得る方法としてウソをつくという行動が
この先も有効かどうかを判断していくものです。
子どもの言動に振り回され、親は、点々づけの“いい親”になって感情的に対応するのでなく
例え、子どもの言動は間違ったことと判断しても、まずは、子どもを信頼し反映的に聴く ことが大事です。
大変難しいことですが、まずは、自分の価値観を手放す勇気をもって、
子どもを違う視点から眺めるようにしてみましょう。
“視点の移動”です!
お母さんは、毎日忙しい。
前ばかり見ていないで、時には空を見上げてください。
そこには、青く澄んだ大空が、どこまでも果てしなく広がっています。
今日も一日、素敵な日でありますように!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
STEP勇気づけ【アドラー心理学に基づく教育心理学】
http://www.locoms.com/step-s.htm
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2014年01月27日
日本平トングRUN

こんばんは。 minoです。
日本平さくら通り(日本平山頂駐車場から日本平スタジアムに通じる旧道)の
ゴミ回収をして、面白いものが・・・・
DOMO(コンビニにある無料配布の就職情報誌)が3冊もありました。
そして、枕が1個 ・・・・。
競輪の車券が2枚。
回収したゴミを集計したところ
ジャジャ~ン!!!
1位 缶コーヒー
2位 コンビニ弁当
3位 ペットボトル
4位 農作業用資材
5位 おつまみの袋
6位 タバコの箱
7位 使い捨てマスク大人用
これらから何か気づきませんか?
そうなんですッ!!
ポイ捨ては大人がやっとりますんですよ。
子どもの飲むようなジュ-スや菓子類のゴミがないのです。
ささやかな罪悪感もないのか、どうかは、わかりませんが
「勇気がくじかれた責任感のない大人の仕業であるもの」と思われます。
しかしながら、『ポイ捨て反対!!! 』と叫んだり
』と叫んだり
『モラルの低下 』を嘆いたりする気持ちは
』を嘆いたりする気持ちは
これっぽちもありません。
そして、トングRUNの最中にすれ違う人の表情がまた面白い。
声を掛けてくれる人がいます。
「ご苦労様で~す。」
「すごいゴミっ。」
「あ、 あ、 こんちわ。」
視線を反らすように伏し目がちになる人 。
何故?なに?(走ってるの?ゴミ回収してるの?)とキョトンとする人。
ボラティア精神なる大層なものからやっていることではないので
「ありがとう」とか「スミマセン」とか「大変ですね」
と言ってもらうより一番嬉しかったのは、
「げげえ~ ゴミかかえながらこの坂をマジ走ってるなんて超変態~
ゴミかかえながらこの坂をマジ走ってるなんて超変態~ 」と
」と
話し掛けて来てくれたおじ様 。
ポイ捨てする人がいるかぎりminoのトングRUNは、楽しいトレーニングとして続けられますし
走る目的にもなります 。
だから『ポイ捨て止めろ』
と人に文句を言う暇があれば、回収して走った方が私の勇気づけになるです。
勇気づけに満たされていない人が、ポイ捨てをするのであれば、
きっと美しくなった山にポイ捨てをするほどの勇気も持ち合わせていないはず。
であれば、文句を言わない、叫ばない、嘆かない、原因探しや悪人探しをしている暇があれば
また一つ拾ってくることにします。
その方が、minoは勇気づけに満たされますからね。
誰か得かって?
そりゃ ポイ捨てした人より勇気づけを拾ってくるminoでしょう。
しかし、遥か崖下に放り投げ捨てられたゴミに関しては
市役所にお願いしようと思います。
本当は、クライムジムで鍛えたminoの技術を試してみたい気もするのですが・・・。
ぬふふふふ。
2014年01月26日
ゴミ回収トングRUN

こんにちは。 minoです。
昨日、いつものminoのトレーニングコースである
日本平さくら通り を走りました。
日本平マラソンのコースでもあり、
世界遺産である富士山と三保の松原を同時に見下ろせる
ビュースポットがいくつもあります。
最高に素敵な急坂コースなのですが
昨日は何やら勇気がくじかれ・・・・
なんでかな?

と考えてみると、
以前にもましてゴミの量が半端でないことに気づきました。
勇気くじきの基は“ゴミ”でした。
こりゃ~、たまRUNわ~
ストイックに走り込まない(込めない?)キョロキョロランナーのminoだからこそ
気づくことなのかも・・・
車やバイク、自転車の人には、目に入らないのだろうと思いました。
ランナー目線のゴミ拾い。
minoも気持ちいいし
トレーニングにもなる。
ってことで、本日、トングとスーパーのゴミ袋を持って
『ゴミ回収トングRUN』をしました。
持ち帰ったゴミは約4㎏。
重い分だけ、勇気づけの壺もたっぷと“キラキラした気持ちいい”
に満たされました。

枕・・・も落ちていたけれど
昨夜の雨にぬれ、ぐっしょりと重く。。。
「な、なんでやねんッ!」
と強めの一人突っ込みをカマシテみましたが
次回の回収に回しました。
風の強い日や寒い日には、モチベーションも下がりますが
そんな日にも「ゴミを拾いに行かなくちゃ! 」と勇気づきます。
」と勇気づきます。
さくら通りは、ゴミの山。
minoのトングRUNは、まだまだ続きます。
2014年01月25日
山本五十六の“勇気づけ"

こんにちは。 minoです。
今日は、尊敬する、山本五十六連合艦隊司令長官
(大日本帝国海軍の軍人。真珠湾攻撃を指揮した人物。
日独伊三国軍事同盟や日米開戦に最後まで反対していたといわれる。)
の言葉より。。。。
山本五十六の
『やってみせて、言って聞かせて、やらせてみて、 ほめてやらねば人は動かじ。』
という一文は、人を動かす法として有名ですね。
この言葉には続きがあるのです。
『話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。』
戦時中、絶対服従の軍隊で山本五十六は、率先垂範の態度で
相手に“勇気づけ”の気持ち(傾聴、承認、任せる、感謝、信頼・・・)
を持ちながら人を育てたのですね。
人を動かすには自分から。。。。
勇気づけの「やってみせ」です!!!