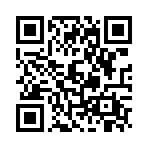2009年03月31日
人生午後の『更年期告知』

スイスの精神科医・心理学者のユングは、40歳を「人生の正午」と呼び、
その後の中年期を「人生の午後」と呼びました。
みのも、「人生の正午」を(とっくに?)過ぎ、体調や身体の変化を少しずつ感じてきています。
40歳を境目にして精神的にも肉体的にも変化して来ている自分を自覚し、
自分の生き方を考える時期にあるのだな~と感じていました。
そう。。。感じてはいるのです!!。。。が、、、、、、
ぬは~。。。精神的にはず~っと、27歳のままで止まっていましたのよ。
そりゃ、ズーズーしいですよ。確かに。。。
『“行け行け!バンバン!”の生活も、ここらでちっと考え直さにゃいかん!!』
今日はつくづくそう思いました。はいっ!!心底、心根の底から思ったんでございますよ 。
。
ココの所、体調が、ちびっとばかりパッとしないもんで、病院で診てもらいに行きました。
Dr.は、人間的にもできた方のようで、とてもお優しくこう言われました。
『あなたは、40歳を過ぎていますね。心身ともに変化してきます。今回のもそれですね。
これから先は、もっと、いろいろな事が起きてくるのです。
どうぞ、参考になると思いますので資料を読んでみてください。』
『あ~ 、先生、つまり更年期ですね・・・
、先生、つまり更年期ですね・・・ う~、精神的には27歳で通してきたのに。。
う~、精神的には27歳で通してきたのに。。
グスンッ 。あ~、騙せない騙せない。。。
。あ~、騙せない騙せない。。。 もう騙せない。。。
もう騙せない。。。 』などと
』などと
あがいているみのを先生はお優しく見つめ、決して『何をバカ言ってんだい! 』ってな
』ってな
お顔ではなかったのです。
『今日は、いろいろと検査をしておきますね。大丈夫ですよ。
1週間後にまた来てください。』と言われました。
はい、はい。行きます。行きますよ。
検査結果を見れば、もうあがけないでしょうから。。。
ズバ~っと見せてもらいましょう!!

それにしても、精神年齢27歳のみのにとっては、『更年期告知』は、とても悲しく辛いものでした。

帰りの車の中で“ワ~ン、ワ~ン”と泣いてしまいました。
本当に悲しいときには、“ワ~ン、ワ~ン”と声を上げて泣けるものです。

。。。。さて、今日から精神年齢37歳のみのが誕生しました。(え、えっ??? )
)
今日からまた、生活を見直して、人生の生き方を考え直しながら、
バンバン頑張りま~す!!
 (あ~、やっぱり、懲りてない・・・
(あ~、やっぱり、懲りてない・・・ )
)
2009年03月31日
桜咲く~合格しました!!

先日、受けた面接・・・
合格しました~っ!!
「わ~い、わい!!」とこの歳でも、合格とあれば、大層うれしいものですね。
『よかったね。』『おめでとう』『合格してうれしいんだね。』
などと家族に声を掛けてもらうことが、たまらなく嬉しくて、ニヤニヤしてしまいましたよ。
そして、
『はは~ん。。。子どもが嬉しそうにニヤニヤしているときってのは、きっと、こんな感じなんだよな~。』
などと思い、
さらに、さらに、子どもを“認めて”あげて、何事も“一緒になって大いに喜んであげよう”
 と思いましたよ。
と思いましたよ。
********
さてさて、滅多にないことでもあり、折角ですから、早速、勝手に
・・・・・『勝因分析~っ!』・・・・・
①伝えたいことを事前にまとめてあった。
②イメージトレーニングとロールプレイで表現力を鍛えた。
③提示された制限時間を厳密に守った。
④等身大の私でいられたこと。
⑤何よりも面接を楽しめた。
親もたまには、試験や面接などを受けて見る機会を持つと、子どもの苦労や喜びを知る事ができるものですね。
2009年03月30日
今日は離任式

今日は、子どもの通う小学校の離任式です。
お世話になった先生が、他の学校に移動することになると
親としてもほんとに淋しい気持ちになってしまいます。

子ども達も新しいクラスの発表があり、クラスメイトと初顔合わせをする
今日は、緊張・不安・楽しみ・淋しさ・・・
いろいろな感情が入り乱れ、朝から落ち着きなく、登校して行きました。

『ただいま~。』と言って帰ってくる様子を、今日はいつもより丁寧に見守りたいと思います。
2009年03月30日
大っきくなった!!
 子ども自身が成長するときに・・・
子ども自身が成長するときに・・・

・親(養育者)以外に信頼関係のとれている大人が一人でもいること
・活躍できる場があること
・自分の長所も短所も認めてくれる友達が一人でもいること
・自分が上級生として育てる必要のある下級生を持つこと
この時期、大きく成長した小学生の子ども達の姿を見てきました。
小学校から中学校への移行期は、子どもの学校生活の中でも大きな変換の時期です。
挫けず前に向かって進んで欲しい!!

2009年03月28日
ただいま

← 坂上田村麻呂(758〜811)の坐像
2泊3日の家族旅行から只今、帰宅しました。


急に京都をまわってから三重県の鳥羽・志摩と行く事に決まり、大した強行軍でした。


たまたま行った京都の清水寺では、99年ぶりに坂上田村麻呂(758〜811)の坐像がご開帳となっておりました。
んまっ
 、ラッキーでした。
、ラッキーでした。
そして、京都や三重では、マスクをしている人は珍しく、久しぶりに花粉症から開放されて快適でした。

これまた、ラッキーでした。

しかし、残念ながら、桜の開花にはちと早かったようでした。
されど、これもまたまた、ラッキーです。

残念だけれどラッキーとは???
なぜなら、次は、『桜の開花時期の夜間ライトアップされた清水寺』を拝みに行くという楽しみができましたからね。
ぬはは。。。
 食べて
食べて 食べまくり
食べまくり まして、
まして、これまた、ラッキーでした。

そして、帰りの高速道路では、ETCの1000円高速で渋滞に巻き込まれるかと思いきや、
渋滞はなかったので、ずんずん帰ってこれましたよ。
しかし、我が家ではETCの機械は取り付けていないので(ゲ~ッ???
 意味ナイ、、、)
意味ナイ、、、)普通に料金を支払ったのですが、料金所のおじ様が、驚くほど親切、親切!!!
『どうもご利用、誠にありがとうございます。どうぞ、お気をつけていらしてくださいね。』と
満面の笑顔でね、、、(ん~、、、昨晩、鏡を見て練習したんだろうな~。。。)
料金所で笑顔とは、これまた、ラッキーでした。

あはは~、なはは~、ラッキー、ラッキー・・・ルンルンルン。。。




最後の最後で、ズバリ・アンラッキー。。。。

『ぐうわ~ん・・・

 』夜間に雄叫びを上げる、みのの足元には、理想を大きく振り切った体重計のは、は、針が『はい、これまでよ!!』といわんばかりに正直に現実を示していましたよ。
』夜間に雄叫びを上げる、みのの足元には、理想を大きく振り切った体重計のは、は、針が『はい、これまでよ!!』といわんばかりに正直に現実を示していましたよ。




 」
」
2009年03月25日
懐かし ひよこ菓子

「銘菓・ひよこ」
東京の名物かと思っていたら福岡で産声を上げ製造したのは本舗・吉野堂。
昭和39年東京オリンピックの年に東京に現れたというから、まさにそのころ
みのには双子の弟妹ができました。(うッぷ。。。歳がバレバレ。。。)
当時は、「高級菓子・舶来品・めったに食べられない・贅沢品」と思っていたのは
『文明堂のカステラ』。そこに現れたのがひよこのお菓子。
お菓子とは思えないほど愛らしくて、すべすべしたなめらかな手触りは
高級舶来品『文明堂のカステラ』(?)とは違い、
子ども心にも何だか手が届きそうなものに感じたものです。

実はみのが、親の愛情の品定めとして選んだのが、この「銘菓・ひよこ」。
「父ちゃん、東京に行ったお仕事の帰りに買ってきて。どうしても買ってきて。 」
」
とせがんだ記憶があるのです。
しかし、「銘菓・ひよこ」は、東京で爆発的な人気となり、売り切れで店頭に並ばなく
なっていたようです。
それでも父は、何としても買って帰ろうとしてくれていたそうです。


どうしてもひよこのお菓子を食べたかったというよりも、当時生まれた双子の弟妹に
親の愛情をとられてしまったと感じていたみの(3歳)が、ひよこのお菓子で親の愛情を確かめようとしていたわけです。
子どもとは、何とむごいものでしょう。。。

今でも、みのの母は、『あんたは、ひよこのお菓子が好きだったね~。
何かといえば無理言って、お父さんに買ってきてもっていたものね。。。』
と、今もって母はその思いの奥にあるみのの企みを知りません。

子どもはどんな手を使ってでも愛する人からの“存在認知”を得たいものなのです。
“承認されたい”のです。

みのにとってのひよこのお菓子は、そんな“せつないお菓子”です。

2009年03月25日
競い合いを避ける教育

先にあげた、日本人論の続きです。
ある大学の講座で、年配の学生が、教授に質問をしました。
「昨今の教育現場で時に見られる『競い合いを避ける教育』『横並びの教育』といわれるものがあるが、これはおかしいのではないか。
競争しながらも互いにその努力を認められる世の中にして行くことが大事ではないのか。
我々の頃は、競争は当たり前にしてきたことで、その競争で得た結果もそれぞれが認め合い納得できていたように思う。」
と発言されました。
私には、心に響く問題提起でした。
ちょっと考えて見ました。
例えば、運動会で順位をつけないようにしたという学校があります。
その理由として
「競技において走るのが速いか遅いかというのは、個性の現れである。
人の個性を順位づけ(価値づけ)することは、教育上問題があると考え、順位づけをやめることにした。
そして、順位に関係なく皆の努力を認めるという運動会にしているのだ。」ということだそうです。
しかし、一方で、教科課題において(算数や国語など)は、テストをすることで点数化(評価)している現実があります。
すると、「走ることの速い遅いが個性というのなら、勉強の得手、不得手も個性ではないのか?個性とは何か?」
と考えてしまいます。
勉強の不得手の子は、図工や音楽や体育など、他の分野で自分を発揮して評価をもらい、
自己効力感が得られている子どももいます。
何でもかんでもが、横並びでよいとも思えないし、評価することが一概に悪いということ
でもないであろうと考えます。
事実、いったん社会に出れば “競争原理”に基づき、順位づけや評価がなされているのです。
このように、たとえ、教育現場で『競い合いを避ける横並びの教育』が行われようと、
社会に出れば激しい競争が待っている現実がここにあるのです。
私は、このずれが、“社会のゆがみ”として出てきているように思えてならないのです。
大事なことは、この男性が言った
「競争で得た結果もそれぞれが認め合い納得できていたように思う」
というところにあると思います。
つまり、競争を通して得た結果で、自分や他人に烙印を押すのでなく、その結果や努力を建設的に認め合える力を持つ仲間関係が育つといいなと感じます。
同時に「人間は、一人として同じ人がいない。だから、尊く、違うということは素晴らしい。」と人それぞれの違うことの良さを理解できる教育であればいいな?とも考えました。
競争原理が、「良い」とか「悪い」とかではなく、必要なことは『競争原理を越えた人類的・普遍的な価値の探求』にあると考えるのです。
2009年03月24日
何と鳴く?

この所、みのは、オノマトペ(擬音語・擬態語)の世界にはまっています。
『犬は「びよ」と鳴いていた』山口仲美:著。。。は面白いですよ。
そこに、こんなことが書かれていました。
昔の人は、猿の声を「ココ」と聞いています。でも、猿を見世物にするようになった室町時代からは鳴き声を「キャッキャッ」と写しています。
これは、猿の鳴き声が変わったわけではなく、「ココ」というのは、猿が満足そうに食べ物を食べている時の声であり、「キャッキャッ」は恐怖心を抱いたときに出す声を写したものだそうです。
猿の鳴き声の表し方が「ココ」から「キャッキャッ」に変化したところには、猿と人間の付き合いの文化的変化があるようです。
また。。。
犬も、昔は「びよ」と鳴いていたといわれています。
犬が落ち着いた環境で飼われたのは江戸時代後期であり、それ以前の野性味を帯びていたと きには
きには
「びよ」と写しているのです。低い声で「びよ~、びよ~」と吠えていたのかもしれませんね。
飼い犬と野犬では吠え方が違うといいますが、ペットのように飼われ始めてから犬の声は「わん」と写されたのですね。
このように、環境の変化によって、犬の泣き声自体にも質的変化があったようです。
そこで思い浮かべたのが、高度成長期時代の“働くお父さん”の泣き声ではなく、
仕事から帰って話す言葉です。
『風呂、飯、寝る』
あまりに忙しく働き通したお父さんが帰宅して話す言葉は、この3つだと言われました。
時代が変わり今の若いお父さん達は、「子育てに参加できない。してくれない。」と言う声はあっても、帰宅後の会話は3つ以上成されているようです。
経済、文化、環境的変化で人間も泣き声ならぬ、会話が変わるようですね。
2009年03月24日
日本人だよ。

日本人論として名高い『菊と刀』という本を読んだ事がありますか?
第二次世界大戦後のアメリカは、日本の占領統治を進めるために、日本人の行動様式を
理解する必要がありました。
そして、この課題に取り組んだのが、文化人類学者ルース・ベネディクトです。
彼女はの『菊と刀』(1944年)という日本論を著しました。
この本は、1988年にすでに100万部を超え日本人論としては最も広く読まれたものの一つだそうですよ。
読んでみると、荒唐無稽な記述も見られますが、当時の外国人から見た日本の姿が
そこにはあります。
といっても、ルース・ベネディクトは、日本に一度も来たことがないということですから驚きです!!
そして、そこには
『現在の日本社会においても払拭されていない日本的なものが鋭く摘出されている』
とも言われています。
その、今にして色あせていないと思われる一つに以下の文章をご紹介します。
『 日本人は従来常に何かしら巧妙な方法を工夫して、極力直接的競争を避けるようにしてきた。日本の小学校では競争の機会を、アメリカ人では到底考えられないほど、最小限にとどめている。
日本の教師たちは、児童はめいめい自分の成績を良くするように教えられねばならないという指示を受けている。
日本の小学校では、生徒を落第させてもとの学年をもう一度やらせるということはしない。
一緒に入学した児童は、小学校の全課程を一緒に受け、一緒に卒業してゆく。
成績通知表に示されている小学児童の成績順位は操行点(努力の有無)を基準とするものであって、
学業成績によるものではない。』
今の教育にも通じる形がここに見て取れるようです。
昨今では、『競い合いを避ける教育』『横並びの教育』『個性を大事にする教育』等を更に大事にしているように思います。
『菊と刀』は、「歴史性を無視したデータの使用法」や「聞き取り対象者の偏った選択」
など、用いられた資料に問題がなかったというわけではない・・・とはいいますが、
日本に一度も来たことがないというルース・ベネディクトが、これほどまでに日本を映し出し書いたその想像力には、本当に驚くばかりです。
2009年03月24日
肝斑(かんぱん)かよ。。。
 先日は、食べものの“乾パン”について書きましたが、今回は、お肌の気になる
先日は、食べものの“乾パン”について書きましたが、今回は、お肌の気になる
“肝斑(かんぱん)”について。
美容を専門職としておりました、過去の経験上、家事と子育ての毎日において
『洗濯干し、公園遊び、夏休みのプール・・・』などで多量の紫外線照射は、
積もり積もって、いつの日にか、必ずやみのを襲ってくるはず。。。
と嫌な覚悟しておりました。
そして、とうとう、、、来た~。 来ました~。
来ました~。
 来てしまいました~
来てしまいました~

 。。。
。。。
悲しいかな、それは、『しわ・しみ・そばかす』そして、極めつけに、
『か~んぱ~~ん!!』(かんぱん)として堂々とみのの顔に出現してきたのであります。
『か~んぱ~~ん!!』と『か~んぱ~~い!!』(乾杯)は一字違いなのにどうしてこうもうれしくないのでしょう。
とほほ・・・

悲しいやら、悔しいやら、ゾッとするやら。。。
しかし、しょ気ていても始まりません。
そこで、現在始めましたのが、“トランシーノ”
飲んでます。飲んでます。
まずは、2ヶ月飲むのですって。
飲みます。飲みます。最後まで!!・・・と書いてしまえば、続くかと。。。
『有言実行』です!!

がんばります。

2009年03月23日
サイエンス・ワールド

← 東海大学海洋学部

行って来ました。
今日、東海大学サイエンス・ワールドが開催されました。
小中学生を対象に『みて、さわって学ぶおもしろ実験会』です。
参加者は、グループに別れて
*算数(数学)・・・メビウスのふしぎ
*化学・・・石けんの力でミニボートを動かそう
*物理・・・圧力のふしぎ(肺の模型)
をやりました。
大学の先生方が趣向を凝らして授業をしてくださいました。 
大学生のお姉さん、お兄さんに従って実験をしました。
“理科離れ”を心配されている子ども達ですが、みな真剣な表情で授業に参加し、瞳はキラキラ と輝いていましたよ。
と輝いていましたよ。
大学構内を廻りながら、実際の実験室や教室で学ぶ授業は、子どもたちにとって
とてもよい経験となりました。
ありがとうございました。
2009年03月23日
懐かし ドラム缶・トカゲ

子どもの頃、よく遊ぶ空き地があった。
そこには、どういうわけかドラム缶が一つ置き去りにされていて
そのドラム缶を使って、私たちは、たくさんの遊びを創造した。




*ドラム・バランス(ドラム缶を倒しその上に乗ってバランスをとるゲーム)
*ドラム缶風呂(風呂に入ったつもりになる“つもり遊び”)
*ドラム缶はドラム(いろんなものを拾って来ての青空音楽会をやった。ドラムの役割)
一番楽しかったのは、捕まえてきたトカゲをその中で飼う事だった。
トカゲとは、何て賢く、すばしっこく、生命力のたくましい生物なのかと
私は大好きだった。
あの、ちょろちょろ加減が素敵だ。あこがれだ!!
でも、そう簡単には捕まえられない。
今でもトカゲを見かけると、思わずしのび足になり、手が延びてしまう。。。
全身がメタリックなトカゲに出会った日には、
『やった~!今日は、絶対に何かいいことがある!』と思えたものだ。
尻尾がメタリックブルーのトカゲに出会った日には、
『素敵なものをお持ちだな~。』とうっとりとしたものだ。
トカゲは、敵に襲われると自分で自分の尻尾を切り離すと言う技を持つ。
何と、潔く毅然とした態度であろう。
『痛くはないのかしらん?』『そこから毒は入らない?』などと心配したが
トカゲは同情されるに似合わない生き物だ。
切り離された尻尾さえもが、チュルチュルといつまでもうごめいているのだから。
ドラム缶の中に入れたはずの賢く、すばしっこく、生命力のたくましいトカゲたちは、
翌日にはきれいさっぱりと姿かたちがなくなっているのだ。
素敵だ!!
トカゲの季節が始まった!!

2009年03月22日
私の猫は左利き

← ヒゲ1本白がチャームポイント
七雄くん
セシリアが言うのです。
『七雄(猫)は顔を洗うときも、、皿を引き寄せるときも、御飯を手ですくうときも、
いつも左手だよ。(ハードのキャットフードを一粒一粒、手ですくって食べます。)
はは~ん、この子は左利きだったんだ!だから器用なんだ!』

。。。左か利き??ほんとうかな~?15年も飼っているのにみのは知らんかったぞ。。。
と、みのも、よく観察してみる事にしました。
子どもは、面白いことを見ているものです 。
。
みのは、時々、子どもの視線になりたくて、その場でしゃがんでみたり中腰で何かをしてみたりします。
すると新しい発見があります。
『うわ~、こんなところに埃がいっぱい!』
とか、嫌な事もあるけれど、
『うわ~、つくしが生えてる~。』
とか、いい事もあります。(つくしはいい事です。)
春休み、子どもの視線になって、いろんなところでいろんな経験をしてきます。
中腰で歩いているみのを発見したら、「やってる、やってる!!」と思ってください。



***
数時間後、七雄は左利きである事を確認いたしました。
***
2009年03月22日
『育てる』チューリップ

少しばかり時期を遅れて、1月のはじめに植えたチューリップの球根。
今、やっと5cmばかり、濃い緑色のしっかりとした葉が出揃ってきました。
楽しみだな~。
そこで。。。考えて見ました。
私は、チューリップを育てながらヒヤシンスになる事を期待してはいない。
『このチューリップはどんな色で咲くのかな?』と、
チューリップである事を認めながらその美しさを想像するのである。
例えば、家庭菜園でミニトマトの木に、ブドウがなることを期待してはいない。
ニンジンを育てるときに『どうぞ大根になっていますように。。。』とは思っていない。
しかし、子どもを育てているときにはどうだろう?
『鯉を育てていながらくじらになる事を期待したり、
鈴虫を育てていながら蝶々になる事を期待するような事はないか?』
そう考えると『育てる』とは、その子の特性・性質を知りながら、その子の持っている本来の力を引き出し、引き伸ばすことであると思います。
そして、その子らしさを認めながら、持てる力を発揮する場、活躍できる場を設定する事にあると思います。
我が家のチューリップは、玄関先で持てる力を発揮しようとしています。
にぎやかに咲き揃うのを楽しみにしています。
4月の始業式には、きれいに咲き揃うかな?
2009年03月21日
自己ちゅ~『E』

『子どもは自己中心的視点にとらわれていてある年齢にならないと対面する相手の視点を想像できない・・・』
といわれています。
でもどうでしょう?
大人になっても私達は基本的には、自分の視点から世界を眺めているのであって、
そこから他者の視点を取得するのはかなり難しいのではないでしょうか?
そこで、お試しください。
【自分のおでこに『E』の文字を向かいの相手から見ておかしくないように描いてみましょう!】
いかがですか?簡単にできましたか?
私達は大人でも、自己中心的視点にとらわれやすいものなのですね。
2009年03月21日
懐かしき テカテカ

みのの小さいころにゃ~、ハナタレ小僧やハナタレ小娘はたくさんいた。


母ちゃんは、一々『はい、チーンしなさい。』なんて言ってくれなかったし
チーンと上手にできる子は、何だかさっぱりときれいな顔をしていた。
チーンとできない子は、洋服の袖で拭く。袖は、テカテカ としていた。
としていた。
そして、埃だらけの顔がキチャナク(汚く)まだら模様になっていた。
それでも誰もいじめたりしなかった。
いつもテカテカした袖が、勲章のように輝いていたK君。
それでも誰も汚いと言わなかった。
昔の子どもはそれなりに、みんなキチャなかったのだ。
今の子どもは美しい!!
鼻などタレていたひにゃ~、ティッシュを持った手がス~ッと延びてきて
洋服の袖にお世話になる必要もない。
懐かしき テカテカ。。。。
あの頃、子ども達もテカテカ キラキラ
キラキラ 輝いていたように思う。
輝いていたように思う。
2009年03月20日
緑々しきかな
 ちょっとばかり、当てもなくちろちろとドライブ
ちょっとばかり、当てもなくちろちろとドライブ に行ってきましたよ。
に行ってきましたよ。
行った先は、はいっ! 焼津!!
みのの住むところより更に、緑輝き 鮮やか
鮮やか で、心洗われましたよ。
で、心洗われましたよ。
菜の花が、『春よ。春だよ。』とそよそよと踊ってました。
今日は、陽射しも春めいて、なんだかちょろりといい事が起こりそうな
そんな気分になりました。

こんな、まったりとした日常も大切なんです。
2009年03月20日
懐かし ハイカラな幸せ

子どもの頃、お隣に引っ越して来たお宅は、とてもハイカラだった。
ある日、子どものいないお隣さんが「遊びにいらっしゃいな。 」と誘ってくれた。
」と誘ってくれた。
うれしくて、うれしくて、興味津々お家に上がった。
お部屋の中は美しかった。
今思えば、子どものいない家では、こんなもんなのであったのだろうが。。。
「幸せそうだな~。幸せってのは、清潔で、良いにおいで、静かなものなんだな~・・・ 」
」
な~ンて勝手に思ってみた。
すると、急に緊張してきた。
外で泥だらけになって遊んでいるキチャナイ(汚い)子ども がお邪魔するには
似つかわしくないと思えたからだ。

お隣さんは、優しい声で『ホットケーキ食べる?』と聞いてきた。 
『ホットケーキって何? 』
』
というとしばらくして、二段重ねのまあるいケーキが出てきた。
それは、あまい香りととろけるバターと蜂蜜でできていて、そのお隣には
フォークとナイフが付き添っていた。
『うわ~ 昼間っから(?)、フォークとナイフだなんて、何と贅沢なんだろう!
昼間っから(?)、フォークとナイフだなんて、何と贅沢なんだろう!
大人になった気分だ!! 』
』
とソファーからおしりが15cmくらい飛び上がったのを覚えている。
お隣さんは、優しく食べ方を教えてくれた。
「昔の人の苦労を思え!」というおやつの乾パンとはわけが違った。
私の“幸せ”の定義が増えた。
幸せとは・・・清潔で、甘いにおいで、静かで、やわらかくて、
優しい問いかけと大人な気分。
ついでに、レースのカーテンとクッションの効いたソファー。
(我が家にはないものだった。)
あまりにも幸せで夢のようなひと時だった。
『また、食べにいらっしゃい。』と言われ、帰るときには、額がつま先に付くほどおじぎして、
更にこう付け加えるのを忘れなかった。
『私には、双子の弟と妹がいます。
カーテンに触らせないし、ソファーで跳ねさせないので、今度一緒に連れて来てもいいですか? 』
』
『もちろんよ。』
この幸せを弟と妹にも味合わせてあげたかった。
こうして、お隣さんに子どもができるまで、私たち兄弟は、“ハイカラな幸せ”を楽しませてもらった。

2009年03月20日
春休み前 家族会議

春休み。
楽しい、楽しい長期休暇を有意義に過ごす為に
恒例の“長期休暇前・家族会議”を開きました。
議題は、『春休みの過ごし方と目標』
「春休みの娯楽」「勉強&運動」「お手伝い」について決めました。
娯楽については、「京都・志摩旅行」のほかに、「映画(ヤッターマン)」と
「ボーリング」が追加されました。
ア~、楽しみです。
後、こうして何回、みんなで過ごす春休みを持てるかな?

2009年03月19日
つ、通知表。。。

← 『ゆ~らり、ゆ~らり、ゆっくり、ゆっくり』の太郎吉
今日は通知表を頂いて来る日でした。
朝、太郎吉は、
「うん。いけてると思う。テストもよかったし、たくさん発表もしたからな。 」
」
と言って自信満々に登校して行きました。。。
(注:先のブログに書きました)
みのは、『通知表が痛知表にならなきゃいいな~
 』
』
と思って送り出しましたが。。。
な、、、なんと、、、なんと
太郎吉の持ち帰った通知表は「よくできた」の3重丸の数が、前期の2倍に
増えていたんですっ。
確かにがんばっていたのは知っていましたが。
それにしても、2倍よくなるってのは、どんなもんなのでしょう?
いかに、今までが低空飛行 だったかってことは解かるけど。。。それにしても。。。
だったかってことは解かるけど。。。それにしても。。。
そう言えば思い出しましたよ。
スイミングのコーチが、テストでやっと合格した太郎吉へのコメントに、
『やっと、今回は合格です!
しかし、“2回目の泳ぎで、いきなりタイムを6秒縮めるというのは
今までどんな泳ぎをしていたのか?”と反って問題ですね。』
と厳しくご指摘いただきました。
(ううう、、、た、確かに、、おっしゃるとおりです。
 )
)
太郎吉は、通知表に大喜びでしたので
「1年生からコツコツと今まで努力した結果が、5年生の今に実を結んだね。
太郎吉は器用じゃないけど、忍耐・努力ができる子だもんね。よかったね。
 」
」
と勇気づけました。
そして、時間がたってから、こうも尋ねてみました。
「・・・それにしても、何でこうも一気に成績やスイマーのタイムが上がったんかね?」
すると、太郎吉は
「んま、“やる気、気合、目的意識”だな。・・・今まで力抜いてたな~。 」
」
どうやら、自分の力の出し方が解かっていなかったようです。
 『ゆっくり育つは、よく育つ!』
『ゆっくり育つは、よく育つ!』
太郎吉や、あなたはあなたでいいんだよ。
そうさ!太郎吉。よくがんばった!!
 合格っ!!
合格っ!!