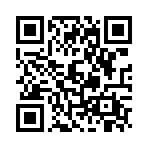2009年10月29日
こころ柔らかく

「こんなこと出来て当たり前」
「何でこれができないの?」
と言いながら、繰り返しイライラ、ガミガミ・・・・
終いに、相手を不信に思い、勝手に自分で落ち込んでみる。。。。
こんな子育てや対人関係を繰り返していませんか?
もしかしたら、本当に相手の方は、そのことが苦手で、一生懸命取り組んでも
できないのかもしれません。
しかし、もしかしたら、できないというのは「やりたくないからしない・やりたくないからできない」
のかもしれませんよね。
いずれにしても、できない、したくないというのなら
「相手が喜んで取り組める方法・相手が受け入れやすい方法」をこちらで用意する必要があるのです。
「私が言ったように何故しない!何故できない!」と責めたところで
自分から取り組むようになるわけが無いのは、
そう強要しているその人自身が良く知っている事なのではないでしょうか?
こころ柔らかく。。。。
「この手がダメなら、あの手で行こう」と柔軟に自分の気持ちを入れ換えましょう。
こころが硬いと相手との関係も硬直していきます。
こころが硬くなっている時は、お顔も硬くなっているはず。
当然相手は拒否反応を示すか、言うがままのロボットを演じるか。。。。
相手はその行動からは何も学んでいないのです。
相手に建設的な行動を求めるのなら、こちらも柔軟な心構えで、「心柔らかく」いきましょう。
2009年10月26日
夜間パトロール

昨夜のこと。
地域の安全のために自主的に始めました~!!
【夜間パトロール】
20時から1時間ほど歩きます・・・・
歩きます・・・・
歩きます・・・・
って。。。あはっ。。。。
「地域の安全のためにパトロール」????
といえば聞こえがいいけど、
ようはウォーキングです。
***************
セシリア 「母ちゃん、一人で大丈夫?」
太郎衛門 「母ちゃんなら、3時間でも5時間でも大丈夫だよ。行っといで。」
と何やら、嬉しがっていいんだか、何なんだか分からない応援を頂き、
イザッ、出発!!
***************
事故なし! 迷子なし! 火事なし! 痴漢なし! 落し物なし! のら犬なし!
地域の安全、良しッ!!
静かな夜が更けていきました。
2009年10月25日
ホット一息

ここのところ、静岡市健康福祉審議会委員として会議続きでした 。
。
「健康福祉基本計画策定委員会」
「地域福祉・健康づくり合同分科会」
「第2回健康福祉審議会」
・・・・・・・・・・・・
たて続いた会議もやっとここで一息。。。
それにしても、行政の事務局担当者の皆様のお仕事振りはお見事でっす!!
「早い、正しい、美しい」
三拍子揃っておりますよ!!
一部の公務員の軽率な対応で、公務員に対する非難の声が多々聞こえても参りますが
多くの皆様は身体を壊さんばかりのお仕事振りでっす。
行政依存の市民の姿も正していかなければ成らないと感じています。
2009年10月24日
減量はオリジナル法で

減量して変化したこと・・・
まずは、背中やお尻や、二の腕、太腿、ウエスト、腹・・・・
ありとあらゆるところがスッキリしてきました。
ついでに、足の甲や手のひらまでスマートになっちゃって、
くつもブカブカです。
シミも薄くなるのですね~。。。。
疲れも減り健康的に成ってきました。
以前の仕事柄、人様の美容管理、プロポーション管理、食事管理はお手の物。
かといって、自分の事となると後回しとなっていました。
今回の自己管理では、自分が「気持ちいい」と思うことを取り入れてプログラムしていますので
ワクワクして続いています。
卵ダイエット、りんごダイエット、バナナダイエット
ダンベル、ジョギング、マシン、骨盤矯正、マッサージ、つぼやせ
美容体操、レコードダイエット、断食、、、、、、、、
んと、ま~、世の中にはごまんとダイエット法がありますが
皆様も是非、自分の気に入った方法を見つけて、それらを上手く組み合わせて
オリジナルなプログラムで試してみてください。
『自分にあった、自分らしい方法を、自分で組み立てる』
・・・・そうです!!
オリジナリティが大事なのです。
これこそが、長続きする、成功の秘訣です!!

自分の体が喜ぶ方法を見つけましょう!!
2009年10月23日
6㎏減量 成功っ!!

8月末から始めたウォーキング。
今の季節、金木犀の香りに誘われて、出かけていきます。
黄色く揺れるセイタカアワダチソウ。
黄金に輝くススキの野原。
移り行く季節を味わいながら、現在も楽しんでいます。

このウォーキング・・・
ダイエットのつもりで始めたわけではなかったのですが、
始めてみると、2週間ほどでminoの体重は2kg減。
んま、こりゃ、体脂肪が落ちたというより、むくみが取れたのでしょうが。
それでも、前更年期にあるこの歳でむくみであろうと何であろうと
体重を落とすのは至難の業。。。。
飲み食いしなきゃ2kg位は簡単に落ちたあの若かりし頃とは違い、
年を重ねるごとに、にっくき脂肪はminoの身体に取り付き、しがみ付き
そう簡単にゃ~落ちないのでした。
ところが、楽しみながら体が絞れるとなっちゃ~やめられません。
今では、ウォーキングに加え、簡単なトレーニングと脂肪燃焼排出マッサージと食事管理で
この2ヶ月弱で、何と6㎏の減量となりました。
エ~ッ、6㎏減?
そ、そんなにくっついていたん?
水分と脂肪。。。
体が軽くなると、心も軽くなり、煩わしい事は羽が生えていつの間にかすっ飛んで行っちゃいますし
何より、体が求める栄養素のみを理性を持って摂取するように変わるのです。
目が欲しくなるという事もなくなり
衝動にまかせて食べるなどという事も、はたと無くなりました。
しばらく、この気持ちいい体を保持すべく、楽しみながらトレーニングを続けま~す。
2009年10月19日
『第24回くさなぎ井戸端会』

『くさなぎ井戸端会』では。。。。。。。
「障害を持つ、持たないに関わらず、地域みんなでお互いの違いを認め合い、
助け合い、楽しく子育てできたらいいな...」と活動しています。
自分の子育てをとおして『発達障害』の理解に近づきながら、実践的なコミュニケーションについて
皆さんと一緒におしゃべりトークしながら学習していきます。

今回のテーマは、【子どもへの“心配”と“信頼”】
日 時 : 平成21年10月22日(木):毎月第4木曜日
10:00~13:30
場 所 : 長崎新田スポーツ広場(交流センター)
2階和室
参加費 : 500円
お子様ご同伴でどうぞ!!昼食をご一緒できる方は、ランチをお持ち下さい。
◆お気軽にお申し込み、お問い合わせください。
LOCOMS 子育ち・親育ち&発達障害啓蒙
http://www.locoms.com
2009年10月15日
子どもからの“挑戦”

【 STEP 第1章 「子どもの気になる言動」について 】
『子どもが“挑戦”を仕掛けてくる… 』と感じることや経験はありませんか?
』と感じることや経験はありませんか?
例えば。。。。
・あくまでも我が儘を貫き通そうとする。
・現状に見あわない要求をしてくる。
・屁理屈を言う。
・親を怒らせたり混乱させるために「子どもの気になる言動」
( 関心をひく、主導権争い、仕返し、無気力を示す)を仕掛けてくる。
などなど・・・・
子どもは無意識に親を試します。
どこまでなら許して貰えるかと探るために“仕掛けてくる”こともあるようです。 
親が、このような子どもからの“挑戦”に乗り、感情を乱し怒ったり混乱して反応している限りは
子どもは、さらに“挑戦”を強化してきます。
こんなときは、親は子どもの感情に巻き込まれないように気をつけながら、
“温かく”なおかつ“毅然”として
『その手は通用しないよ。乗らないよ。』という態度を示さなければなりません。
子供のネガティブな挑戦には乗らず、建設的な言動で返しましょう。
『親がネガティブな挑戦には乗らない』と分かれば自ずと
“子どもからの挑戦”は次第に減ってくるものです。
2009年10月13日
なるほどの“コンテナ”

昨日のブログで 『稚魚200匹をさてどうしましょう?』
と皆様にご相談を持ち掛けさせて頂きましたところ、
静岡市在住のMさんから早々に良いアイデアをいただきました。
「御近所様の屋外にかなり大きな バスタブ? コンテナ?・・・用の物で
たくさんの金魚を飼っておられるお宅があります。」
と写メまで送っていただきましたよ。
う~ん!! すんばらすい~!! お見事でっす!!
“静岡気分”の生活品活用バンクの『ゆずってください』コーナーに
早速申し込んでみる事にします。
Mさん、ありがとう!
2009年10月12日
稚魚 200匹 。。。

今年の七夕祭りの『金魚すくい』で我が家の一員となった“紅赤(赤一色)”の金魚たち。
9月を“春”だと勘違いして産卵し、数日後に孵った卵は数知れず・・・・
あ~ん、、、野鳥友の会の会員さんが知り合いにいないのが、これまた残念。。。。
恐らく、200匹近い稚魚が居り、元気にスクスクと成長していますです。
それらを、現在3つの水槽に分けてありますが、、、、
稚魚が成魚に成りつつあり。
これらが、すべて成魚となる日も近く、嬉しいやら 悩ましいやら
悩ましいやら ・・・・
・・・・
飼い主のセシリアは、一匹たりとも手放す気はなく・・・
太郎衛門は「セシリアに気づかれないようこっそりと、一日5匹づつ草薙川に流せ。」
と無責任なことを言う。
しかし、このまま成魚に成った日ニャ~室内の水槽どころじゃない。
釣堀の池のようなものが必要になるんでしょうね~・・・

“紅赤”で池が真っ赤に染まるのを見てみたい気もするが、
池など作れる土地もなし、いわんや金もなし・・・
あ~ん、セシリア以上に悩ましい日々を送っているminoであります。
この健気な200匹たちは、本当に可愛いです!!
一匹も欠かすことなく手元で育てたいセシリアの気持ち、、、、
よ~くわかるのです。
どなたか良いお知恵を下さいまし。
2009年10月11日
「子どもを変えたい」と思う親

どうしてこうもだらしがないのかしら?
何で自分の考えをもたないのかしら?
何故、お手伝いをしないのかしら?
いつからこんなに反抗的になったのかしら?
 ・・・・・
・・・・・
あ~、んもう~、いやんなっちゃう。
毎日この子のお陰でクタクタだわよ・・・・
子どもを変えるにはどうしたらいいのかしら?
何かいい方法は無いのかしら?
自分の行動に責任感を持ち、自主的に考え、積極的に行動し
思いやりの持てる子にするにはどうしたらいいのかしら?
・・・・・
こう願いながらも、目の前の子どもを見ては嘆いている親御さんも多いのではないでしょうか?
さてさて、、、、、
そもそも、、、、、
子どもを親の思いどおりに変えることなど、果たしてできることなのでしょうか?
子どもは、親の思いどおりになるロボットであるわけは無いのです。
そこで、子どもを変えたいと願う時に大切だと思われることは,,,,,,,
『親として、子どもが自ら変わりたいと思える“日々の生活”を用意してあげる事』・・・・・・
なのではないでしょうか?
つまり、親は子どもの『発達の願い』を見守りながら、
“変わりたい・・・乗り越えたい・・・”
と思える日常を工夫し、経験の場面を用意する事。
親がしつけと称して罰したり、叱咤激励でコントロールして子どもが変わるわけではないと思うのです。
子ども自身が、日々の生活の中で気づきを得ることができたり、
経験を通して自分自身を信頼し、「自分は変わりたい、変われるのだ」
と思う気持ちが持てるように、子どもを勇気付けていくことで
子どもは自らの心の内に湧き上がる自分自身への“信頼”と“正義”をもって
前向きに変わっていくものだと感じています。


2009年10月09日
修学旅行 延期・・・

とおとお・・・・・
6年生の太郎吉のクラスも学級閉鎖となり
14日からの修学旅行は“延期”と決定いたしました。
当の本人も、しっかりと新型インフルエンザに罹患し
うなっておりましたが・・・
その他の学年にも学級閉鎖のクラスが出てきています。
このまま、『学校閉鎖』にならないことを祈っています。
尚、既に新型インフルエンザから回復した子どもを持つお母さんから
アドバイスをいただきました。
。。。。家族に広げない方法として。。。。
ポイントは、
“隔離”と“マスク”
んもう、これに尽きる!!
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
、、、ってんで、厳しく実行しています。
皆さんもどうぞ充分お気をつけ下さい。
2009年10月06日
“障碍”は“個性”なの?

障碍も個性と言えるのでしょうか?
障碍と個性の線引きはできるのでしょうか?
何をして、その障害を個性であるといえるのでしょうか?
難しいところです。
障害をもつ子どもたちと関わって30年以上が経ったという 近藤 直子氏はこう言います。
『障碍も個性』だと言う言い方がなされる時があるが、
機能障害が自己変革の願いの“発生”や“発展”を妨げる時
それは本人にとっては個性でなく、発達上の障碍だと言えるでしょう。
子どもの持つ機能障害が、本人の『発達したい、成長したい』と願う気持ちや行動の妨げとなるときには
そのことはやはり個性ではなく、本人にとっては障碍なのです。
このことからも、『障碍も個性のうち』と言いきれるのは、
「そのことを享受しているご本人の言葉として発せられる時」
なのだと感じます。
皆さんは、どうお考えですか?
2009年10月04日
学級閉鎖

いよいよ身近に迫ってきた感じの『新型インフルエンザ』 。。。。。
子どもたちの通う小学校でも学級閉鎖のクラスが出てきました。
6年生は、後数日で小学校最後の最大イベントである“修学旅行”が控えています。
みんなが揃って無事に出かけさせてあげたいところですが、神に祈るのみです。
新型インフルエンザの感染力は非常に強いようですが、実際に発症した子どもたちの様子は
思ったよりも軽く済んでいる子どもが多いようで安心しています。
しかし、何よりも学級閉鎖になってしまうと辛いのは、1週間はジッと家の中に居なければならないこと。
感染していない元気な子どもも同様です。
習い事や部活動もお休みします。
さて、、、子どもたちのストレスはいかほどでしょう。。。
もちろん、お母さんのストレスは・・・・恐ろしいほどに?????
そこで、考えました。
『もしかして、1週間、家で待機・・・のmino家の過ごし方』
・発病者が出た場合は、家族みんなが交代で看病をする。
・図書館で山ほどの本を借りてきておく。
・腕を上げよう!子どもの“料理力”(この機にじっくりと子どもの好きな「料理」を教えちゃいます。)
・1週間で作っちゃおう! “マイ箸&箸ケース”(庭の梅の木でマイ箸作り。)
・『世間から隔離された1週間』をじっくり味わってみることで『日頃の生活を見直そう!』
せっかくの1週間を『悔しい!残念だ!つまんない。』と嘆いて過ごすより
まずは、珍しいこの機会を日頃頑張っている子どもたちへの“休息のボーナス”だと思い
日頃の生活を見直す“チャンス”に変えてしまおうと思いました。
万が一、新型インフルエンザに感染してしまっても、学級閉鎖になってしまっても
とりあえず母としてのminoの気持ちは『ドンと来い!』です。