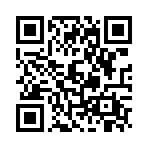2014年04月14日
めでたく親子関係契約更新

21時20分過ぎると近所のスーパーは値下げします。 ダ~ッシュッ!!!
ただいまっ~。minoです。
『隣の芝生は真っ青』って話です。
中2の娘が、
「A子ちゃんはいいな~。あんなお母さんがよかった。
何でもかんでもやってくれる。スケジュール管理も。遊びに行く段取りも。
洋服も買ってくる。いいよな~、楽で。楽な母ちゃんがほしいな~~~。 」
」
minoが
「へ~。何でもやってくれて、それで、ああしろ、こうしろと、口は出さないの?」
と聞くと
娘 「・・・・あ、そっか~、Aちゃん、うざいうざいって、あんなにやってもらっていて、うざいって 。」
。」
mino「ふ~~~ん」
娘 「Aちゃんて、勉強もよくできるし、生徒会にも立候補するような積極的な子なんだよ。
でも、ここぞという大事なところで困ってしまうとどうしてよいか自分で判断つかずに泣いちゃうんだ。。。
泣いたって始まらないのに。
だから、責任ある仕事は任せられないんだよ。」
mino「ふ~~~ん」
娘 「・・・Aちゃんて、甘やかされて育った子なのかな?
・・・親が全部やってきちゃって自分では解決できないのかな?
ああ、面倒くさいや。楽な母ちゃんとは、結局、面倒くさい母ちゃんということか・・・」
mino「ふ~~~む」
娘 「自分で決めて自分で責任を取るほうが楽でいいや。楽な母ちゃんでなくていいや。
しばらく今の母ちゃんでいいや! 」
」
mino「ふ~~~ん。しばらくね?じゃあ、母ちゃんを取り替えたくなったら、また、相談してね。」
ということで、今年も「めでたく親子関係契約更新」と相成りました。(パチパチパチ)
2014年04月12日
「身投げのバッシュ」明らめる
花粉にやられてしまっています。 ズズズル・・・
こんばんは、minoです
写真をご覧ください。
身投げでしょうか?
いいえ違います。
娘いわく「バッシュを干している」ということらしいのですが、
どう見てもだらしなく脱ぎっぱなしの体です。
小さいころは男の子?と間違えられる言動や様相であった娘も
今や中学2年生となり、オシャレに興味を示す多感な女の子に成長しました。
(・・・のはずなのですが・・・ )
)
娘は、よく言えば「さっぱりしていておおらか」な部分があります。
それが見方によったら「だらしない、いいかげん」な部分でもあり
今でもこのようにしっかりと残っています。
さて、、、、
子育ての相談でよくあるのが“忘れ物”をするお子様の相談です。
「うちの子は、何度言っても忘れ物が治らない。
先生からも家庭でしつけてください!と言われ
あの手この手で忘れ物をしない子にしようと毎日頑張っているのに・・・ 」
」
と言われます。
「そこまでされて、お気の毒です。
残念ですがお母さん、、、、、忘れ物の性分は治りません。
命を忘れるようにさえならなければ良しとしましょう。」
と、お答えすることがあります。
仕方がないからと無責任に述べているのではありません。
子どもの『忘れ物をする子』という特徴を個性ととらえあきらめましょう。
・・・ということなのです。
「あきらめるって? 」
」
と驚かれるますが、諦めるとは、明らめるとも書きます。
この場合のあきらめるとは、断念することではなく
「事実を明らかにして認める、受け入れる」ということです。
『忘れ物をする子』として受け入れることで、親子関係の無用なストレスが軽減され
逆に子どもは勇気づき『忘れ物のない子』になりたいと思えるようになるかもしれません。
いつも忘れ物をして叱られたり、勇気をくじかれたりしているのは子ども自身なのですから。
あきらめる行為は、明らかにして認めるということです。
認め、受け入れることができたならば心は穏やかであります。
私はこうして今日も「身投げのバッシュ」を明らめ
心穏やかに美味しいコーヒーをいただいています。
2014年04月10日
色とりどりの存在

本日、静岡市は気温25度の予想。
おはようございます。minoです(*^^*)
新しく受け持たれた先生を前に、子どもも親も、期待に胸ふくらんでいますか?
さて、
「子どもたち一人ひとりの個性を認めるためにも、まずは教師自身が色とりどりの存在であるべきだ。」
と乙武洋匡氏は言う。
同感です。
色とりどりの個性豊かな先生方のいる学校に通う娘は、ありのままの自分を上手く表現できているようでイイなあ、、、と感じます。
一人ひとりの個性を尊重し、受け止めてくれる大人に触れて育った子どもは「みんな違ってみんないい」を
‘自由勝手’
というわがままなことではなく
‘一人ひとりが大切な存在である’
というふうに人を尊重する捉え方ができるように思えます。
尊重されて育った子は、人を尊重することができるようになる、、、
当たり前ですが、そういうことです。
我が子の尊重を願うならば、先生のあら探しから始めるのではなく、
保護者も先生を尊重し、応援する気持ちを持つことが大切に思います(*^^*)
2014年04月09日
笑顔はバロメーター
おはようございます。minoです(*^^*)
ある施設で
『子育て。育てるのは笑顔です。』
ってポスターを見ました。
ほんとだよなあ、、、と感心し、
しばしポスターの前で腕組み頷く私は‘変な人’に見られた模様。f^_^;)
でも、子どもの笑顔はいろんなことでのバロメーターやろー?
^o^ 違うかや?
今日も元気で、いってらっしゃーい
(^O^)/

2014年04月08日
子どもの自発性に期待したい
おはようございます。minoです。
新学期、子どもへの期待は如何程でしょう?
ですが、、、
親は「やらせたい」「させたい」というけれど...
「やりたいからやる」という自発性とやらが伴わないと、本当のよろこびは生まれないんだわよねえ。
たから「やらされている」限りは続かないんだよなあ。
それでもって
「諦めが早い」とか「根気がない」とか言わないで!ってんだわよ。
勝手すぎるぞ!大人っ! ( *`ω´)
、、、って、
子どもの頃の私が怒ってる ( ̄Д ̄)ノ
どうぞ、子どもに自発性が芽生えることに期待してみてくださいね (^.^)

2014年03月21日
まぶしいティーンエイジャー

春、、、別れと出会いの季節です。
おはようございます。minoです。

中学一年の娘・セシリア。
(花束を持って卒業式に向かいます
 )
)この一年間の成長は、驚くばかりで親の私にも希望を分け与えてくれています。
しかし、今はちょっぴり淋しそう。
この春、大好きな先生や先輩とのお別れがありました。
彼女の成長のための光となり、支えとなって下さった方々です。

先生や先輩のような、手本となり尊敬できる”憧れの人”を持つ者は宝ものを手に入れたようなものだなあ、、、と思います。
目の前にある憧れが目的を生み、それが時として夢や希望となります。
セシリアは今、希望に満ち溢れています。
まぶしいよ。まぶしいよ。

私は、あんなに存分に輝いていたかしら?
『どうか、あなたらしくあれ

そして、もっともっと輝いて!


私の分まで輝いて!
 』
』セシリア応援団団長 minoは、今日もこう言って叫んでいます

続きを読む
2014年03月19日
若者たち

卒業の季節です。
おはようございます。minoです
4月 光る風の中
背すじ伸ばして輝いて
空を見上げてまぶし気に
旅だって行く若者たち
mino
嬉しくもこころ淋しいこの季節。
親も子も自立の時です。
2014年03月17日
春、親を思うと

卒業式も、もう間近 。あ、あ、あ、子どもたちの成長は眩しいですね。
。あ、あ、あ、子どもたちの成長は眩しいですね。
おはようございます。minoです。
『おはよう。
お父さの具合はいかがですか?
この春、Aちゃんも卒業だね。
子どもが大きくなってホッとすることが増えてきて、
でも、いつの間にか自分の親はオヤッ?と思うほど年老いて来ていて、
それがどういうことかって、わかっていたつもりでも、がく然とするものだよね。
私の母も大分、弱音を吐くように(吐けるように)なっていて、
子どもを連れて春休み中に会いに行こうと思います。
Mちゃんも、Aちゃんをそう育ててきたように
今度は、お母さんの話しを反映的に聴いてあげてね。
私もそうしてきます。
今日も一日素敵な日でありますように 。』
。』
朝から大事な友人の一人にこの様なメールを送っていました。
友人を思いながら、私自身を励ますように!
友人を勇気づけるつもりが、友人に勇気づけられている毎日。
こんなとき、人は一人で生きてはいない。
人の支えによって生かされている・・・ということを感じます。
育ち行く子どもたち、老い行く我が親。。。。
一日一日を大切にしていこうと改めて思う。
今日も人との出会いの中で、皆様にとってかけがえのない一日になりますように。
2014年02月08日
止められないよ。

おはようございます。
minoです。
静岡は、暴風雪警報発令中!



太郎吉の高校では、休校措置がとられました。
そんな中・・・
インフルエンザで寝込んでいた娘が、まだ寝込んでいてもいいくらいなのに
早朝よりバスケの試合に出るといって出かけた。
4日後には、中学で最も大事な後期試験がある。
寝込んでいたため、勉強もはかどっていない。
「試験の出来は心配であるが、ここまで来たら仕方ない。
自分の力を出し切るしかない。。。 」と腹を決めたようだ。
」と腹を決めたようだ。
親としては、試験はどうであれ、体調が万全でないうちに激しいスポーツをすることで
病がぶり返すことが心配だ。
しかし、本人は心に決めてしまっている。
自分で決めたら最後、一歩も後には引かない彼女だ。
いつも寛容で柔らかな彼女だが、こういう時には立派な頑固者になるのだ。
試合に行くことで逆に病を跳ね返す勢いだ。
仕方がないね。
彼女の人生だもの。
たとえ、試験の結果がどうあろうと、体調が悪化しようと、自分で選択し決めたことだ。
中学生にもなり、もう、心配する親の言うことなど聴きはしない。
結末は、ドッコラショと、自分で背負う!!!と、いうことらしい。
決意は、ヌグググッと固いのだ。
説得などしようものなら、壁にバゴン、ガゴンと、二つ三つ穴が開くであろう。
んま、ココは、親として彼女の決断を尊重しよう!
しかし、、、、
むふ、む、むふ、む、むふふふ~~~
そっくりだ!全くだ!そっくりだ!
誰に?
あ・た・し・に。
アホなところが似た者親子だ。
そうと決めたら、がんばれや!
途中でリタイアした場合は、何とか力になってあげるさ。
のほ、のほ、のほほほ~
私も『野辺山ウルトラマラソン100㎞』で、風邪による熱発中であったのにも関わらず
“気のせい、気のせい”と、鼻水 風になびかせながら、13時間も走りつづけたっけな~。

倒れこむように完走して、そのままスグに、夜間バスに揺られて直帰し
自宅に着いて、ヘロヘロしながら3日間ほど働いた後、、、、
くぁ、くぁららうぃ、ちくぁららぁ、はりりゃりゃりぃ~~・・・
(か、からだに、ちからが、はいらない~~・・ ・)
・)
となって、
ありゃ~、こりゃ~、気のせいじゃ~ないや。。。 。と流石に認めたよ。
。と流石に認めたよ。
うふふふふ、、、肺炎 になってたっけ~。
になってたっけ~。
ぬあぬはははは。
そんなんだもの、言えんわよね~~~。
ダメだなんて、止められないわよね~~~。
言ったところで、聴くわけないわよね~~~。
、、、んざけろ、、、って言われるわよね~~~。
まあ、鼻水垂らしながらも、思いっきりかっこよくシュート決めてこいや!
ないすしゅ~~~~。じゅる。
2014年02月03日
親子ミュージカル♪

おはようございます。
ピッピになりたいminoです。
土曜日、楽しみにしていた[有度山トレイル]のボランティアをする予定が、突発的な事情により参加できませんでした。
上級クラスの選手の走りをこの目で見て“何だ、これっ!” ってものを盗みたかったのに・・・。
ってものを盗みたかったのに・・・。
残念でした。
日曜日は、ロゼシアター(富士市)で、お友だち親子が出演した
静岡県民ミュージカル「長くつ下のピッピ」
を観てきました。
子育ての苦労を共にしてきた彼女が、舞台の上でピカピカに輝いていました。
彼女の人としての“良さ”や“持ち味”が、その役どころを通して溢れ出ていたのです。
「こんな才能や能力を持っていたんだな~・・・ 。」と、友だちであることをとても誇りに自慢に思いました。
。」と、友だちであることをとても誇りに自慢に思いました。
自信たっぷりな友だちの姿を見るのは、自分への勇気づけとなり嬉しいものですね。
子どもとの関係性に悩み、よい影響をしあえる親子になりたいと願い、ずっと一生懸命に努力してきた友。
それを見てきただけに、親子が同じ舞台に上がり、一つになって歌い演じている堂々とした姿に感動し
不覚にも、わ~んわんと、大泣きしてしまいました。
そして、この親子なら大丈夫。。大丈夫。。とうなづいていました。
誰にも輝けるその瞬間がある。

舞台に輝く、友だち親子の笑顔が眩しい『ピッピ』でした。
今日も良い日でありますように! mino
2014年01月31日
受験、未来はきっと

おはようございます。
目覚めたら、今日もminoです。
って、、、あたりまえなのだ・・・。
んが、、、たとえば、朝、目覚めたら、今日は象です。とか、ランドセルです。
とかってなってたら楽しいでしょうに。。。
どうなのかしらん?
それでもやっぱり、象の中身はminoで
ランドセルもminoだったりするんだろうか・・・?
形を変えてもminoはmino。。。ってことか。
そんなんじゃ~つまらないから
それならば、minoの“まんま”の“そのまんま”でいいや。
ということで、今日もminoです。
(って、、、導入、長っ!!!すみません )
)
ヘンな妄想はさて置いて、
ぽかぽかの春はまだまだ先なのに
早くも春の訪れのご報告を頂いております。
『minoちゃ~ん、サクラさく!やりましたで~~~。咲きましたで~~~~ッ!!! 』
』
という、合格通知を手にして
喜びに満ちたお母さん方の悲鳴・・・いや、嬉しい雄叫び・・・いや。。。。???
とにかく、いっぱい届いています。
お母さん方のホッとした気持ち伝わるな~。
あるお母さんは『ああ、これで安心して寝込めます 。』って。
。』って。
う~~~ん、これまで、具合が悪くなっても、寝込む自由もなかったんだね~。
子どもの受験は、家族にとっても大きな試練。
子どもに寄り添いながら勇気づけ、ときに叱咤激励し子どもと共に戦い抜きます。
この戦いは、相手を倒す戦いではなく自分に打ち勝つ戦いです。
サクラの咲いたご家庭では、合格通知を目の前に大きな勇気づけ となったでしょう。
残念ながら、願いが叶わなかった受験生も
『咲こうが、咲くまいが、ここに至るまでの過程(努力や試練に立ち向かう勇気、鍛錬、積み重ねた知識・・・)
が大事だったんだ。
 』って
』って
人生のどこかで振り返れたらいいな~~~と思います。
ともかく、とにかく、お疲れ様。
あなたの“まんま”の“そのまんま"
未来はきっと素晴らしい!!!
2011年12月05日
第7回清水インドアアーチェリー大会

昨日の日曜日、清水総合運動場体育館にて第7回清水インドアアーチェリー大会
がありました。
冬の時期は、アーチェリーは屋内(体育館)での試合となります。
小学生~大学生、社会人まで幅広い層が集まり、遠く離れた的に向かって一斉に矢を放ちます。
前日の夜間に大会準備をしました。
子どもも大人も総出での準備。
的の土台にするのは、畳です。
この畳が重いのなんのと・・・・。
倉庫の中でしっかりと水分を含んだ畳の重さはすごいものです。
大の男が2人がかりで一枚の畳をえっさえっさと運びます。
どういうわけだかminoも畳を運びます。
(他のお母さん方は、椅子出しなどの作業を主にしていました。)
これが、良いトレーニングになりました。
昨年、患った五十肩は右。
今回、畳運びで最初に悲鳴を上げたのは左腕。
意外や意外。
翌日、左腕の筋肉痛は「鍛えていただきありがとう 」と言っているようでした。
」と言っているようでした。
歳を重ねると脚力より腕力の方が先に衰え始めるようで
重いものの移動が大変になったり
指先の力が減退するので、袋菓子などが開けづらくなるようです。
ひょんなことから、自分の身体の変化を知り淋しさを感じたわけですが
そんなことにはお構いなく、セシリアは今回の大会でもがんばりました。

3位入賞
メダルのリボンの部分くらいは、
minoの畳運びが貢献したのではないですか?
・・・と、セシリアに聞いてみると
、、、、そら、無い
ってさ!
なははははっは。
さて、本日9時半より『勇気づけサロン・昼の部』を開催します。
たくさんの楽しいワークをご用意しています。
お待ちしています!
2010年05月29日
“ピタリ”と止まる

我が家に“虹”がかかりました。
激化していた太郎吉との主導権争いは、昨日から“ピタリ”と止んだのです。
彼は、主導権争いを仕掛けても来ません。
建設的な親子関係に戻れました。
元々、こじれた親子関係ではなかったので、私の心の構えを点検し変えることで
太郎吉の様子が変わったのです。
日々の生活の中で、時に親子関係が悪循環に陥っていくことがあります。
それに気付いていながらも、そこから脱却できない時は
自分自身の“心の構え方のあり様”を見直すことが大事です。
私の“心の構え方は・・・・・
頑なになっていないかな?
緩みすぎ放任になっていないかな?
諦め無気力になっていないかな?
・・・・・・・
相手を変えようと思っても変わらない。
自分の心構えが変わることで、自分から発するオーラが変わるのですね。
自分が変わることでしか相手は変わらない。
2010年05月28日
初体験! 中学校の授業参観

あっちへ、こっちへと、こんがらがっちゃう~~~~~。


昨日は、昼間【くさなぎ井戸端会】開催
夜間は、【スポーツ指導者養成講座】出席
今日は、太郎吉の中学校の授業参観(指定された3日間、自由に参観できます。)
午後は、静岡市健康福祉審議会の打ち合わせ
明日は、セシリアの小学校の運動会
午後から、太郎吉の中学校の保護者会と、
夜は、保護者懇親会
・・・・・・・・・
ああ~、この山越えたら少しは落ち着く・・・・。
と思い、勇んで出かけた本日の中学校授業参観。
1時限目:数学。
「ふえ~~~、男子校ってこういう感じなんだ~~~~。 」と感心しました。
」と感心しました。
なんか、みんな朗らか、
素直、
キリキリ・ピリピリしていないで、かといってダラケテモいない雰囲気、
一人一人が、まだどこかしら幼くて、でも一生懸命
どういうわけだか、クラスの半数の子の髪の毛が立っていた(寝癖を直す余裕は
まだないのか、それとも、女の子の視線がないからか、、、は、わかりませんが・・ )
)
・・・・
「へ~~~、なんか新鮮~~~。 」
」
太郎吉の様子はというと、一生懸命に授業に取り組む姿は真剣そのもの。
(こんな真面目な姿を参観会では見たことがない)
まだ、緊張がほぐれていない様子。
「太郎吉の愉快なところや、おどけたところは、まだきっとみんなに見せて
いないんだろうな~。
どの子も充分に溶け込んでいるわけではないであろうに、一生懸命にこうしている。
健気だな~。がんばっているな~。 」
」
そう思ったら、思わず涙が出てきてしまいました。
(ンゲッ、参観会で泣くとは・・・・ )
)
ここのところ太郎吉との主導権争いが激化していました。
そんな様子を見ていたセシリアは
「お兄ちゃん変わっちゃったね。母ちゃんとよくケンカになるね 。」
。」
と言っていました。
太郎吉が新生活の緊張感とストレスと疲労とで、いっぱいいっぱいなのは
わかっていましたが、どうしても主導権争いを交わす術が見つからないでいました 。
。
何が何でも、認めて欲しかったんだよね。
頑張っている自分をもっと労わって欲しかったんだね。
自分の知らない新しい世界、未知なる試練が、目の前に次々に現れて、まるで
襲いかかられるようなのかな。
・・・あなたの不安感をもっともっと、感じてあげられればよかった。
もっともっと頑張りを認めてあげられればよかった。
ごめんよ。太郎吉。。。勇気づけがもっともっと欲しかったンだよね。
今後も暫くは、主導権争いをしかけれる事態が続くと予想しますが、
受け流せそうです 。
。
私はこれまでの自分の対応を反省して、自分を責め立てるのではなく、
今日の参観会の太郎吉の健気な姿を思い出すことで、太郎吉の【気になる言動】
に乗らずにかわすことが出来るような気がします。
授業参観、行ってよかった。
子どもの様子、クラスの様子、先生や学校の様子、、、
見て、知って、感じて、理解して、納得できて、本当によかった。
2010年03月05日
閉鎖的な会話からの“立て直し”

セシリアに3月7日の「駿府マラソン・ハーフマラソン女子一般」
に出場することを伝えたときのことです。
セシリアは、「 え~っ?!母ちゃん、すっご~い!!絶対に応援行くっ!!
え~っ?!母ちゃん、すっご~い!!絶対に応援行くっ!! 」と、興奮気味。
」と、興奮気味。
「母ちゃんが、ハーフマラソンに参加することは、まだ内緒にしておいてね 。」
。」
と言うと「わかった!内緒にしておくっ! 」
」
・・・ん、、、しかし、その日の夕食の時、セシリアはいきなり、、、、
「母ちゃんが、7日のハーフマラソンにでるんだってさ!!」
( う、う、うぉ~いっ。そりゃないだろ~!“内緒”って言ったばかりじゃ~ないかい。。。
う、う、うぉ~いっ。そりゃないだろ~!“内緒”って言ったばかりじゃ~ないかい。。。
 )
)
===【気付き・その1】子どもに“内緒”は、通用しない!====
すると、それを聞いた太郎衛門が、
「無理だ!無理だ!そんなモン、お前に走れるわけが、ないじゃ~ないか! 」
」
と、いきなりのダメ出し(閉鎖的な会話)で、minoにガツンと一撃!
mino「おいおい!無理ってのは、完走を想定してるからだろ?ハーフを走り切るのが目標じゃないんだ。
参加だよ。雰囲気だよ。どこまで行ける自分を試すんだ!チャンスだろ?
お気楽な気持ちで参加するんだ。
ってやんで~。ほっといてくれっってんだい! 」
」
と、こんな時には、浅草生まれの気質で応酬し、太郎衛門にバコ~ンと逆襲!
このように、はなっから、ダメ出しされると、多くは
「落ち込んで、諦めを選択する」か「発奮し、俄然やる気になる」かのどちらかだと思いますが
minoはもちろん「発奮し、俄然やる気になる」のでした。
がははははっ・・・・。
こうなったら、「ハーフマラソンに出場して楽しく走ること」で建設的に太郎衛門への“復讐”を
成し遂げるつもりでありますっ!
うぉっふぉっふぉっふぉっ・・・・。
===【気付き・その2】子どもも『はなっからのダメ出し攻撃』を親から受けているよな~。====
『閉鎖的な会話』より『開放的な会話』の方が、コミュニケーションを円滑にし、より良い関係
(信頼関係、尊重し合える、安心できる・・・など)を作っていくものであります。
しかし、たとえ『閉鎖的な会話』を受けてしまっても、又、その会話に乗ってしまっても、
『勇気づけのバケツ』が満たされていれば、その後味の悪さを長く引きずることはありません。
『勇気づけのバケツ』が満たされていれば『すぐに建設的な自分に立て直せる』のです。
マラソン大会参加で、minoの『勇気づけのバケツ』を更に満たしてきま~ス!!

2010年02月16日
どの子もMAX!

『子どもたちは、どの子もMAXがんばっている
 。』
。』
『本当は、子どもたちは、今ある自分の力の限りを精一杯を出し切りたいと“願っている”のだ。
 』
』
昨日は、そう感じることの出来る一日でした。
*******************
「『我が子も、今日一日を精一杯がんばり抜いたのだ。
結果はどうであれ、その姿に“万歳”なのだ!』
・・・と、いつでも、どこでも、どんな場面でも、そう認めてあげられたら良いのに・・・
それを中々認めてあげられない自分がいる。。。。。 」
」
そんな、親御さんは多いと思います。
私もそうです。
そんな時は、心に繰り返し言い聞かせています。

『子どもたちは、どの子もMAXがんばっている。
本当は、今ある自分の力の限りを精一杯、出し切りたいと“願っている”のだ。 』
』
と・・・
*******************
親は、子どもの日々のがんばりを認めてあげられないで、がんばっている子に
「もっとがんばれ!」と言っている。
がんばっている子は、もうこれ以上がんばれないから辛い。
「がんばっているというのに、これ以上、どうがんばれと言うのだよ~・・っ・・!!!!
 」
」
子どもの身体も心も悲鳴をあげる。
「がんばれ!」ではなく「がんばっているね!」と認めてあげたい。
「がんばれ!」ではなく「がんばっているね!」と声を掛ける日常でありたい。
2010年02月15日
人間距離

前回のBLOGでは、思わぬことから大喧嘩を見てしまったminoでしたが、
その場面に出くわして感じたことは、
『車間距離も大事だけれど、人間距離も保たないと事故に遭う! 』ということでした。
』ということでした。
今回は、知らない者同士の肩が接触して衝突してしまった、“物理的な人間距離”の事故でしたが、
人間関係においては、心の距離という“精神的な人間距離”を保たないと、
これもまた事故に遭うのですね~。。。。
ズカズカと相手の心に踏み込む事も
よそよそしく知らぬ存ぜぬでいる事も
時と場合によったら、人間関係に事故を起こしてしまいます。
距離間(感)の取り方。。。。 これって、とっても難しいけど大切なこと。
これって、とっても難しいけど大切なこと。
車間距離のように慎重にいきましょう。
ですが、車間距離をとるように、慣れるとその場その場で自然に人間距離間が上手く取れていくもので
もあると思います。
2010年02月13日
公衆の面前での大喧嘩

明日はバレンタイン。 チョコレートを買いに、とある特設会場に。。。
チョコレートを買いに、とある特設会場に。。。
『流石、混んでいる~!! 』・・・・・
』・・・・・
と思いきや、、、、
ん???
何だか周囲の様子が変なのです。
狭いバレンタインデー・コーナーの中央では、何やら不穏な空気が漂っていたのです。
何と、それは公衆の面前での大喧嘩でした。
『 ぶつかった、謝った、態度が悪い、納得行かない、引っ込みつかね~、クソ婆~、、、
ぶつかった、謝った、態度が悪い、納得行かない、引っ込みつかね~、クソ婆~、、、 』と
』と
耳を覆いたくなるような文句を、大の大人が延々と大きな声でまくし立てているではありませんか。
どうやら、騒ぎを聞いて駆けつけた店員さんも、余りのことにオロオロするばかり。
何の役にも立っていません。
むしろ、当人達の態度はヒートアップしていくばかり。
大勢のギャラリーのいる前で、どうやら双方とも引っ込みが付かなくなってしまったようで。
“主導権争い”によるケンカは、仲裁に入った店員と、観衆の視線によって引っ込みが付かなくなり
“仕返し”にまで発展しました。
*****************
・・・・・『あ~あ、子どものケンカと一緒ヤネ~・・・』
そうして、いつもの事ながら、
『もしも、私が店員だったら?』
とここで又考えちゃいました。
*****************
原因が何であれ、大喧嘩が始まってしまったわけですから、今更、犯人探しをしたところで
収まりません。
むしろ悪化させます。
双方の言い分を聞いていたところで、交通整理ができる状態ではありません。
そこで、まずは、双方を少しでも落ち着かせるために私がとる方法は、、、、
① まずは、謝る。(ナンデ、店員が謝るか?)
ケンカの原因は、混雑した中でぶつかったところから始まった。
特設会場は狭く、ディスプレイの仕方や、レジの位置も悪く、客の流れは滞り混乱していた。
混乱が予想されるであろうに、明らかに、イベント会場としての設置方法に無理があった。
そこをすかさず謝る。
「大変失礼を致しました。当方の会場が狭く、お客様方に嫌な思いをさせてしまったようです。」
② 次に、ギャラリーのいないところへ場所を移して頂き、心置きなくケンカしてもらう。
「お客様のお話しを静かなところでお伺いたいと思います。
申し訳ございませんが、ご一緒していただけますか?」(・・・と事務所に誘う。)
少し落ち着き、観衆もいなくなれば、自分たちの愚かさにも気付くというもの。
場所を移動したら、
③ 後はケンカの仲裁などせず、
「何分にも、本日は最終日ということで、大勢のお客様がお見えになり、当方も狭い会場で
大変申し訳なく思っておりましたところでございます。
どなた様にも気持ち良くお買い物をして頂けますようにと、日々、努めてまいりましたが、
この度は、お客様方には、嫌な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
今後とも精一杯努力させていただきますので、本日は、お気持ちをお納めいただきまして、
何とかお許し願えないでしょうか。」(・・・と深々と頭を下げる)
実は、「ケンカなどして恥ずかしい」と思っているのは、当人達のはず。
しかし、「けんかの原因は自分ではない」と思いたい。
そこで、けんかの原因は、双方にあったのではなく、“店”にあったということにしてしまえば
これ以上の恥の上塗りは、やめようというもの。
いかがかしら?
2010年02月12日
宣告してない?

「この成績じゃ、受からないぞ!」
「お前は何をやってもダメだな!」
「お前のここが悪いんだ!」・・・・
子どもに対して、こう“宣告 ”する事はありませんか?
”する事はありませんか?
このように先生や親に、バッサリ、グサリ とやられて
とやられて
① 発奮する子

② 絶望し自暴自棄になってしまう子

がいると思います。
“宣告”が功を奏して、その子のやる気に火をつける結果となるのであれば良いのですが、
多くの場合は、やる気を失ったり、親や先生への“憎しみ”や“復讐心”を駆り立て
自分自身に絶望し、自暴自棄になってしまう子が多いと思います。
教育、しつけ、子育て・・・は、“治療”ではありません。
子どもの悪いところをダイレクトに指摘して、明らかにしたところで
『よし。頑張って、治そう!』というものでもありません。
教育、しつけ、子育て・・・では“治す”のではなく“育てる”視点が大事なのですね。

2010年02月11日
親は弱音を吐いてはいけないの?

親は、子どもの前で愚痴を言ったり、ぼやいたり、弱音を吐いたり、
弱みを見せてはいけないのでしょうか?
あるお母さんが言いました。。。。。
『親として子どもに弱みを見せるのはいけないことだと思っていた。
自分が子どもに弱音を吐いたり、弱みを見せたら、子どももそういう弱い子になりそうだから。 』
』
と言うのでした。
????? はたしてそうなのでしょうか ???
子どもは、親の姿を見て育ちます。
すると、子どもは、弱音を言わず、弱みを見せられない親から何を学ぶのでしょう????
『人に弱みを見せてはいけない。』
『愚痴やぼやきやネガティブな言動はしてはいけない。』
もしも、そう感じ取ってしまった子どもがいたならば
その子は、“弱音を吐かない子”になるのでしょうか?いいえ、“弱音を吐けない子”になるのだと思います。
自分を励ましながら、忍耐強く自分を律して滅多なことでは“弱音を吐かない心丈夫な子ども”に
育って欲しいと親は考えます。
もしも、その様に育って欲しいと願ったならば、親自身が完全・完璧でない事を認めることです 。
。
『あ~、母ちゃん結構頑張ってるつもりなんだけど、結果を出すのはしんどいことだね・・・・。』
とぼやき、弱音を吐いた時に、太郎吉もセシリアも
『母ちゃんは、よく頑張っているよ。大丈夫、僕たちは知っているからね。』
と励ましてくれます。
そして、子どもたちが弱音を吐いた時には
『そうなんだね~。人生はママ成らない。それでもきっと、あなたなら乗り越えられるよ。 』
』
と励まします 。
。
人間は完璧ではないのです。もちろん、親だって完璧ではありえないのです。
親が、弱みを見せない、完璧であろうとする心構えから、子どもにも完璧を求めてしまうものです。
こうした親の心構えが影響して、何事も弱みを見せず、完璧であろうとする子どもは、
確実に一番になれないことや失敗の可能性のあることは避けて通る子どもに育つ可能性があります。
考えてみてください。
弱音を吐いて心を整理して、乗り越える力にしている場合もあるのではないですか。
弱音を吐く子は、だらしがない弱い子ではないのです。
弱音を吐いても自分の力で、何とか乗り越えていける子どもに育てていく事が
前向きに挑戦する子どもを育てていくものだと思います。
大切な事は、親が、子どもの前で強がって見せるより、「親として・人間として」ある姿から
子どもが、感じ取って、学んでくれる事ではないでしょうか?