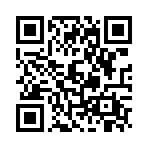2009年03月08日
相互理解へ近づく





皆さんは、自分自身のこと、子どものこと、家族のこと・・・
どれだけ理解していると思われますか?
「私は、自分自身のことをどれだけわかっているといえるのであろうか?
何をどれだけ理解しているというの?
我が子のことは、どうであろう?よくわかっているつもりでも、私とは別人格。
わかった振りしているけれど、我が子をわからないとしても当然。
そんな、私が他人のことを理解したいと思っても果たして理解になぞ近づく
ものであろうか?」と・・・
しかし、思うのです。
「本当に理解することなどできないとしても、大事なことは理解したいと願う思いや行動・姿勢など、そのプロセスではないかしら?」と・・・
そんな時にこんな出会いがありました。
第9回『くさなぎ井戸端会』に参加くださったあるお母さんの言葉です。
(了解を得てご紹介します。)
「私は2人の子どもとも発達障害で普通の子どもの子育てはしたことがないので、
(定型発達の子を持つ)皆さんがどのように思って行動しているのかを知る事で
私の偏りがはっきりとわかりました。
今後は、偏った考え方を減らしていけるよう普通の子どもへの理解を深めて
行きたいと思いました。」
こう言っていただいたのがとってもうれしかったのです。
活動を続けてきてよかったと思える瞬間でした。

私自身は
「“双方は、はじめから互いに違うのであるから理解なぞできるわけがない。”
と諦めて距離を置いてしまうのでなく
“違うなら、その違いに対しての理解に近づきたい。”」
と願い活動を続けてきました。
しかし、この願いは一方通行では成らないのです。
双方による『理解に近づく願い・努力』が大切なのです。
相互理解なのです。 


障害を持つ子どもの親も、そうでない子どもの親も、“子ども同士”
を真ん中において、子ども同士の関わりの中から双方が理解に近づいていけると考えます。
その可能性があることを、このお母さんは教えてくれました。