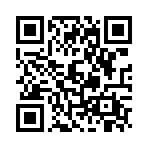2011年02月10日
「第32回くさなぎ井戸端会」ご報告

H22.9.9(木)行われました、くさなぎ井戸端会の内容をご報告いたします。
テーマ 「子どもの将来を見通しての選択」
参加者22名で賑やかな学習会となりました。
ありがというございました。
以下、その内容をまとめたものです。
*********************
今回はまず、普通学級から支援学級へと進路変更した後、またさらに節目での進路選択を経験した親子の事例を紹介し、
その進路選択の際の子どもの様子や、親の葛藤を参加者に聞いてもらうことからスタートしました。
進路を選択する際に、親の中に偏見があったことに気付き、支援学級は、能力がないから行く場所なのではなく、
その子に必要な力を身に付ける為の環境であることを、改めて感じたというAさん。
第三の大人(両親でも祖父母でもない大人、例えば先生)の存在が、大きく影響した事例とも言える・・・。
子どもにとってふさわしい環境が、普通学級なのか、支援学級なのか、支援学校なのか、その選択は非常に難しく、
「学校から提案されて進路を考えるものなのか・・・」という質問が出ました。
学校での様子そのものは、現場の先生に伺ってみないとわからないので、先生とのコミュニケーションはとても重要です。
大切なことは、今その環境に子どもが適応できているかどうかということでしょう。
そして、どの環境の中であっても、やはり、『自己肯定感』がキーワードになりそう・・・。
発達障害の子どもは特に、『叱る』以外の手立てを使いたいところです。
しかし、つい、叱ることが多くなってしまったり、日頃、心配なあまりに注意したりすることが、自己肯定感を低くして
しまうことに繋がることが多々あります。
親である自分自身の自己肯定感が低いことに気付いたり、自分の子育てに自信が持てなかったりすることが、
わが子の自己肯定感を下げているのではないかという発言がありました。
わが子が育てにくく、親からも躾が悪いと言われ、自分を責め続けたBさん。
発達障害という事実が明らかになることで、頑張り続けた自分から解放され、子育てが楽になれたと言われました。
問題が生じてはじめて気付くことがあり、それをきっかけに、子も親も、発達・成長できることがあります。
(ピンチがチャンス )
)
見た目や、親の価値観でほめたり、できる・できないにこだわるのではなく、何が良いのかを見極めながら、
努力や建設的な姿に声をかけることのできる親でありたいという発言もありました。
等身大の自分を見つめる作業は、子ども自身や子を見る親に思い込みがあるため難しいが、親ではない、子どものことを
真剣に見つめてくれる『第3の大人』、すなわち、情を極力廃して教育してくれたり、正しく判断してくれる人の存在
(学校の先生など)がとても大切であり、この第3の大人の存在こそが、将来を見通しての選択を迫られる時に、
大きな支えや道しるべとなり得るのかもしれない・・・。
*******************************
くさなぎ井戸端会は、どなたでも、いつからでも、お1人でも・・・自由に参加できる座談会です。
発達障害について、ご自分の子育てについて、先生やお母さん方とのコミュニケーションについて・・・
など、心配なこと、困っていること、迷っている事、解決の糸口を見つけたいこと・・・・など
多くの問題を、その人、個人の問題として取り上げるのではなく、
皆さんの共通の経験を通して、みんなの問題としてとりあげ、話し合っています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。