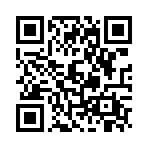2011年07月01日
「第37回くさなぎ井戸端会」ご報告

日時: 4/28(木)
テーマ: 「進級進学」フリートーク
参加人数:10名
4月は進級進学で子ども達の閑居に変化がある時期である。
そんな中で子どもや親がどのように過ごし、何を感じているのかを自由に話し合ってみた。
●子どもが入学して2日目に鼻血を出して帰ってくる。理由を聞くと「前の席の子が(わざと)転ばしてきた。
でもすぐに謝ってきたから許してあげた」と。
学校からはその事について特に連絡もなく、親の私のほうがびっくりしてしまったが、
本人が「別にいいから・・」と納得しているようにみえた。保育園の時は毎日の送迎で先生と話す機会があったが、
小学校に入り全くといっていい程、情報が入らない。
親としては今回の思わぬできごとに、先制パンチくらったように思ったが、子どもの成長を感じ取ることも出来た。
●小6の子が不登校になっている。一年生の終わり頃から学校に行きたがらなくなり最後は、
無理にでも引っ張って登校させることもあったが、理由を聞いても「いじめられるから・・・」と言うが、はっきりせず。
小4の2学期から行かないことも多くなり、5年の後半から不登校になり、現在に至る。親としても心配ではあるし、
年齢に不相応に暴れることがあった。
その後、病院で軽度発達障害があると診断されるが、支援を受けられるほどでもない状態でいる。
学校側にも何度か相談するが、取り合ってもらえず、市の子ども相談センターに相談する。
不登校の今は、週に一度、支援を受けている子どもと一緒の教室に通い、勉強している。
担任や学校に相談してもダメだと感じ、外部に相談することで救われた感じがあるが、
6年生なので、中学への進学も様々な角度から考えて、子どもにとってよい方法を見つけたい。
●小2の子。とてもゆっくりマイペースが心配で、つい言葉がけが多くなってしまう。
先生は「何度も繰り返し経験する事で、自分のものにしている」と言われるので、見守っていこうと思う。
けれど朝「学校に行きたくない」と言われると親も少しドキッとする。
親の敏感さが子どもに伝わり、子どもも反応していると思う。
●小4の子。小2の頃、数日間学校に行かないときがあった。
原因はいじめでもなく、親の私がしっかりして欲しいと思うが余りに細かく色々言い過ぎて、子どもが疲れて
(勇気がくじかれていた)いたように思う。
親の当たり前は子どもに当てはまるものではなく、その子のペースで成長しているのだと分かった。
●小5の子。友達との関係が上手に築けず「ふつうの女の子になりたい」と言う。
友達への声かけや接し方などを具体的にアドバイスをしてみると、「やってみる」と。
子どもも高学年になり、自分と他人の違いを感じてきている。
********************
子どもの年齢により、悩みや問題も変化してくる。
学年が上がるにつれて「不登校」なども増えてくるが、原因は本人に聞いても分からない。
けれど何か心がくじけてしまう事があり、学校に行けなくなってしまう。
ともすれば親は「学校に行けない」ことに過敏に反応し、行けなくなった原因を探り、何とか登校させようとすることが多い。
けれど親は学校に行けない子どもの心を認め、学校以外に行ける場所や、何なら出来るのか、好きなことは何か、
などその子どもがどう在りたいかを一緒に考えていくことも必要である。
そして、親の思う当たり前はそのまま子どもに通用するものではなく、親の思い込みや願いばかりを子どもに強要している事も
多いので、当たり前を具体的に表していくと分かりやすいと思う。
また、小学校から中学校への移行期は子ども本人の思春期とも重なり大変でもある。
小学校では段階を経て少しずつ手を離していくのに対し、中学校では、出来るのが前提でスタートするので、
「何で出来ない?」「やっておけよ!!」となり、子どもも混乱する。
移行期に向けて、子どもが主体性を持って何事にも取り組むことが出来る力をつけていくためにも、
日々「あなたはどう在りたいのか?」という視点を持って子どもと接していきたいと思う。
(S)