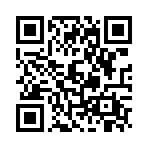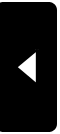2011年06月05日
「第36回くさなぎ井戸端会」参加者の声

参加者アンケートより、皆様の了解を得て、一部掲載させていただきます。
********************
お母様方の意見がきけて大変参考になりました。
一番印象に残ったのは、公平さの話題です。
連帯責任において本人が納得する不公平さの理由付けをする。
それは大変なことだと感じました。自分だったら、連帯責任というのはしたくないです。
しかし、お母様方の話をきき、ときにはしなければならないものではないかと思うようになりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
教師志望の学生<A.Y>
今日はさまざまなテーマでの皆さんの意見を聞けて、とても参考になりました。
「子どものことで悩んでいるのは私一人ではない!」とも感じ、なんだか安心したようなホットしたような
・・・。また参加させてください!
<H>
本日は参加させていただきまして、ありがとうございます。
実際に皆さんのお話を聞くことが出来、とてもうれしいです。
来年度、教育実習にもいくので、今回お聞きしたことを実践していきたいです。
本当にありがとうございました。又参加させてください。
教師志望の学生<H>
自分の親としてのスキルがまだまだだなぁと実感させられます。
理屈としてわかっていてもそれを実践できないところが子どもというより、
自分の成長が必要かと思いました。<M.I>
皆さん、カード等を通じて、先生とコミュニケーションをとっているんだなぁ・・・と思いました。
私はつい面倒くささが先に立ってしまって・・・。
これからは、あまり肩肘張らずに、気楽な気持ちで思いついたことを先生に伝えていけたら、と思います。
<N.A>
今日もありがとうございました。毎回勉強になります。
これから先生になる学生さんの意見を聞く機会はないので参考になりました。
4月からの小学校生活に向けて、また皆さんのお話を聞いていけたらいいなと思います。
<M.W>
保護者の方から見た子どもと、教師から見た子どもは違うんだなと感じました。
しかし、子どもたちをよくしようという気持ちは一緒で、みなさん熱心な方が多くとても感動しました。
清水区内の小学校でボランティアをやっていますし、来年度静岡市の教員になろうと思うので、
またお会いする機会があると思います。よろしくお願いします。
教師志望の学生<T.K>
本日はありがとうございました。
保護者の方々とお話しする機会は滅多にないので、参加できて大変うれしかったです。
来月も参加したいです。
先生になってからはなかなか参加できませんが、自分に子どもが生まれたり、育児休暇中には参加したい!
!と思いました。ママ教師を目指して頑張ります!!
教師志望の学生<Y.M>
今日は貴重なお話がたくさんお聞きできて良かったです。
温かい目で先生を見ていることを知りとてもうれしい気持ちになりました。
ありがとうございました。
<K.S>
発達障害について子どもがどう考えているのかをお話し頂いてとても参考になりました。
診断名がつく事、その選択については、未だに良かったかどうかは分からない・・・と聞き、
親の気持ちを思い知りました。
本当にみんな悩みながら前向きに過ごしているんだなと改めて思いました。
先生たちも保護者がどう感じるかはとても気になることなんだなと判りました。
<O>
2011年06月04日
「第36回くさなぎ井戸端会」ご報告②

<前回につづきます>
今回の井戸端会には、とても熱心な教師志望の学生さんがたくさんご参加下さり、
保護者(親)への質問や、保護者から教師への願いや普段はなかなか言えない本音なども出てきました。
学生さんからは、
・教師が信頼を得ていないような気がして・・・
教師としてもっとたくさんの知識を得たいと思いました!!
という、とてもうれしくてありがたい志や、
・来年度、新採で教壇に立ちますが、新採の教師に保護者としてどんなことを望みますか?
・教師にされて嫌なことは何ですか?
との問いに対して、
・新人の教師は若さゆえに、親からは頼りなく感じられることもあるが、
「若さと自分の強み」を生かして指導して欲しい。
・子どもを不公平に扱う、笑顔やユーモアがない、年齢にそぐわない責任を子どもに強いるのは
やめて欲しい...。
また、中学校の子どもの担任は、比較的若くて、気さくで話しやすい反面、
子どもからなめられているようにも感じる。それでいいのかと疑問に思うこともあるし、
教師として、大人としてもっと毅然とした態度や威厳を持つのことも必要なのでは?
という意見が出ました。
立場が違えば、考え方や見方の違いは当然ありますが、両者共に「子どもを教育する」
という目的は同じなので、お互いに信頼関係を築くことが何より必要なのでしょう。
けれど実際にはなかなか教師と保護者が話をする機会(時間)がありません。
そこで、コミュニケーションのとり方のひとつに、子供の宿題で使われる音読カードの保護者サイン欄に
コメントを書くというのがありました。
相談するという程ではないけれど、気になることや、子どもの様子などを書き、
それに対して返事があることで、お互いの信頼が増していくのだと思います。
また教師からもクラス便りなどで情報を発信することで、保護者の信頼を得ることがあります。
(クラス便りがなくても直接子どもとの会話で教師や学校の様子を知るのが理想ですが...。)
本音も飛び出す意見交換で、学生さん達からは、思っている以上に保護者の方が教師に対して
暖かい気持ちでいてくれるのがわかったという感想があり、
コミュニケーションの大切さを再確認しました。
(一歩間違えれば、モンスターズペアレントになりかねないので、それには注意が必要ですが... 。)
。)
2011年06月03日
「第36回くさなぎ井戸端会」ご報告

日時:2/24(木)
テーマ:無し フリートーク
参加人数:18名(学生6名)
今回のくさなぎ井戸端会も、前回同様、椅子にテーブルの会議室で行われました。
あえてテーマを決めず、過去のアンケートの中で皆様から挙げられていた、
『取り上げて欲しいテーマ』をホワイトボードに書き上げ、
参考までに参加者の皆さんにそれを御覧いただき、書かれた内容に関連することでも
そうでないことでも、自由にお話いただくような形で、会をスタートしました。
まず最初に投げかけられたことは、
「特性と障害はどう違うの? どこで線を引くのだろう・・・
どこで線を引くのだろう・・・ 」でした。
」でした。
・社会で生きていく中で、その特性があることにより生きづらくなった時、
特性が障害となるという見方をするのかな・・・
・生きやすくなる為に、手立てを必要とするとき、障害となるのかな・・・
・発達障害ではなく、発達デコボコというネーミングの方がふさわしいという話も聞いたことがあるけど
・・・
・障害があるかないかの線引きそのものは主に医師がすることになるよね・・・。
その目的は、差別区別ではなく、療育や支援を具体的にどのようにしていくかを見極める為なんだよね・・・
・「僕は障害者なの? 」と子供に聞かれたことがあって・・・。
」と子供に聞かれたことがあって・・・。
障害者なのか、そうでないのかという白黒つけるような答え方はしなかったな・・・。
子供自身が「障害者」をどう捉えているのかを聴いて、そう考えている子供の気持ちを受け止めるよう
にしたよ・・・
そして、このようなディスカッションからさらに、
・やっぱり親が早期に気づいて受け入れることが大切なのかな・・・
・早いうちに発見できると、具体的な手立てを早期に得られるし、
集団生活でのスキルを身につけるには、小さいうちからの方が良いのは明らかだけど、
早期に受け入れるのが親の責任!みたいになってしまうと、それは厳しいかな・・・
障害じゃないと思いたい親の心情もあるしね・・・
・うちの子は小学校入学と同時に障害があるものとして受け入れて、支援級を選択してきたけど、
それが本当に子供にとって良いことなのかどうかはわからないし、親としては全く後悔はしていないし、
むしろたくさん得るものがあると信じているし確信しているけど、
子供がそれをどう受け止めるかは子ども自身になるからね・・・
・先生や学校の理解が得られないと感じたら、専門の相談機関に行くのもいいかも...。

といった、すぐには答えが出ないけど、
皆さんと一緒に考えていくことそのものがとても大切と思われる貴重な意見がたくさん交換されました。


<つづく>
2011年06月02日
走っど~!! の 今後の予定



マラソンデビュー2年目。
今年は、少~し遠出で
ガッツリ走ります。









6/12
第10回グリーンチャリティーリレーマラソンin東京ゆめのしま
12時間走(個人)・・・・夜間走
6/19
第6回乗鞍天空マラソン・ 30km
7/17
第9回小布施見にマラソン・ハーフマラソン
7/30
2011フライデー ナイト・リレーマラソン in 国立競技場 夏大会
12時間リレー 1人チーム(個人参加)・・・・夜間走
8/21
第31回山日YBS富士吉田火祭りロードレース
ハーフ(21.0975km) マラソン
9/4
朝霧高原トレイルランニングレース
ロング約34km
9/19
第6回佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足206km ←《2011minoメインイベント》
10/30
第3回しまだ大井川マラソンinリバティ・フルマラソン
12/11
奈良マラソン2011・フルマラソン
<抽選結果待ち>
10/30 大阪マラソン・フルマラソン(再抽選結果待ち)
11/20 神戸マラソン・フルマラソン
まだ、エントリーの開始されていない素晴らしい大会がいくつかありますので
今から楽しみです。
夢は《スパルタスロン》へ!!!!

「めちゃ運動嫌いの専業主婦・一念発起・スパルタスロンへの道」


どうぞお楽しみに!!!!!
ガははっははははははは、、、、ひ、、、、
2011年06月01日
ストレス反応

人間は、いつもとは違う、
大変ショックな出来事に遭遇した時に
あらゆる反応を示すものです。
しかし、この反応は誰にでもある、
当たり前な反応ですので
心配はありません。
時期が来れば、自然と収まって来るものなのです。
今回の出来事でminoに現れたストレス反応は
フラッシュバックで
4年前に味わった激しい怒りや不安感、寂しさ、絶望感など
情緒不安定な感情が鮮やかに蘇ってきてしまいました。

不意に涙があふれてきたり
脱力感やイライラ、やる気が出ない、落ち込み、、、、
などの様々なストレス反応を感じています。
ウルトラマラソンで100km走ったところで
疲れて寝込んでしまうような事はありませんが、
今回の出来事によるストレス反応で
ダウンしてしまいました。
1日、休みました。
当の太郎吉はというと、
「しばらく考えがまとまらないよ。 何だか力が入らない
何だか力が入らない 。」
。」
と落ち込んでいるようだったり
「ふざけんな! 何てことしたんだ!俺はどうなるんだ!
何てことしたんだ!俺はどうなるんだ! 」
」
と怒りをどこにぶちまけていいかわからない様子。
少しぼんやりしたり、イライラして人に絡んできたり、
「かあさん、かあさん、、、、」と用もないのに連呼したり(子どもがえり )
)
少し落ち着いてきた反抗期の様相も
又、ぶり反しいています。
********
ストレス反応が収まるポイントは
①安心できる、気持ちが和む時間や場所があると、心が楽になり元気が戻ってきます。
②家族や友だちや先生と過ごすときに<絆>を感じられるとよい。
遊びや行事を通じて「一人ぼっちではない」と感じること。
③泣く、笑う、怒る・・・などの感情を我慢せずに素直に表現すること。
また、親は、子どものその気持ちを素直に受け止めてあげること。
先ずは、私自身のストレス反応を軽くするために
積極的に走っています。 (いつもか・・・)
(いつもか・・・)
先日は、4時間30分走ってきました。
こうすることで、子どものストレス反応に
上手く対応できるのです。