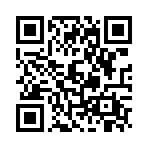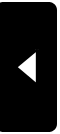2009年05月20日
“ある・なる・する”の親

あるお母さんから。。。。
子どもの抱える問題を子ども自身が乗り越えられるように、勇気づけ、ここぞと言うときに
ポンと背中を押す事で、子どもが自分の力で一歩踏み出せたというお話から
・・・
こんな嬉しいご報告をいただきました。
【晴れ晴れとした気持ちで、私も心の底から「よく頑張った」と子どもをほめることができました。
今までこんなに心底ほめたことがなかったんじゃないか、と思うくらい・・・本当にうれしかったです。
これからは、今まで気がつかなかった小さなことも素直にほめてあげられるような気がします。
私にとっても この経験でどんどん成長できればいいな・・・ 】】】】】
】】】】】
親子共に素晴らしい経験が出来て良かったですね。
*************
「芸術家」と呼ばれる人の中で、才能が生まれ持って“ある”という人がいます。
しかし、多くの人は、努力しながら「芸術家」に“なる”のです。
そして、人生において「芸術家」を“する”人となっていくのです。
ところが、子どもを持って、最初から「親」で”ある”人はいないのです。
子育てを通して、成功や失敗体験を少しずつ積み重ね「親」に“なり”ながら、
「親」を“する”自信を付いていく のですね。
*************
minoも我が事のように、とっても嬉しくて、勇気をいただきました。
ありがとうございました。
2009年05月19日
感情を利用する?

STEP第2章では。。。。
「皆さんは感情を利用することがありますか? 」
」
「どのように感情を利用するでしょうか? 」
」
。。。。と、考えてきました。
・相手が思い通りに動かないときに怒ることでコントロールしようとする。
・解かってもらいたいのにわかってもらえないと思うときイライラしてあたる。
・同情、哀れみが欲しいときに悲しむ、泣く。
・自分の権威を示したいとき怒りをあらわにする。
・心配してもらいたいときに無気力な態度を示す。落ち込みを表現する。
などなど。
私達は、感情を利用することで、相手に何かをして欲しいとコントロールしたり、
相手に関心を持ってもらいたい、承認されたい。。。。と願っているようです。
子ども達も、感情をぶつけてきます。
そのようなときに、子どものぶつけて来る感情(怒り、落ち込み、不安、憐れみ、イライラ、など)
に巻き込まれ、何らかの感情をぶつけ返す事で、子どもの行動をさらに強化してしまいます。
このような場合は、親は子どもの感情に乗らないことが大事です。

2009年05月19日
“中庸の軸”

中庸とは?
****************
考え方・行動などが一つの立場に偏らず中正であること。
過不足がなく、極端に走らないこと。また、そのさま。
古来、洋の東西を問わず、重要な人間の徳目の一とされた。中道。
「―を得る」
****************
つまり、「偏らない。平衡を保つ。」という事が大事なのかと思います。
minoは「物事が、どうも上手く行かないな~???」と感じるときに
「自分は今どこに立っているのか?」と考える事があります 。
。
それは、自ずと「偏らない。平衡を保つ。」という“軸”で物事を判断しようと
しているときであり、minoはこれを“中庸の軸”と名づけました。
“中庸の軸”を得ると自分が楽になり、心が落ち着きます。
人を良し悪しで判断し非難することがなくなり
物事を赦せる大らかさが備わります。
是非、みなさんの“中庸の軸”を探してみてください。


2009年05月18日
メガネです。

ア~、太郎吉もセシリアも、とうとうメガネを掛けることになりました。。。。
眼科に行き、Dr.が「メガネをつけることにしましょう。」と言うと、セシリアは大喜び!!
それを見たDr.が、、、、
Dr. 「お母さん、良かったですね。普通は、メガネは嫌だといって説得するのが大変なのに。
あの子は大喜びだ。。。 」
」
mino 「はあ、小さいころからメガネが好きで、あの子にとってみたらファッションなんです。。。。
表現なんです。。。幼稚園の頃は、水中メガネをつけて歩いていましたから。。。。 」
」
Dr. 「・・・・変わってます・・・ね・・・・ 」
」
太郎吉は太郎吉で、掛けたくないのに掛ける事になってしまったという興奮と混乱のあまり、、、、
「えっと~、これって、遺伝ですか?」「ぼくは、この先どうなりますか?」
「ぼくにはメガネが似合いますか?」「あ~、こんなはずじゃなかった。。。 」
「ア~、眼が回る・・・・」
と、わけのわからないトンチンカンなことを連発して(眼が回りそうなのは母ちゃんだよ・・・ ・)
・)
mino 「お願いだから、落ち着いて、黙っておきなさい。。。 」というと
」というと
Dr. 「・・・・いずれにしても・・・・・・ 」
」
mino 「はい。いずれにしても、変わってるんです。 」
」
Dr. 「あはは、 イヤイヤ、
イヤイヤ、 お母さん。そうじゃなくて、
お母さん。そうじゃなくて、 いずれにしてもメガネの処方箋を
いずれにしてもメガネの処方箋を
書いておきます。」
mino 「ああ、 は~。。。はい
は~。。。はい 。」(。。。と、なんだかこっちもトンチンカンになってしまい
。」(。。。と、なんだかこっちもトンチンカンになってしまい 。。。)
。。。)
という事で、一番混乱し、ガッカリしてしまったのは、minoでしたよ。
やっぱり体質は似るんだな~。
遺伝させちまったな~。
minoも太郎衛門も極度の近眼ですから。。。。
セシリアは、「明日から黒板が良く見える!!うれしい!!
世界が細かく良く見える。感激!! 」
」
と喜んでいますから、やっぱりこれでよかったのだと、少し“ガッカリ”が回復しました。
そして、太郎吉も、「湯上りのメガネは、いい男過ぎる!! 」と鏡を覗き込みながら、、、、
」と鏡を覗き込みながら、、、、
相変わらずトンチンカンですが
セシリアや太郎吉の明るさに、こうしていつも救われます。

2009年05月18日
5.18キラッ!!咲いた!

5.14『見切り品コーナー』の“しょぼけたオーラ”の葱坊主。。。。
毎日、水やりしながら勇気づけていました。

「あなたが来てから、楽しみが増えたよ!」」
「しょぼける事はないんだよ。きっときれいに花咲くよ!!」
「信じているよ。大丈夫だよ。。。。」
「“矢切の渡し゛(細川たかし)ならぬ“値切りの私”(mino)は、
あなたと出会えてよかったよ!」
・・・・・
などと話しかけていましたら。
咲きましたよ~!
葱坊主にまで“勇気づけ”なんて、何て暇????、、、、
って呆れられそうですが、
勇気づけは、暇がなくともい出来るのです!!
あらゆるものへの“感謝”と“勇気づけ”は、自分への勇気づけとなって返ってくるのですよ。

お試しあれ!!
今日のキラリは、
葱坊主への感謝状!! 
「葱坊主へ!!
生活を豊かにしてくれて、ありがとう。
minoより」
2009年05月17日
そりゃ“気合”だよ!!

セシリア 「母ちゃんは何で、前の晩遅くまで起きて勉強したり、家事をやったりしていて、
遅く寝ることになっても、次の日には、きちんと早く起きれるの?」
mino 「う~ん、そりゃ、“気合”だね!!」
セ 「“気合”か・・・・・?」
mi 「母ちゃんが“気合”入れなきゃ~、あなた達、毎朝ご飯抜きで登校することに
なるじゃな~い?それってどうよ? 」
」
セ 「そりゃ、困るよな・・・・ 」
」
mi 「んでしょ~?!!だから母ちゃんは、皆のために“気合を入れて寝る”んだよ!! 」
」
セ 「あれ?“気合を入れて起きる”んじゃないの?」
mi 「甘い、甘い!!“気合を入れて起きる”ためには、 『明日も起きるぞ~っ!!』って
“気合を入れて寝る”んだよ。」
セ 「は、はあ~、なるほど。。。 だから、あたしは気合を入れて起きようとしても
だから、あたしは気合を入れて起きようとしても
起きられないのか。」
mi 「なははは。。。。
それから、もう一つ。“気合”は自分のために入れるときもあるけれど、
人のために“気合”を入れるってことも大事なんだよ。」
セ 「『試合に勝つぞ~!!』とか『100点取って見せるど~!!』とかってのは、
自分の為に気合入れているけど、母ちゃんは、私たちのために気合を
入れてくれているんだね。。。」
mi 「んま、そういうこっちゃね。えへん!! 」
」
セ 「・・・んなら、あたしも、母ちゃんの為に気合を入れたことがあるよ。」
mi 「なんだい?そりゃ~?? 」
」
セ 「おにぎりさ。。。。母ちゃんのおにぎりは、時々、塩じゃなくて砂糖なんだよ。
“気合”入れて食べたら美味しく感じたから、言わないでおいてた。。。。 」
」
mi 「ヌゲ~~~~ッ!!そ、そりゃ、“気合”い入れないで言っておくれよ~・・・。

とほほほ、、、、
すまんかったな~。。。。。
 」
」
セ 「気合って入れるの難しいね。」
mi 「ほんとうだね。。。。
人のために“気合”を入れるときには“思いやり”が含まれるんだって、
セシリアから教わったよ。ありがとう。。。 」
」
こうして、子どもたちはいつもminoの良き先生なんです。
感謝しいてます。
2009年05月17日
何よりのチャンス!!

セミナーを受講され実践されているお母さんより、こんな嬉しいメールを頂きました。
了解を得て、ここに、ご紹介させていただきます。
**************
・・・・最近、気づいたこと、、、、
『主体的に取り組む』ということの大切さです。
『やらせよう。』ではなくて、「本人がやりたい」と望むことが、
何よりのチャンスなんだ ということに気づいたといいますか・・・。
STEPを始める前は、
「子どもには、親が主導権を握り支配的に、何事もやらせれば、何とかなるものだ。 」
」
という考えでしたから。
**************
そういえば。。。。
大昔・・・6年生の時、学校の恒例行事で、ペアになった(本音は、組まされた・・・)
小学生1年生を連れて歓迎潮干狩りに行かされました。
私は貝をドッサリ獲りたいのに、
勝手にどこかへ行ってしまう相手に腹が立ち、
その気持ちが知れず、思い通りにならない事実に
「ガキは嫌いや! 」と思いました。
」と思いました。
その後、出産するまで
「子どもは嫌い! 」と言い続けていました。
」と言い続けていました。
しかし、今なら、相手が『何をしたいのかな?』と、まずは尋ねてみたくなるのになー
と思いました。
**************
いかがでしょうか?
『主体的に取り組む』ということの大切さに気づいたというお話です。
実は、今、学校現場で、児童生徒の中に『主体的に取り組む』という事の出来ない子どもが
増えているといわれています。
・・・いわゆる『指示待ちっ子』です。
子ども自身が「やりたい!!」と感じ『主体的に取り組む』ということが出来て初めて、
子ども自身が力をつけながら伸びていくチャンスとなるのですね。
親が主導権を握り、何事もやらせてばかりでは、
「自分で考えて取り組むという経験の元に、主体性を育てる」という事ができてこないのですね。
**************
また、このお母さんの「相手が『何をしたいのかな?』と、まず、尋ねてみたくなる」。。。。
というのは、まさに相手を思いやる気持ちですね。
『私がどう思うか!!』ではなく『この子(人)は、どう感じているのか?』
と思いやれる態度が、子どもを勇気づけ、主体性やチャンスを育んでいく事に
繋がっていくと思います。
嬉しいご報告をありがとうございました。
2009年05月16日
魚より肉!!

子どもの魚離れに歯止めが掛からず、摂取量は過去10年で2割以上減少したと
いいます。
「は~。。。やっぱり家だけではなかったのか!!」
と、安心するやら確信するやら。。。
実は、我が家でも子どもたちは刺身以外の魚をあまり好んで食べようとしません。
毎回、刺身というわけにも行かず。。。
摂取量の減少が健全な発育に影響を及ぼしかねないと知り、何とかしたいと
頑張っては見るものの、、、、
『何だ~魚か。。。 明日は肉ね~!!
明日は肉ね~!! 』と言われるとガッカリしてしまいます。
』と言われるとガッカリしてしまいます。
今の子は箸の使い方が下手だと言われていますが、この不器用さが
「魚の食べずらさ=魚を食べるのが面倒くさい」となり“魚嫌い”に拍車を掛けているように思えてなりません。
「肉はいいけど魚はいやだ!!」ではなく
「肉もいいけど魚もいいな!! 」と思ってもらえるような工夫に、毎度、四苦八苦していま~す。。。
」と思ってもらえるような工夫に、毎度、四苦八苦していま~す。。。

2009年05月16日
あ~、、急がなきゃ!!

昨夜のことです。。。。。
いつもは『んま~いっか~!?』のセシリアが、珍しく
『あッ~、急がなきゃ!! 急がなきゃ!!
急がなきゃ!! 』とお風呂に入りながら慌てています。
』とお風呂に入りながら慌てています。
mino 『何をそんなに急いでいるの?』
セシリア『だって、昨日、早く寝たら身体がスキッとして気持ちよかったから
今日も早く寝たいんだ! 』
』
mino 『ゲ~ッ??金曜日なのに~?いつもは、“花の金曜日”は“だらり金曜日”だからって
「だらりとしながら好きなだけ起きているのが、リラックスすることが身体休めだ。」って
言ってたのに???』
セシリア『確かに そういう時も必要だよ。だけれど、今は身体が睡眠を求めてるんだ!
“自己管理”の時なんだ! 』
』
mino 『え~?すご~い!!かっこいい!! 身体の要求がわかるようになったんだね。
身体の要求がわかるようになったんだね。
じゃ~、慌てないで、急ごうね!! 』
』
セシリア『何だよ、それ? 』
』
こうして珍しく早寝したセシリアは、minoに“花の金曜日”をプレゼントしてくれました。
お陰さまで、昨夜は、今日と明日の出張の準備が充分出来ましたとさ!!
しかし、、、、
子どもって、“気持ちいいこと”や“新しいこと”を覚えると、それをやってみたくなる
ものなのですね。
さて、minoはこれから三島へGO!!
セシリアに負けないように“気持ちいいこと”や“新しいこと”を発見しに行ってきま~っス!!

後は頼んだよ~!!!。。。。かははは。。。
2009年05月15日
自己管理もプロの仕事

セシリアは、立派なバスケットボールの選手を目指し、日々、精進しています 。
。
セシリアは、ここのところ、読みたい本との出会いが多く、読書時間が伸びており、また、
運動会が近いので、その練習も重なり、少々寝不足・お疲れ気味 。。。
。。。
自分でも身体や頭が、スカッ!とパッ!としないのが、わかって来ているようでした。
昨晩は、『あ~、こりゃ眠い。。。寝るわ。。。』といって、大好きなバスケットボールのDVDもそこそこに、
自分から早く休みました。
(「早く寝なさい!!」と口をすっぱく言わなくとも、自分で必要なら寝るのです!!)
今朝、起きて来てスッキリした顔で「おはよう!!
 」といい
」といい
「やっぱり身体は正直だ!!今日はスッキリとして、気分がいいよ!!身体も軽い!! 」といいました。
」といいました。
mino 「そう~、それは、よかったね~。昨日早く休んだお陰かな?
それを“自己管理”って言うんだよ。」
セシリア「“自己管理”?」
mino 「そう!!プロの選手はね、“自己管理”っていって、日頃から自分の体調を万全に保つのも
仕事のうちなんだよ。
セシリアも休めば身体が楽になるってこと解かったでしょ?
だから、『疲れたな~』と思ったら、休むのも仕事のうちなんだよ 。」
。」
セシリア「ふ~ん。 “やりたいこと”・“しておきたいこと”を我慢しても、休むことを優先しなくちゃ
ならないことがあるのか。。。 」
」
mino 「そうだね!!プロの選手には自分の身体を“自己管理”する責任があるのだね。」
セシリア「そうか~。。。じゃ~、、、プロになるには、、、、
音感・リズムが良くなりたいから、“ピアノ”。
サインをうまく書きたいから、“書道”。
身体が大きくなりたいから、“残さず食べる”。
それに“毎日の練習”と“自己管理”か~。。。。
うん、行けそうな気がする~ 。。。」
。。。」
こうして気分良く、機嫌よく、今日も元気に登校して行きました。
**********
さて、この事例から何が言いたいのかと言うと。。。
親は、只、口で「自己管理しなさい。」と子どもに言ってみても子どもは“自己管理”の何たるかを知りません。
そこで、初めは、“自己管理”の何たるかを教える必要があるのです。
(親は、教えなくともできると思いこんでいることが多いようです。)
“自己管理”とはどういうもので、どう感じたか。。。と、子どもの経験を通して確認しながら、
それをする必要性やその意味を繰り返し教えていきます。
すると子どもは、自分で考えて、必要に応じて、それができるようになっていくのです。
そして、親は、子どもが『自己管理できていない!!』と叱るのではなく、自己管理が出来ているときに
『自分のことを大切にできるあなたは、偉いと思うよ。 』と褒めて、認めて勇気づけてあげるのです。
』と褒めて、認めて勇気づけてあげるのです。
**********
子どもは、大人の姿を見たり、自分の経験を通して、学んでいきます。
そこをどう、手助けしていけるかが子育ての楽しみでもあるのです。
2009年05月15日
5.15キラッ!!乾杯
これっ!! ↑
どうどうと昼真っから飲めるビール。
ノンアルコールなのに“なんちゃってビール”な感じがしないのよ。
『(ゴックン、ゴックン)・・・・っくうわ~ッ!!!』って
ちゃんと「っくうわ~ッ」ができるし、、、、
minoにとってのビールは、「気分転換・のどの渇きに!!!」って感じで
お気楽に飲みたいもので、
「それでは参りましょう!!!」と本気で酔っ払いたいときには、
日本酒・焼酎・ブランディ・・・なのです!!
はい。
今日のキラリは、
キッチンドリンカーにならない“主婦の味方”?
“ノンアルコール ビール”
2009年05月14日
ママpika学習会にて

本日は、第16回『ママpika学習会』,,,,
皆さんご参加ありがとうございました。
お母さま方と共に、3人の現役大学生がご参加くださいました。
将来、教員を目指す学生さんと共に『教育、子育て、しつけ、学校と保護者、
特別支援教育など。。。』についてトークしてまいりました。
平成19年4月から特別支援教育はスタートし、現場の先生方につきましては
講習・研修で学ばれる機会も増えてきたようですが、しかし、これから新たに
教員として現場に立つであろう学生さんにおいては、大学のカリキュラムの中に
『特別支援教育』についての学習はないのだという事でした。
日本の教育現場において、これから先生となる人に必要であると思われる知識や
スキルの習得は、必ずしも大学では学べないのだ!!。。。。
という現実を知り、「教員になったはいいが、やめて行く若い人も多い。」ということにうなずける思いがしました。
更なる特別支援教育の推進が、なされていく為には、“大学としてのあり方”が見直されるとき
に来ているのではないでしょうか?
2009年05月14日
5.14キラッ!!葱坊主
スーパーの『見切り品コーナー』ってありますよね?
いつも、そこを通ると、あのコーナーの食材たちが、売れ残ってしまった結果、勝手に見切られて
何だか“しょぼけたオーラ”がしょ、ぼんしょぼん とminoを誘うのであります。
とminoを誘うのであります。
昨日、見つけた『見切られしょぼりん』は、長ネギ。。。。
買って帰って、、、、冷蔵庫にお入りいただこうとすると、、、、
ん????
ありゃ????
何やら付いてる。。。
怪しいものが。。。。
よく見るとそこにあるのは“葱坊主”。。。。
エッ???
だからなの???
見切られちゃったのは。。。。
今回の“しょぼけたオーラ”は、“あなた”だったのね。。。。

記念に写真を撮りました。
今日のキラリは、
“しょぼけたオーラ”の
“葱坊主”。。。。
しばらく、花瓶に生けておきます。
2009年05月13日
『ネエ。どう思う?』

セシリアが、太郎吉相手に、こんな話をしていました。
『お兄ちゃん、参観会でね、いろんなタイプの先生がいるんだよ。・・・・
・お母さんたちが来る日も、普通の授業のときも、変わらず丁寧な字を書く先生 。
。
・お母さんたちが来た日だけ、見違えるように丁寧な字を書く先生 。
。
・日頃から、誤字脱字が多くって“止め・跳ね・はらい”などお構いなしなんだけど、
お母さんたちが見ている前だとちゃんと書ける先生 。
。
。。。ンネエ~。。。これってどうよ???お兄ちゃん???』
すると太郎吉は・・・
『ふ~ん。何だか、人間出ちゃうよな~ 。』
。』
セシリア・・・
『誰が居ようと、態度の変わらない先生は、信用できる先生だと思う。

私は そんな先生が好き!! 』
』
くは~。。。相変わらずの観察眼。。。
先生、ご注意して下さいね。
子どもたちは観ています!!
ありのままの、いつも通りの先生で良いんだと思いますよ。
2009年05月13日
人生楽し!自分好き!②

考えてみると、これまで太郎吉が、問題を抱えていると感じたときも“共感”はしてきたけど“同情”はしなかったのです。
ことあるごとに、太郎吉と共に感じながら(悔しいね。嬉しいね。苦しいね。気持ちいいね。辛いね。など)
前向きに一緒に考えてきましたが、
「可愛そうに。この子は上手く出来ない子なのだから、私がどうにかしてあげなくちゃ。。。」と同情した事はありません。
そして、
●「人間は一人では生きていけない、“社会的動物”って言われるんだよ。
だから、あなたが、お友だちや人との関係づくり(コミュニケーション)が難しい・苦手と感じることが
あるのなら、それは、あなたが長い人生の中で、自分で考えて解決していく課題なんだね。
逃げることができない問題なんだね。 」
」
●「そうありたいと願い努力をすれば、そうなれる可能性があるのが人間なんだよね 。」
。」
●「あなたの考えて選択したことは、母ちゃんも応援するから乗り越えるんだよ。きっと太郎吉にはできると信じているよ。 」
」
●「太郎吉が“自分自身”を好きになれる人生を生きてほしいんだ。
そうするにはどうしたらいいかを困難なときほど考えて欲しいんだよ。 」
」
などと太郎吉の心に寄り添いながら勇気づけてきたつもりです。
“共感”は、彼を認め、励まし、勇気づけることになるけれど、
“同情”は「ダメな子。出来ない子。」とレッテルを貼ってしまい結果的に
子どもの自己肯定感(自分を好き・これでいいと思える気持ち)を奪ってしまうのだと考えます。
自分で考え、選択して、拓いて来た人生を『楽しい!!』と思え、そんな自分を『大好き!!』
と言い切れる彼は、自尊感情(自分は尊い大事なもの。大好き。と思える気持ち。)が育ってきた結果だと思いました。

そんな太郎吉をminoは、大好きです!!!!!
minoの子育ての目標は
『自尊感情を育む関わり方!!』であり、
これを“勇気づけ” といいます。
といいます。
2009年05月12日
5.12キラッ!!美容院

日頃から
“思い煩うことなく”
“健やかに”
“笑顔よろしく”
“気持ちよく”
生活するのも
こりゃ、『自己責任』だと思うわけです。・・・
そんなこんなで、久しぶりに美容院に行って来ました。
。。。。。1年ぶりくらい。。。。
「ゲ~ッ???
1年間どうしてた???」
って・・・・?
自分でカットしたり、巻いたり、染めたりしてました。。。。
(mino元美容師です。。。 )
)
でもとうとう“自己責任”が果たせなくなりそうだったので美容院のプロにやってもらいましたよ。
これで又しばらく、気持ちよく生活するという『自己責任』が果たせそうです。
クアハッハッハ。。。
皆さんは、『自己責任』を果たす為にどのようなことをしていますか?
ショッピング? 映画? ランチ? 飲み会? 旅行? スポーツ?・・・
今日のキラリは
気持ちをキラリ!!
美容院で『自己責任』

2009年05月12日
人生楽し!自分好き!①

太郎吉は6年生。
太郎吉とminoの合言葉は、
【ぼく思春期前。母ちゃん更年期前。共に乗り越えようぜ~!!ベイビ~!! 】です。
】です。
頼もしくなりました。逞しくなりました。
そんな太郎吉に改めて聞いてみました。
『あなたにとって“人生”ってどんな感じなものなん?』
すると、迷わず即答してくれました。・・・
「“人生”とは様々な“選択”の中から生まれるものなんだ。
その道の分岐点でどちらに進もうか、考えながら自分で選び取ってきた。
自分で生きている人生なのだから苦しくも楽しいものだよ。 」
」
といい切ります。
(mino・・・す、すっごい!! 結構考えてる!!)
結構考えてる!!)
さらに、
『では、あなたは自分のことをどう思う?好きかしら?』
すると、
『大好きだよ!!自分のことを大好きなんてナルシストだと思われるかもしれないけど、
そうじゃなくて、こんな自分でもいいと思えるし、自分が好きなんだ。 』
』
minoは、
『自分のことを好きと言い切れる太郎吉はすごいと思うよ!!
母ちゃんが、あなたの頃は、自分を“好き”と赦して上げれなかった。母ちゃんは安心した。
更にあなたを信頼していける。嬉しいよ!! 』
』
といいました。
考えてみると、これまで太郎吉が、問題を抱えていると感じたときも“共感”はしてきたけど“同情”はしなかったのです。
***** つづく ****
2009年05月11日
“心配”は“信頼”に!!

太郎吉は、幼い頃から人と交わって遊ぶということが少なく傍観遊び(他の子の遊んでいる様子を
観て楽しんでいることが遊びとなっている様。)を好んでする子どもでした。
言葉が出るのも遅く、コミュニケーションは活発ではありませんでした。
幼稚園の入園式の日のこと。
太郎吉は第1子です。親も子どもも初めての社会化への第一歩でした。
観るもの、聴くことが初めての世界で親子して緊張していました。
その日は、年長さんが太郎吉たち新入生のお世話をしてくれていました。
そこで、心配していたことが起こりました。
太郎吉の担当してくれた年長さんが
「おばさん、この子は口が利けないの?何を聴いてもい答えないよ。僕困っちゃうよ。。。」
と言うのです。
子どもは素直です。直球で聴いてきます。
minoは、心臓が痛くなるほどショックでした。想定内でもショックでした。
この先の幼稚園生活を思うと心配でしかたありませんでした。
心配を笑顔に変えて答えました。
「この子は、元々、静かな子なのだけど、今日はかなり緊張しているみたいでね。
ごめんなさいね。心配してくれてありがとう。
慣れたら、少しお返事ができるようになると思うから、大丈夫よ。
このままお世話、お願いしますね。」と答えました。
こうして、太郎吉の集団生活が始まりました。
心配で心配でたまらなかったあの頃は、太郎吉を信頼できていなかったのかもしれません。
その太郎吉も、今はもう6年生。
立派に大きく成長しました。
小学生になってもコミュニケーションの不器用さで、お友だちを作るのに苦労したり、
悲しい思い、悔しい思いを繰り返し、時に、殴り合いのケンカになったり、
あるいは仲間と思っていた子ども達から省かれたりすることもあったようですが、
その頃にはminoの太郎吉への“心配”は“信頼”に変わっていました。
「この子だったら大丈夫!!自分で乗り越えて行ける力を持っている!!」と
思えるようになっていました。
minoも、子どもと共に成長したんだと思いました。
太郎吉は、今は信頼し合える友人に囲まれ、輝きながら彼らしい生活を送っています。
こうして、子どもの成長と共に、minoの子どもへの思いも“心配”より“信頼”の方がず~っと大きくなったと実感しています。
2009年05月11日
5.11キラッ!!お手紙

昨日は、母の日でしたね。
セシリアは、手紙を書いてくれました。
「お か
か あ
あ さ
さ ん
ん へ
へ
しあいのときに、おむすび、はい車、しあいでのおうえん、
いろいろなことをしてくれてありがとう。
今日は、しあいで、シュートを一本きめたいと思います。
がんばります。
おうえんよろしくおねがいします。
 セシリアより」
セシリアより」
本当は、朝、試合に行く前に渡そうと思って書いてくれたそうなのですが、
そこは、《うっかり・しっかり・ま、いっか~》のセシリアさん。
夜寝る前に、手渡してくれました。
念願のプレゼント“シュ~ト・一本!!”は、残念ながらありませんでしたが
それでも、あの気合の入った動きが、minoには、素晴らしいプレゼントでした。

改めて、日頃の感謝を言葉や態度で表現するのが、母の日や父の日などのイベントです。
イベントだとわかっていてもうれしいものです。
お手紙は、minoの活力、明日への希望という“宝物”となりました。
今日のキラリは、
うれしくて、心も瞳も思わずキラリ・・・
“感謝のお手紙”
2009年05月10日
3つの“はなす”

子ども(相手)が問題を抱えて相談してくる場合に、解決してあげたくなったり、話を聴きながら
アドバイスを考えたりしてしまうことがありませんか?
実は、この「解決してあげよう!」と思う気持ちが“聞き上手の邪魔”となってしまうようです。
子ども(相手)が相談してくる場合に、アドバイスや解決策を求めて相談してくるとばかりは言い切れません。
相談する・話す・・・・という行為は、
【悲しい気持ちや悔しい気持ちを「話す」ことで、悲しみや怒りを身体から「離す」
ことができ、それはマイナスの感情を解き「放す」ことに繋がる。】
このように3つの“はなす”を含むのです。
話を聴くときに
「相手は、アドバイスを求めて話して来ているのか? 」
」
「3つの“はなす”をしに来ているのか? 」
」
「私は、話を聴きながら、相手の思いをしっかり受け止められているか? 」
」
と自問してみましょう。