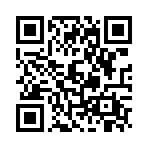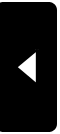2009年03月09日
苦手な面は”工夫して”

【今回のご相談】
家族と囲む楽しい夕食。しかし、いつも食事時間を過ぎてもS君だけはだらだらとしてなかなか食べ終わりません。
終いには、いつものお母さんの噴火です! 
「いい加減にしなさいっ!早く食べてしまいなさいっ!!」
毎日これの繰り返しです。困っています。どうしたらきちんと食べ終わるのでしょう。。。
***************
さて、
「早くしなさい。」と急かしたり
「もう時間だよ。いつまで食べてるの!!」と叱ったり
「いつもあなたが最後なんだから、あなたが全部片付けなさい!!」と罰したところで
今更、食事が早くなるとは思えません。
返って、「うるさいな!」とばかりに反感を持ってのらりくらりとするかも知れませんね。
【考えて見ましょう!何故、S君だけ食事時間をオーバーしても食べ終わらないのでしょうか?】
①まずは、観察しよう!
●“好き嫌い”があるわけでも無し、TVが付いているわけでもありません。
幼稚園では普通に食べることが出来ているそうです。すると、
S君だけが、食事中にみなと違う事は何かしら?・・・と、観察してみてわかりました。
彼は最初から最後まで、食事中、一人でず~っと話し通しなのです。
S君のおしゃべりで動くお口には、食べ物を咀嚼し飲み込む暇はないのです!!

②観察したら、見つけよう!
●本当の問題はこれでした。。。「しゃべりすぎ」
③S君の苦手は?!
●S君は『早く食事を食べる事が苦手』なのではなく『黙って食事を食べる事が苦手』だったのですね。
④苦手な面は違う面から援助しよう!!
『黙って食事を食べる事が苦手』な子に「黙って食べなさい」といったところで10秒も
しないうちにしゃべり出します。

ですから、工夫をして違う面からのアプローチをします。
例えば、
*「20分間の食事中は、おしゃべりをしないで食べます。
食事が終わってデザートの時間には自由にお話しを楽しめます。」
と“お食事ルール” を作ったり。
* 「ここは高級レストラン。食事の間は、マナー良く食事をしましょう。」
と食事中にクラッシック音楽を流し“食事のマナー”を楽しく教えてみてはどうでしょう?
いつもと変わった様子に、子どもがワクワクして取り組めるように環境を整えたり、
工夫を凝らして「みんなと静かに味わう食事は楽しいものだ!」と思えるように
違う面から援助します。
日々、繰り返される困った子どもの行動は、叱ったり、なだめたり、脅したりしても何の効果も無いのです。
罰を与えてみても恨みを買うだけです。
褒美でつっても褒美に飽きたらやらなくなります。
子どもの苦手は、違う面から支援しよう!!そこには、工夫が必要です。
親が楽しみながら工夫をすると子どももワクワク乗って来るものです。
【苦手な面は”工夫して”違う面から援助する】お試しください。
2009年03月08日
春。輝いていますから。

あったかくなりましたね~
春がそこまで来ていますね~
うれしいうれしい春です!!
今日は、セシリアのミニバスの試合の応援に行って来ました。
どの子も輝いていました。 子どもの成長はすごいです。
子どもの成長はすごいです。
6年生は一回りも二回りも大きくなって、この半年間を後輩の育成に力を注いできました。
後輩達もそれに応えるよう結果を残そうと一生懸命活躍していました。

何かに打ち込む姿は、人を感動させるものですね。
子どものキラキラと眩いばかりに輝き、生き生きとしている姿は、何物にも変えがたい美しさです。
みんながドリブルするたびに心が躍り 、シュートか決まるたびに涙が出て・・・。
、シュートか決まるたびに涙が出て・・・。

「あれ?何で泣いているの?」って・・・
ア~、花粉の季節でよかったです。

セシリアは、ミニバスを始めて半年。
これまでも少しずつ試合にも出してもらえるようになってきましたが、まだ、
初ゴールは決めていません。今、むずむずとしているところです。
まるで鼻の奥でむずかるくしゃみのように、そのときを待っています。
は~は~は~っくしょ~んっ!!!と一気にそのときが来たら『ゴ~ル~!!』です。
今、貯めて貯めていますから。
輝きながらいますから。


み~んな、みんな輝いて、4月にまた一つ大きくなります。

2009年03月08日
相互理解へ近づく





皆さんは、自分自身のこと、子どものこと、家族のこと・・・
どれだけ理解していると思われますか?
「私は、自分自身のことをどれだけわかっているといえるのであろうか?
何をどれだけ理解しているというの?
我が子のことは、どうであろう?よくわかっているつもりでも、私とは別人格。
わかった振りしているけれど、我が子をわからないとしても当然。
そんな、私が他人のことを理解したいと思っても果たして理解になぞ近づく
ものであろうか?」と・・・
しかし、思うのです。
「本当に理解することなどできないとしても、大事なことは理解したいと願う思いや行動・姿勢など、そのプロセスではないかしら?」と・・・
そんな時にこんな出会いがありました。
第9回『くさなぎ井戸端会』に参加くださったあるお母さんの言葉です。
(了解を得てご紹介します。)
「私は2人の子どもとも発達障害で普通の子どもの子育てはしたことがないので、
(定型発達の子を持つ)皆さんがどのように思って行動しているのかを知る事で
私の偏りがはっきりとわかりました。
今後は、偏った考え方を減らしていけるよう普通の子どもへの理解を深めて
行きたいと思いました。」
こう言っていただいたのがとってもうれしかったのです。
活動を続けてきてよかったと思える瞬間でした。

私自身は
「“双方は、はじめから互いに違うのであるから理解なぞできるわけがない。”
と諦めて距離を置いてしまうのでなく
“違うなら、その違いに対しての理解に近づきたい。”」
と願い活動を続けてきました。
しかし、この願いは一方通行では成らないのです。
双方による『理解に近づく願い・努力』が大切なのです。
相互理解なのです。 


障害を持つ子どもの親も、そうでない子どもの親も、“子ども同士”
を真ん中において、子ども同士の関わりの中から双方が理解に近づいていけると考えます。
その可能性があることを、このお母さんは教えてくれました。
2009年03月07日
2つある「しつけの方法」

「しつけの方法」というと、いろいろあるようだけど・・・
あなたはどちら?
子どもをしつけるのに、大きく分けて2つの方法があるといいます。
①『子どもに、喜びを持たせてしつける方法』
②『支配的に、抑圧的にしつける方法』
① は、子どもを認め、励まし、ほめて勇気づけながらしつけます。
すると子どもは能動的な子になるといいます。
つまり、自主的に考えて自分から行動する子になるのです。
② は、子どもに、指示・命令・強制・脅迫をすることで支配的にしつけようとするものです。
すると子どもは、受動的な子になるといいます。
つまり、指示待ちっ子です。指示されたことは素直に行動できるが、自分から行動できない子になります。
さて、皆さんは、子どもにどう関わりながらしつけをしていますか?
2009年03月07日
孔子と子育て“長~い眼”



論語を読んでいると、子育てにとても役に立つことがでて来ます。
孔子が言われました。
『政治はどうしたらよいか。外面的な法律の力によって人民を強制したり、正しく秩序を守らそうとしても、返って法律と政府の取り締まりの抜け穴をくぐって、平気で違反をするものだ。
人民の良心をめざめさせると、人民は自ら進んで社会に秩序を守るようになるに違いない。・・・』
というのが、孔子の考え方です。
孔子は政治をするのに、外面的な法律の力によって刑罰を処せば短期間に効果を
上げるかもしれないが、人民が支持しない一方的・受動的な制度では、人民の気持ちも
離れる。しかし、人民が良心をめざめさせ能動的・主体的となれば安定した政治を司れる
であろうと考えたのですね。
孔子は政治を長~い眼で見ているのですね。
子育ても同じですね。
親は、目先の事に捉われて、早く解決したいと強制的・支配的に秩序を守らせようとしがちです。
これも子どもが小さいうちは、圧倒的に親が強いのですから、効果もあるでしょう。
しかし、いつまでもそうはいかないのです。
ある時、親からの一方的・受動的なやり方に反発・反抗するときが来るでしょう。
ですから、子育ても長~い眼で見る必要がありますね。
時間は掛かりますが、親が、子どもの良心をめざめさせるように関われば、
子どもは能動的・主体的に考え、行動できるようになるでしょう。
子どもが、能動的・主体的に考え、行動できるようになるには、親は、
子どもにはその能力があると信じて尊重し
勇気づけていく必要がありますね。


2009年03月06日
誤解される子どもたち


「何て乱暴な子?」
「親のしつけがなってない。」
「わがまま、怠惰、だらしがない」
このように言われがちな子ども達が、あなたの周囲にいませんか?
ご存知ですか?
日本においては、まだ社会的な認識が不十分で、人から理解されにくく誤解や偏見を
受けてしまうことが多い人たちがいます。
それは、軽度発達障害(現在は“発達障害”とだけ言われるようになってきています。)
を持つ人たちです。
軽度というからには、彼らの抱える『問題』は軽度なのかと捉えられやすいのですが・・・
軽度発達障害とは知的な水準が軽度という事であり、(つまり知的障害が無いか、
あったとしても軽度と言う意味)抱えている『問題が軽度』というわけでは決してないのです。
また、発達障害をもつ人たちは外見からはわかりづらい(定型発達の人と変わらない)
ため理解されにくく誤解を受けやすいのです。
そして、周囲から繰り返し受ける、非難・中傷・叱責により傷つき、
自尊心を失い自己肯定感・効力感を持ちづらくなって行きます。

このように、返って軽度なぶん、
①発見されにくい(わかりづらいため、小学校高学年になってからわかる場合もある)
②認められにくい(わがまま、怠惰、だらしがないと見られる)
③理解されにくい(問題行動が発達障害に起因している場合もあるが、ただ、乱暴な子、
しつけが悪い・・・と見られがち)
など、軽度発達障害ならではの困難やしんどさを持つのです。
つまり、軽度と言うと「軽い」のだと誤解されやすいのですが、
重度には重度のつらさがあるように軽度には軽度ゆえのつらさがあるのです。
それでは、発達障害はどのような障害なのでしょうか?
これは、機能的な脳の中枢神経系の障害で決して「親の育て方」や「本人が怠けている」というものではないのです。
彼らのは、外からキャッチする情報の処理障害があり、情報が上手く入っていかなかったり
情報刺激に過敏に反応してしまったりするのです。
その現れ方が、「乱暴な、落ち着きのない、我が儘な、だらしない、怠惰、、パニックになる、
切れる・・・」などと見て取られるわけです。
彼ら自身が
「人と同じようにできない自分はダメだ!」
「いつも叱られる僕はバカだ!」
「一生懸命やっているのにわかってもらえない!」
などと苦しんでいるのです。
周囲が発達障害の特性理解に近づくことで、少しでも互いを認め合い、それぞれの困難が緩和されればと願います。
誤解や偏見に惑わされる事なく『お互い様に、どうぞよろしく。。。』と誰もが赦し合える社会になればいいな~
そう願って、子育てを続けていきます。
2009年03月05日
チェンジリング

この衝撃的な映画は、実話だそうです。
1928年のロサンゼルスを舞台に、誘拐された息子の生還を祈る母親。
母親の強さと切なさには、心揺さぶられ涙なみだでした。

映画が終わると一目散に家に帰り、子どもの帰宅を待ちたくなりました。
そして、「毎朝どんなことがあっても『行ってらっしゃい』とハグをして
送り出したい!! 」と思ったのです。
」と思ったのです。
今朝はことのほか、心を込めてハグをすると、太郎吉もセシリアも
ニタニタと嬉しそうに『行ってきま~す。』
と出かけていきましたよ。
あわただしくも平凡に過ぎていく毎日に感謝です。
2009年03月05日
淋しくなる・・・

今日の『くさなぎ井戸端会』には、2名の保護者の方(お母さん1名、お父さん1名)が初めて参加くださいました。
新しい方との出会いの中で、今日を最後にしばらく(?)お会いできない方々もいらしていただきました。
転勤の決まった、Y・Aさん、Y・Yさん、職場復帰されるK・Nさん。
残念ながら今日お会いできなかったOさん。
この季節は、なんだか淋しい。

出会いと別れの季節です。
でも、どこに行っても同じ時代に子育てして来た仲間として、こうして悩み
分かち合ってきた事を思い出して欲しいです。
そして、これからも繋がって行きたいです。
皆さんから、多くのことを教えていただきました。
心から感謝しています。
そしてまた、違った土地に行っても多くのことを教えてくださいね。
よろしくお願い致します。
そうです。
“さようなら”ではないのです。
2009年03月05日
思春期のコップ

太郎吉(息子)は、小学校5年生。学校で先生が「思春期のコップ」という話しを
してくれたと言って帰ってきました。
太郎吉「『日頃から、親の言うことを何でも素直に“そうだ”と思って、何の反発も
せずに従ってしまっている人は、思春期という時期になると大変なことになり
とても辛い時期となります。思春期のコップから水が溢れ出してしまうのです。
溢れ出さないように日頃から上手に水を抜いていく事が大事です。』
って話しだったよ。」
みの 「上手に水を抜いていくとはどういうことだと思う?」
太郎吉 「親に反撃、反抗的になれってことだよ。」
みの 「げ~っ?そ、そういうことかい???」
太郎吉 「あはは、うそだよ。いい子ちゃんにならなくていいんだと思う。自分の考えが
親の考と違うなら反論していいってこと。」
みの 「うん。うん。で、太郎吉の思春期はどうなると思う?うまく乗り切っていけそうかい?」
太郎吉 「大丈夫さ。上手に水を抜いているもの。」
みの 「確かにね!!
ま、どっぷり、じっくり思春期をしたら良いさ。どんなことになろうと
母ちゃんの覚悟はできているもの。」
・・・ア~、大きくなっているな~。。。
ついこの前、自分の背中よりも大きなランドセルを背負って学校に行き始めたと思っていたら。。。。
今日は、5年生の太郎吉たちが企画し、実行する『6年生を送る会』というものがあります。
6年生の先輩方に、今までの感謝の気持ちを込めた催しを行います。
来年は送られる側であると思うと、今からジ~ンとしてきます。
本当に子どもの成長は早いものです。
先生、良いタイミングで『思春期のコップ』のお話し、ありがとうございました。
2009年03月04日
親支援プログラム『STEP勇気づけセミナー』体験会
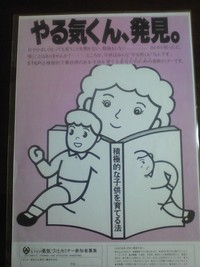
『STEP勇気づけセミナー体験会』 開催します。
ぜひ一度ご体験してみてください。
子育てのヒントが見つかるかもしれません。
日 時/ 3/12(木)9:45 ~12:00(9:35受付)
会 場/ 長崎新田スポーツ交流センター
参加費/ 500円
詳しくはHPをごらん下さい。お申し込みお問い合わせは
http://www.locoms.com
********************************
あなたがSTEPを学ぶと―――
子どもが朝、ひとりで起きてくるようになります。宿題を忘れません。
失敗を恐れないで、何にでも積極的にとりくみます。
ちらかった子ども部屋を自分でかたづけます。
ふしぎだと思いませんか?あなたがSTEPを受けたのに、なぜ子どもの方がこんなに自発的になるのでしょう?
STEPでは、まったく新しいコミュニケーションやしつけの方法、子ども勇気づけてやる気にさせる方法を学ぶからです。
あなたが新しいことを学んで、あなたがもっとすてきになって、そして、子どもがぐんぐん伸びるのです。 
■□■□■□
STEPは(Systematic Training for Effective Parenting)は児童心理学の理論やカウンセリング、コミュニケーションの手法から開発されました。
STEPを知ると、親子関係、人間関係が楽になり、子育てにゆとりが生まれ、子どものよいところがどんどん見えてきます。
STEPは各地のカルチャーセンター(朝日・読売)や行政の子育て支援、教職員、保育士の研修にも取り入れられ、子どものやる気と責任感を育てる方法として高い評価を得ています。
STEPは 「なぜ、親の言うことを聞かないのだろう?」
「なぜ、親を困らせることばかりするのだろう」
というような子育ての問題を自分で解決できるようになる考え方です。 
■□■□■□
★参加者の声・・・
・頭ごなしにガンガンどなり散らし、子供を隅へ隅へと追いやっていたことを、つくづく反省しました。(S.Sさん)
・一年前には考えられないほど、おたがいに本音でものが言えるようになりました。(T.Y氏)
・「この頃のお母さん、好き!」と言われた感激は忘れられません。(Y.Iさん)
・自分自身の心にゆとりが生まれ、感情のコントロールができるようになったことに気づき、
子供と接することが楽しくなりました。(S.Tさん)
2009年03月04日
子育ち・親育ち・・・活動の原点







東京で起業をしていましたが、結婚を機に一切を引退し、静岡で暮らすこととなり、早くも12年。
この間、子育てをしながら、人々の温かさや気候の穏やかさにおいて、
「小さな子どもを育てるのはこの地でよかった。」と思えることが多かったのです。
子どもが大きくなるにつれ、私の視野も少しずつ広がりながら、
地域の中でお母さん方との繋がりを求めていました。
そうした中で、当時、我が子と同じくらいの年齢の子どもたちの中に、
周囲に馴染めなかったり誤解を受けたりする子どもがいる ということに気づきました。
それは、発達障害を持つ子どもたちでした。
周囲からは『しつけが悪い』『何でじっとできないのか』
『すぐに暴力を振るい問題を起こす』などと言われていました。
実は、我が子も少し変わった子どもでした。公園に行っても他のお友達と
あまり交わって遊ばない為、私もなかなかお母さん友だちができなかったのです。
子どもたちを眺めていると、小さいながらもみんな個性があって、どんな子どもも素敵でした。
それなのに、およそ母親というものは、みんなと同じでないと心配になるものです。
どんな親も、子どもの発達や発育には不安を持つものです。
『みんな違って、みんないい』と思う勇気は、子どもが小さければ小さいほど持ちづらいものでした。
『みんな違って、みんないい』は『みんな違うから、みんないい』のではないでしょうか。
そんな思いから自分の子育てを通して発達障害の理解に近づくことで、誤解や偏見のなぞを解きたいと考えました。
そして、今、少しずつですが発達障害という言葉を耳にする人も増えてきました。
しかし、まだまだ「誤解や偏見が減って、誰もが自分らしく尊厳を持ってこの土地で生活できるようになってきた。」
とまでは言いがたいのです。
全ての人が、自分らしく生きていくためにも、互いの違いを理解していこうとする視点を大切にしたいと考えます。
2009年03月03日
さぎのよう・・・?

こりゃ、一体全体・・・鷺ではなくて詐欺ですよ。
むむ・・・物騒ですと?
違いますわよ。
プリクラを10年ぶりに撮りましたの。
魔~、すごい進化しているのには驚き!!
『え~、400円?高い!!』なんて思いきや、うそ。うそ。
1回400円であんなにきれいに嘘っぱちに撮れるなんて・・・
う。うれしい~ィ~~。って感じでしたよ。
もう、お見せできないのが残念ですわ。
実は、自分のお財布を持ち始めたセシリア(娘)が、
『今年から毎年お母さんの誕生日には、二人でプリクラを撮りましょう。
私からのプレゼント 』
』
と言ってくれたのです。
ん~、毎年誕生日には、厚化粧したみのが、ゲームセンターで
『はい。ち~ず。。。』か・・・・なんて想像していましたが、とんでもない。
化粧は、ほど程でも15歳はサバ読めますから大丈夫です。
出来上がった写真は、15年前のみのでしたもの。ぬはは。。。
人生正午(半分)を過ぎた皆さん、是非プリクラとって、
過ぎ去ったあの頃に戻ってみましょうよ~。


2009年03月03日
ゲームを通して子どもを育てる②

【責任感を育てる】
昨日の続きです。 『ルールを守る』という事から、責任感を育てることができます。
以下は一例です。まずは、
●『ゲーム遊びのルール作り』
親子、双方がある程度譲歩しながら、“勝ち負けなし”の納得の行くルールを作ります。
一方的に親が決めるのでなく、ルールを守るべき子どもの意見も尊重しながら、
お互いに無理のない物を作ります。
ルールつくりに参加して自分で納得したものに関しては、子どもは守り抜きたいと思うものです。
そして、ルールが守れないときにはどうするかも決めておきます。
●子どもへの言葉がけ
*『ルールが守られたとき』には・・・
「ルールを守るってどんな気持ち?」
「お母さんは、あなたはを信頼しているわ。だって、自分で決めたことをきちんと守って
いるのだもの。偉いと思うのよ。」
と、子どもに気持ちを尋ねたり、喜ばしい気持ちを伝えたりしましょう。
*『ルールが守られなかったとき』には・・・
親は毅然と、そして心穏やかに
「あなたはまだ、責任を持ってゲームで遊ぶことができないようね。」
(何故なら、自分で作ったルールを守れないということなのだから。)
「ルールを守りながら責任をもって遊ぶか、責任が持てないのなら、
ゲーム遊びはできないわよ。」
と言うことを伝え、
『自分の欲求を満足させたければ、それに責任が伴うのである。』
ということを同時教えていくのです。
●親の態度
子どもがどうしてもゲームをしたいという場合に、怒ったり、泣いたり、わめいたり、
子どもが感情的に親に対してきたとしても、親はそれに乗ってはいけません。
つまり、叱ったり、なだめたり、あきらめたり、あわれんだり、例外を作ってみたりという、
今までしてきた態度をやめることです。
そして、親は、毅然と平然と心穏やかにしていることです。
自分のことに没頭したり、子どもの前から離れてみたりして、
子どもの感情に巻き込まれないように努めることです。
そうすれば、子どもは「今までのように感情を利用しても親を動かす事ができない。」と気づくでしょう。
何よりも、親がぶれない事が大事です。
親が、ゲームについて『我が家のルール』をしっかりと考えてみること。
子どもに対する自分の態度をふり返ってみることです。
親は、子どもに根負けしないで、子どもが、最後までやり遂げるよう、
励ましながら、子どもを見守ることですね。
2009年03月02日
ゲームを通して子どもを育てる①

ゲームは楽しいですね。
大人も虜になってしまい時間を忘れてやってしまうこともありますね。
ですから、子どもがゲーム遊びに依存していくのもよくわかります。
しかし、大人がゲーム遊びをすることと、子どもがゲーム遊びをすること
では、どこがどう違うのでしょうか?
ゲームをしている間は、ワクワクしたり、ドキドキしたり「しまった!!」と思ったりと
感情が大きく変容します。この刺激は、子どもにとってはたまらないものなのでしょうね。
こうして、ゲーム遊びをすることは、やめられない刺激となって習慣化していきます。
大人もタバコや麻薬は、身体によくないと知っていながらもその刺激を受けることを
やめられなくなり依存していきます。
子どものゲーム遊びにも、この依存性があるということです。
大人になればゲーム遊びをコントロールしながら生活の中に上手く取り入れていくことができます。
しかし、子どもがゲーム遊びをコントロールできるようになるには、
自分自身をコントロールする力が育っていないとできないことです。
私の経験を通してのことですが、子どもが『ゲーム遊びのルールを守る』ということを通して、
自分自身をコントロールする力をも育てていくことができると思います。
また、『ルールを守る』という事から、責任感を育てていくことができます。
ゲームはやめられない、取り上げられないものなら、ゲームをうまく使って
子育てして行く方法を考えたいものです。
2009年03月01日
子どもの遊び環境

子どもの遊びの環境は昔とは大きく変化してきていますが、
その中で「どうする?ゲーム遊び」という親の悩みをよく耳にします。
子どもがゲームをやることで困っているという親の声・・・・
「時間を守れない」
「ゲームの事ばかり考えている」
「人の目を盗んでもやる」
ゲームを与えるときに、はじめに約束した(例)・・・「一日30分、宿題の後」
などという取り決めは途中で崩れるて来る事も多いようですね。
そして、親は、口うるさく、ガミガミと言ってゲームのルールを守らせようとしますが
、効果はありません。
親は自分の過去を振り返ってこうもいいます。
「私も何時間もやったから、わかるわ。」
「いずれあきるでしょう・・・」と・・・。
しかし、問題は、ゲームをやるということよりも、ゲーム以外に
興味を持たなくなることにあるといえないでしょうか?
つまり「自分の好きな事は、ゲームしかない。」ということに問題があると考えます。
『ゲームも好きだけど、読書も好き。』あるいは、
『ゲームも好きだけど公園で遊ぶのも好き』
というのであれば、いずれゲームにあきる時が来るかもしれません。
しかし、そうでなければ、なかなかゲーム遊びを自分でコントロールしていくのは難しいようです。
親は、子どものゲームをあり程度監視しながらも、子どもがゲームの他にも
「自分にとって気持ちいい・好きな事」を持てるようにと関わる事が大事だと考えます。
我々の子ども時代と違って、子どもの育つ環境は大きく変化しています。
昔は、今と違って周囲は刺激にあふれていました。近所の仲間と遊ぶこと。
放課後の校庭での遊び。川でメダカとり。自分たちの基地作り。・・・・
自分でワクワクする事を見つけ創り出すことの出来る環境がそこにはありました。
今の時代は、子ども自身がワクワクする経験を遊びの中から見つけ出すことが難しいようです。
ゲーム遊びに依存していく環境にあるのです。
親はそのことを頭に入れながら、子どもが上手にゲームと付き合えるようにして行くことが大切だと考えます。
写真出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)